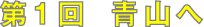
10月某日、
青山通りを渋谷方面へ走っていく
ひとりの女性の姿があった。
東京糸井重里事務所のスタッフ、中林である。
彼女は東京糸井重里事務所の
引っ越しプロジェクトのリーダーを担当していた。
いわゆる「引っ越し大臣」である。
引っ越し大臣、中林は、
人混みをかきわけながら、青山通りを急いだ。
今日は、事務所の移転先となるビルの内覧日なのだ。
「私たちの新しい職場は、
いったいどういう場所なのだろう?」
それは職務以前に彼女の純粋な好奇心であった。
汗ばみながら、中林は目指すビルへ入り、
エレベーターでそのフロアーへ移動した。
「遅れてすいません!」
そこに、中林が見た光景とは‥‥。

「ひ、ひろぉーーーーい!」
青山のビルに、中林の絶叫がこだました。
道行くオシャレな人たちが数人、
その声に気づいて思わずそのビルを見上げたという。
話は、数ヵ月前にさかのぼる。
糸井重里は苦悩していた。
彼の前にはいくつかの選択肢があった。
そしてその選択がとても重要なものであるということを
彼は深く理解していた。
魚籃坂にある明るいビルの4階が、
「ほぼ日刊イトイ新聞」を生み出す場所として、
もはや手狭になっていることは誰の目にも明らかだった。
──4年前は、と糸井重里は思った。
4年前に引っ越してきたとき、
彼を含む数名の乗組員は、
明るいビルの広さに戸惑ったものだった。
家具も人も少なく、真新しいオフィスはがらんとしていた。
──それが、いまはどうだ。
乗組員の数は倍増し、訪れる客の数は増え、
広かったはずのフロアーは
いつの間にか飽和するようになっていた。
どうしようもないほどに狭くはない。
けれども、会社の発展を目指すとき、
未来に大きなビジョンを描こうとするとき、
いまこそ移る契機であると彼は強く感じた。
糸井重里の前には
いくつかのビルの図面があった。
移転先の候補は、最終的に4つにしぼられた。
彼はいずれの場所にも足を運び、
その立地と環境をしっかりとたしかめた。
どこも悪くない。
しかし、選ぶべき地はただひとつ。
それは、どこだ?
彼は眉間に深くしわをよせ、
伸びてきた短いあごひげを落ち着きなくいじった。
と、そのとき、運命の稲妻は彼の頭上に落ちた。
びかびかと火花を散らす強い電気の流れは
瞬時に彼の背骨をつらぬき、
靴底でバウンドして心臓へと戻った。
それは動悸となって彼の体内の血液を押し、
ヘモグロビンは酸素以外のなにかを乗せて
動脈中をせわしなく行き来した。
糸井重里の体温が1度、上がった。
つまり、彼はひらめいたのである。
彼は叫んだ。
魚籃坂の、明るいビルの4階で。
「つぎは、青山だーーーーーっ!」
その声に驚いて、
魚籃坂の買い物帰りのオバチャンが
明るいビルを思わず見上げたという。
青山のビルの内覧から数週間後、
引っ越し大臣、中林はある男と向かい合っていた。
男の名前は飯島直樹。
東京糸井重里事務所のオフィスの
内装を手がけるデザイン事務所、
「飯島直樹デザイン室」の社長である。

「フローリングは無理ですね」と飯島は言った。
中林は食い下がったが、飯島の判断は理路整然としていた。
「ここはいわゆるオフィスビルなので
もしフローリングを希望するとなると
下の階から防音面についてクレームが来るでしょう。
なにより、床下にLANケーブルなどの
配線を通すとすると、当然、
床を5センチくらい上げなくてはなりません。
フローリングにするのは不可能です」
中林はため息をつき、つぎの話題へ移った。
引っ越しが現実的な話となり、乗組員たちは
口々に新しい職場への要望を述べるようになった。
それを実際に内装に反映させていくのが
引っ越し大臣の役目である。
しかし、前途は多難だった。
「会議室がもっとほしい」
「倉庫は広くなるのか?」
「簡単な切り貼りができるスペースがほしい」
「簡易撮影スタジオがあると最高」
「仮眠室は?」
「テレビをきちんと観られる環境がほしい」
「いっそプロジェクターを」
むろん、すべてを叶えることはできない。
夢物語としてわいわいと語る乗組員とは違い、
中林の目に映るのは現実のビルだった。
飯島と中林のやりとりは長く続いた。
広いビルをどのように区切るのか?
応接スペースはどのくらい必要か?
いまある家具や什器はどのくらい流用できるのか?
セキュリティーは? 動線は?
日をあらためながら打ち合わせは何度もくり返され、
そのたびにビジョンは少しずつ現実的になっていった。
そしてある日、飯島は言った。
「‥‥だいたいのところはわかりました。
もう期限がありませんので、
ご希望のところをできるかぎる反映できるかたちで
図面をひき、モック(模型)を作成しますよ。
それを見てください」
その数日後、ついに、新しいオフィスが、
モックというかたちで中林の目の前に現れた。
「おーーーーーーーっ!」
その叫び声には
驚きのほかに感嘆の感情が込められていたため、
魚籃坂を行く買い物帰りのオバチャンたちは
明るいビルを見上げたりはしなかったという。
(つづく‥‥)
2005-11-03-WED |
|
|
|