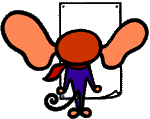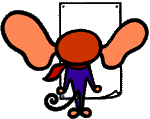|
Thanks!
撮影:glico

68枚目: 「hana-bi」
線香花火が落ちるようにあっさりと。
九月に入ると、もう夏は終わりだと
物わかりの良い人達は言う。
夏の終わり。ビア・ガーデンで、
ガラス越しのような他愛も無い話をしながら
今年は下から花火を見た。
横から見ても、下から見ても
花火はマンマルイって知ってた?
私は小さい頃。
中国人になりたいと思っていた。
手に色の移る花火の紙をむしると
そこには見たこともない
漢字がびっしり書かれた紙が入っていて
きっと花火職人には中国人じゃないと
なれないんだと思った。
海辺の小さな町の港には
不釣り合いに巨大な貨物船がいつも停泊していて。
荷物にしのびこんで海の向こうに行くことを
消波ブロックに座って夢見てた。
十四歳の時。
公開模試でC判定だった私は夏期講習に補習。
楽しみにしていた花火大会にだって
外出禁止でぶうたれたまま新学期を迎えた。
すっかりコートを着て歩くようになった頃。
同じ中学の彼が駄菓子屋で安売りしてたんだといって
ファミリー花火セットを両手にやってきた。
誰もいない砂浜に自転車を走らせる。
「雨の中でも使えるんだぜ。」
彼の自慢のドイツ製ライターで火をつける。
線香花火でおしまいだなんて納得できないで、
私は花火の袋に入っている厚紙だとか
浜に落ちてる燃えそうなものを
つぎつぎと片っ端から燃やした。
花火なんだかたき火だか分からなくなってきて
ただ踊りながら形が変わっていく
ビニールの光をみつめる。
「ばか!毒ガスが出るんだぞ」
彼はどなって私を押し飛ばすと
青い火をちろちろ出して縮んでいくビニールを
砂浜に踏んづけた。
こんな田舎から出ていきたい。
あんなにも願っていた夢。
彼はあの田舎町で今年も花火をしては
違う女の子の肩に手をかけて
同じ事を思い出しているんじゃないかとうぬぼれる。
天上に吸い込まれそうに降る光。
いまだって遠くに行きたいという想いは
変わってない。
シル (shylph@ma4.justnet.ne.jp)
from 『深夜特急ヒンデンブルク号』
|