たとえば、ボクが大きなお店よりも、
小さなお店を好む理由。
200人ものお客様の中から、ボクだけ見つけて‥‥、
っていう努力。
するだけ無駄な、大変な努力であるに違いありません。
それにそうしたお店のほとんどは、
正社員よりアルバイトにたよった運営をしていたりする。
毎回、行くたびに違った人が働いている。
せっかく顔見知りになったのに、
気がついたらその人がお店をやめていた。
というようなことがしばしば起こったりするのですね。
だから小さなお店。
それも、できることなら
家族で営業しているようなお店が好き。
たとえば、ボクがチェーン店よりも、
個人経営のお店を好む理由。
お店の中で一番知り合いになりたい人。
それは店長。
あるいは、調理長と呼ばれる人だろう‥‥、と思います。
だって彼らが一番、
お店の中でたよりになる人なのですから。
特に店長。
フランス料理などの専門店では、サービス長。
家族経営のお店であれば、たいてい、マダム。
あるいは時にしてチーフソムリエが
その役職を兼務したりしますけれど、
今日一番おいしい料理であったり、
それぞれの料理の一番おいしい食べ方だとかを
よく知っているのは、彼らですから。
店長が耳元でささやく一言。
この上もなくシアワセなる天使の声。
‥‥、のようなものなのでありますね。
ところがチェーン店という組織。
「長」と呼ばれる人から転勤になるようにできている。
店長は会社から来ている人で、
会社にもどっていく人だったりする。
すべてのチェーン店の店長が、
お客様のことより、会社のことを優先しながら
仕事をしてるか、というと決してそんなことはない。
お客様との人間関係をたのしむことが大好きで、
それで仕事している大きな会社の店長さんもたくさんいる。
けれど、やっぱり、人と人の
より濃厚な結びつきのことを考えるなら、
チェーン店より、個人のお店を選んでしまう。
それから、ボクと同じくらいの年齢の人が
働いているレストランが好き。
それも友達つきあいをする関係といえば、
やはり年が離れすぎていない方が、
自然であるからだったりするのですね。
こじんまりした大きさの、
家族経営の気のいいお店で、
しかも若い人が一生懸命仕事をしている。
そんなお店をみつけては、
何度か通ってよい印象を残して帰る。
王道中の王道‥‥、であろうと思います。
で、ちょっとずるい、
でもちょっと賢い工夫の話をいたしましょう。
  |
今のボク。
坊主に近い髪形で、髭を生やしていて
にこやかな、小太りのおじさん。
‥‥、目立ちます。
ボクは取り立てて覚えてもらおう、
としているわけではないのだけれど、
どうも印象に残りやすいようで、
初めてのお店の人にも覚えてもらい易いみたい。
ちょっと得をしているのかもしれないです。
でも昔。
今みたいな目立つ存在ではなかった頃。
それでもボクは、自分のことを覚えてもらおうって、
一生懸命。
とあるレストランで試行錯誤をしていました。
ファミリーレストランチェーンのひとつ。
九州の方からやってきて、まだ東京には数軒しかない。
だから、チェーン店ではあったけれど、
まだ家族経営のお店のような
親密で情熱的な雰囲気が色濃くあった、チェーン店。
その一店舗。
ボクの家の近所に出来たばかりのお店でのコト。
ボクがする、ちょっと変わったリクエストが、
実はボクのことを、
そのお店の人たちに強烈に印象付けることとなった。
きっかけは偶然でした。
 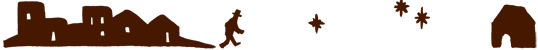 |
この店。
当時のファミリーレストランのご多分に漏れず、
お替り自由のコーヒーのサービスをしていました。
だからまずテーブルに座ると
最初にたのんで持ってきてもらうのはコーヒー。
あらかじめ熱々に温めたカップに、熱々のコーヒー。
猫舌ではないけれど、
コーヒーをふうふうしながら飲むのが苦手なボクは、
いつもこうたのんでました。
コーヒーをください。
できれば氷を一個だけ、
それに入れて持ってきてくれるとうれしいんですけど。
ファミリーレストランの
なかなか溶けづらくできている頑丈なアイスキューブ。
それを浮かべたコーヒーは、
ちょうどボクの手元に届く頃、氷がほとんど溶けている。
もうひと舐めで、ボロッと崩れてしまうくらいにまで
舐めすすんだドロップみたく、
なめらかにカップの表面にユラユラ、揺れる。
その最初のひと啜りは、ちょうど適温。
ふうふうせずとも、スルンと喉に流れ込んでゆく。
なら、最初からぬるいコーヒー。
あるいは、水で薄めてもらったコーヒーをもらえば
いいようなものでありますけれど、
二口目にはしっかり熱いコーヒーを楽しみたかった。
そんなワガママを満足させるための、
ちょっとした一工夫なので、ありました。
そのレストランで注文をする最初の一品。
それはいつも、氷入りコーヒーでした。
行くたびにそれ。
まずはそれをたのんで、
それからメニューをじっくり眺めて、
何を食べようとそう考える。
それが「ボクのいつも」であったのであります。
あるときまでは。 |

