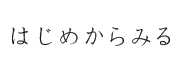第93回全国高等学校野球選手権大会は 思えば、ぼくは神宮球場で行われた けっきょく、 8月20日、日大三高と光星学院の決勝戦を、 試合がはじまる時間を勘違いしていて、 スコアブックをつけるつもりもなく、 それで、変な言い方だけれども、 とはいえ、観ているうちに 野球のルールをまだよく把握しない長男は、 親がなにかに夢中になりすぎると、 『はなかっぱ』が観たい、という下の子を 最後の打者は背番号12。 真っ直ぐで終わりたいだろう、と、 最後の直球は145キロ。 すべての高校の夏が、ここにつながっていた。 |
| 第93回全国高等学校野球 選手権大会 |
 |
 |
今年の甲子園は、ほんとうにおもしろかった。 延長戦は歴代最多タイとなる8試合。 個人的には、 歓喜の輪を見届けて、閉会式を観ることはあきらめる。 |
 |
スポーツのなかで 個人的な結論のひとつは、 野球では、しばしばプレイが止まる。 そこで、観る側は、 そのとき、「祈り」は、 たとえば、「勝て」よりも、 言い方を変えると、 たとえば、3点差で負けているときに、 なぜなら、それでは1点しか入らない。 そうではなくて、「勝て」と願うにあたり、 3点差で負けている最終回では、 そう、2点を追った聖光学院の |
 |
「具体的に祈れるようになるというだけで、 これは、糸井重里が以前書いたことばで、 そう、具体的に祈れるというだけで、 だからこそ、 具体的に、甲子園出場を祈るチームもあるし、 そして、今年の福島の夏が特別だったのは、 |
 |
福島について、考えることは難しい。 壊れた街が復興へ向かって進むとき、 でも、福島については、具体的に祈ることが難しい。 けれども、いま、少し、ぼくは違う。 ぼくは、この連載をはじめるときよりも、 誰かの考えを鵜呑みにするのでもなく、 けれども、その祈りはぼくにとって たとえばぼくは、 |
 |
たとえばぼくは、 |
 |
たとえばぼくは、 |
 |
そして、1ヵ月前よりは、より具体的に、 |
 |
そんなことは当たり前だし、 |
 |
警戒区域での移動中に、 |
 |
福島第一原子力発電所。 感覚はにぶく、具体的な思いは生まれなかった。 |
 |
経験した福島の特別な夏は濃密で、 大事なことは、この夏のはじまりに、 その夏も終わろうとしている。 |