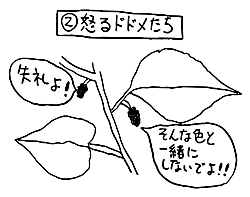| 小林 |
「どないしたんや、北小岩。
ええ男が小鳥のようになくんやない。
まあ、話したいというのなら、
その理由を聞かんでもないが」 |
| 北小岩 |
「実は叔父が描いた線画に、
着色を頼まれたのです。
誠心誠意臨んだのですが納得いただけず、
お前には失望したと言われてしまいました」 |
| 小林 |
「へんやなあ。
思うにお前は日本有数の塗り絵の名手や。
それほどの技で満足できないのなら、
叔父さんの目が節穴なんとちゃうか?
いったいどんな色を指定されたんや」 |
| 北小岩 |
「世紀末的な迫力を出すために、
空をドドメ色にするようにと言われたのです」 |
| 小林 |
「ドドメ色か・・・。
それはまだ人生経験の浅いお前には、
表現しきれんやろな。
どれ、見せてみい」 |
北小岩くんは叔父が激怒したあげくに
くしゃくしゃに丸めてしまった絵を差し出した。 |
| 小林 |
「ははあ。
叔父さんはこれを見てこう言うたんやろ。
俺が味わったドドメは、
もっと地獄のような色をしていたと」 |
| 北小岩 |
「その通りです。
なぜお分かりになったのですか」 |
| 小林 |
「お前よりはさまざまなモノを
見てきとるからな。
ドドメ色に関しては
様々な角度からの考察が必要やで」 |
先生は年代の違う三人の男を呼び、
取材することにした。
一人目は色のプロフェッショナルである印刷会社の若者。
二人目が若い頃遊び人としてならした
80歳のおじいさん。
最後の一人は幼稚園の年少組に通う男の子である。
まずは印刷会社の若者に訊ねた。 |
| 印刷若者 |
「ドドメ色ですか。
残念ながら色見本にはないですね。
でも僕の印象でいいますと、
もう少し明るい色なんじゃないですか?」 |
| 小林 |
「君は今まで
なかなかええ人生を歩んでいるようやが、
まだまだ甘いな。
まあ、遊び人のおじいさんなら
君の何百倍もの体験をされているだろうから、
地獄絵巻のようなドドメ色をご存知なはずや」 |
| おじいさん |
「いんや、わしの思い出の中のドドメは、
もっともっとピンク色じゃな。
北小岩さんのこの色は何ですか。
わしの美しい記憶の中では、
そこはうす〜く透き通るような
愛らしい桃色で・・・」 |
 |
| 小林 |
「らちがあかんな。
このじいさんは本来なら
とんでもないドドメの目撃者なはずやが、
余命を楽しく生きるため、
脳がドドメ色を濾過して
美しい色として刷り込んどるんや。
ほな、まだ経験のない幼児はどうやろ。
ぼく、この空のような色を見たことあるかいな?」 |
| 幼児 |
「あっ、この色、
おかあさんと一緒に行ったお風呂屋さんで
いっぱい見たことあるよ。
でも、ぼくこの色お化けみたいで怖いんだ。
わ〜、怖いよ〜〜〜」 |
幼児は北小岩くんの描いたドドメ色を見て
泣き出してしまった。 |
| 小林 |
「そんなことで泣いとったらあかんで。
これからの人生、山ありドドメありや。
なあ北小岩、ドドメ色といえば
やはり男にとっては
どうしても秘所の色ということになるやろ。
それぞれの体験によって違うわけやから、
これ以上追求してもしゃあないわな。
十人十ドドメ色や。
言いかえれば、ドドメ色というのは
幸せの黒い鳥なのかもしれんなあ。
男たちは幸せを得るために、それを探し求める。
だが、やっと捕まえたと思ったら、
それはただの黒ずんだ鳥となってしまう。
男は永遠に幸せの鳥を追いかけ続けるんやが、
今度こそはと思ってのぞいてみても
それはやはり恐ろしげな黒ずんだ鳥でしかない」 |