| 北小岩 |
「冷えますね」
|
アゴがはずれそうなほどゆるみきった顔で
町を散歩しているのは、弟子の北小岩くんであった。
|
| 北小岩 |
「しかし、30分ほど早足で進むと、
身体の奥から
ポカポカしてくるのでございます」
|
おばあ
さん |
「そこのかわいらしい子」
|
| 北小岩 |
「は?」
|
おばあ
さん |
「あなたのことよ」
|
| 北小岩 |
「わたくしでございますか」
|
おばあ
さん |
「他にいないでしょ」
|
| 北小岩 |
「わたくし近頃、
便器のフタに似ていると
よく言われるのでございますが、
かわいいと言われたのは
遠い昔のこと」
|
おばあ
さん |
「ともかくこのサツマイモ、
あげるわ」
|
| 北小岩 |
「ふたつもいただいて
よろしいのでございますか。
これだけあれば、
先生とわたくし
三日間は生存できます。
ありがとうございました!」
|
弟子はダッシュで家に戻ると。
|
| 北小岩 |
「先生、おイモをふたつ
手に入れました」
|
| 小林 |
「でかしたぞ!
さっそく焚き火や!!」
|
師弟は落ち葉などを速効でかき集め、
火打ち石で火をつけた。
|
| 北小岩 |
「破れてしまったエロ本を
少しだけくべると、
おいしくなるのでございますね」
|
真偽のほどは、定かではない。
|
| 小林 |
「そろそろええかな」
|
| 北小岩 |
「あっ、
門から焚き火研究家の
珍火燃得流
(ちんびもえる)さんが
入ってきました」
|
珍火
燃得流 |
「珍しいな。
焚き火をしているのか」
|
| 北小岩 |
「そうでございます。
珍火さまも、
おイモをひと口いかがですか」
|
珍火
燃得流 |
「ありがとう。
でも君たちの三日分の食糧に
手をつけるわけにはいかないな。
それより、
ここから20キロ離れた山で、
幻想的な焚き火の風景を
見ることができるんだが、
行ってみないか」
|
| 小林 |
「ええかもな」
|
三人は炭になった木を股間に押し当て、
その恐怖を原動力に
20キロ離れた場所まで走った。
|
珍火
燃得流 |
「近づき過ぎずに、
ここから眺めていよう」
|
日は暮れ、
ふたつの焚き火だが煌々としている。
|
| 小林 |
「むっ、なんやあれは!」
 |
| 北小岩 |
「たくさんのおちんちんが、
じっと火を見つめております!」
|
| 小林 |
「もうひとつの焚き火では、
たくさんの金玉が
火のまわりを転がってるで!」
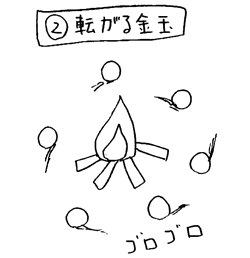 |
いったいこの光景は、
何を物語っているのだろうか。
あまりに荘厳なために、
いつしか師弟の目から涙がこぼれていた。 |



