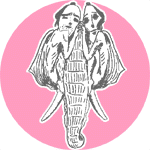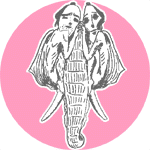| 糸井 |
『真夜中の弥次さん喜多さん』は
もし、宮藤さんが飽きてなければ
続編をつくったらいいと思いますよー。
|
| 宮藤 |
あ、はい。そうかもしれないです。
しりあがりさんが前に
おっしゃってたことなんですが
『弥次喜多』っていうコンテナには
なにを詰め込んでもいい、って。
極端に言ってしまえば
もう2人は旅をしなくたっていいし、
この2人じゃなくてもいいし、
過去でも現代でもいい。
だから続編をつくろうと思えば
いっくらでもつくれるんですよね。
|
| 糸井 |
「この“こころ”でやったんです」
と言えばいいんですもんね。
|
| 宮藤 |
そうですね、
こころを間違わなければ。
|
| 糸井 |
こころだね。
現場は、おもしろかったでしょうね。
|
| 宮藤 |
現場は常にたのしくて、
1ヶ月半、
お祭りが続いているような感じでした。
お祭り中だと
なにがあっても楽しいっていうか
だれかが遅刻しても、
お祭り中だから
怒る気にもならないというような感じで。
和気あいあいとしていたから、
本当に浮かれてるうちに
終わっちゃったなって思います。
で、その後の編集で
悩んじゃったんです。
|
| 糸井 |
撮影しているときは、
後でだれかが編集してくれるような気分で
撮ってるものなんですか。
|
| 宮藤 |
そうですね。
そんな気がしてました。
|
| 糸井 |
でも大間違いだったんでしょう(笑)。
|
| 宮藤 |
はい。
ホン(脚本)書いているときも、
正直、だれかが監督をやってくれると
思ってましたからね。
|
| 糸井 |
え、このホンを書いてるときに?
|
| 宮藤 |
ええ。
そうでないとできないな、と思って。
ホンを書いてたときは
自分がこの映画を撮るということを
忘れたとまでは言いませんけど
ないものと考えていました。
|
| 糸井 |
ぼくはこの映画を見ていて
じぶんの書いた脚本が
映画でやられることって
本当にオソロシイことなんだと
思ったですよ。
宮藤さんはどうでした?
|
| 宮藤 |
今までどおり脚本家としての
ぼくだったら
ホンを書き終わったときに
そこそこ達成感があったと
思うんですけど。
今回は逆で、達成感というより
「不安なものをつくっちゃったな」
という気持ちがつよくて。
急に「監督」の立場に
変わっちゃったっていうか。
じぶんのホンを撮るというよりも
あのホンがあまりにも難解な‥‥。
|
| 糸井 |
自由な(笑)。
|
| 宮藤 |
自由で難解な。
ぼくがいくらスタッフの方に
説明したところで
わけわかんないものを
「わけわかんないもの」として
説明してるだけなんで、
けっこう大変でしたね。
たとえば、弥次さんと喜多さんの手が
つながってしまうシーンがあるんですけど
スタッフの方たちに
「今、幻覚と現実のどっちですか?」
って聞かれて。
どっちかわかんないってことで
行きたいんだけど、
便宜上「幻覚です」って
言っちゃったりとか(笑)。
そういうことはけっこうありました。 |
| 糸井 |
脚本家がどういうふうなことを思って
書いたのかということを、
うまく説明できないような脚本を、
まず脚本家・宮藤官九郎が書いちゃって、
宮藤監督は脚本家の宮藤さんに
それを質問することが
できないっていうことですよね。
|
| 宮藤 |
ええ。それで撮影中
やっぱりわかんなくなっちゃって
「一回家帰って
冷静になっていいですか」
ってことをよく言ってましたね。
|
| |
 |
| 糸井 |
いつも宮藤さんが脚本を書くときは
「ここまでオレがやっておいたから
後はみなさんでたのしくしてね」
って感じなんでしょう?
「オレの言うとおりにやれよ」っていう
命令的な脚本ではないんですよね。
|
| 宮藤 |
ぼくは、どうぞみなさんで
好きにやってください、というほうです。
ト書きも少ないですし。
|
| 糸井 |
その、書いて渡した脚本が
人の手によって映像化されるたのしさを
知ってる人が
映画監督をやっちゃうというのは‥‥。
|
| 宮藤 |
ああ。はい。
ぼく、監督として
現場でけっこうセリフを削ったりして
脚本をいじりました。
|
| 糸井 |
あ、そうですか!
|
| 宮藤 |
ええ。現場で
いらないセリフが多いなぁって思って
後でぜんぶじぶんが責任をとるわけだから
「このセリフいらないです」と言って、
その場で変えてました。
後で冷静な頭に戻って編集するときに
ホンのほうが正しかったということが
何度かありました。
現場でカットしたセリフが
じつは必要だったりして、
あれ? 余計なことしちゃったなって。
|
| 糸井 |
それは、脚本家の宮藤官九郎のほうが
監督、宮藤官九郎より
ベテランだったってことだね。
|
| 宮藤 |
そうなんですよね。
そのときちょっと「さすがだな」って
思ったんですよ(笑)。
脚本にかんしては
ヘタに数やってないなというか、
いちおう考えて書いているなぁと思って。
このとおり撮っておけばよかったなぁ、
というのが何カ所かありましたね。
|
| 糸井 |
その、後から必要だと思ったセリフは
まるっきり撮ってなかったんですか?
|
| 宮藤 |
ええ、撮ってなかったです。
|
| 糸井 |
はははは!
|
| 宮藤 |
撮ってないから編集でうまいことつなげて、
そのセリフがなくても
成立するようにしてもらいました。
|
| 糸井 |
ということは、
この映画をつくるときに
いちばんたいへんだったのは、
最後の編集ですか?
|
| 宮藤 |
そうですね、ぜんぶのシワ寄せが来たのと
CGの制作に半年くらいかかったのかな。
CGの作業をやっている部屋に入ると、
真っ暗なところで
コンピュータ見てる人たちがいて、
日が経つにつれて、
どんどん目がくぼんできたんです。
彫りが深くなって、最終的には
“全員平井堅”みたいになっちゃって(笑)。
そこでけっこう、
無意識に監督っていうことに
浮かれてたんだなって思いました。 |
| 糸井 |
監督って浮かれる仕事ですよね。
|
| 宮藤 |
そうなんですね。でも最初は
とりあえず現場に監督する人がいないから
ぼくがやってますよ、みたいな
スタンスだったんですよ(笑)。
知らない人が現場に来たら
誰もぼくのことを監督だとは
思わなかったと思います。
監督のイスをつくってもらったのに
ほとんど座らずに
現場をウロウロしてましたから(笑)。
さすがに毎日のことなので
「監督」と呼ばれることに
慣れてきたんですが、
ぼくは役者もやるので、
今度は役者として違う現場に行っても
どこかから「監督」って聞こえると
返事したり、振り向いたり
しちゃうんですよね。
|
| 糸井 |
じゃぁ今、野球場に
野球見に行ったりしたら
‥‥「監督!」
|
| 宮藤 |
「はい!」なんて。
|
| 糸井 |
しりあがりさんが
『弥次喜多』を連載していた時代は、
「この漫画、わからないからわからせろ」
なんてことを言う人はいましたか?
たとえば編集者も
「いやぁ、わかんなくなっても
かまいませんよ」
というような感じで
進行していったのかなと思うんですけど。
|
しり
あがり |
えっと、ぼくだけが心配してましたね。
|
| 糸井 |
ああー(笑)。気がちっちゃい!
|
| 宮藤 |
漫画って、
たとえばしりあがりさんが
連載してる雑誌のなかに
ものすごくわかりやすい作品があったら
「オレのはわかんなくてもいいや」という
感覚はあるものですか?
『スラムダンク』があるから、
オレはちょっとくらい
わかんなくてもいいや、とか。
|
| 糸井 |
分担(笑)。
|
しり
あがり |
雑誌をつくってる側が
読者層を広げるために、
この作品にはこういう読者、
こっちの作品には
わからないもの好きな読者、
というふうなことを考えている場合は
あると思います。
でも不景気になってからは
余裕がなくなっていて
雑誌そのものの種類が
細分化されているような
気がしますね。
|
| 宮藤 |
今は雑誌がきっちり分類されすぎていて、
興味がなければ
その雑誌自体を買わないから
じぶんの興味が薄い漫画は
どんどん触れる機会が減って
読まなくなっちゃいますよね。
|
| 糸井 |
すごくマーケティング的ですよね。
|
しり
あがり |
『弥次喜多』は連載中は
ぜんぜん反響なかったんですよ。
|
| 宮藤 |
ええええっ、そうなんですか?!
|
しり
あがり |
うん。ぜんぜん。
でも、単行本になったときに、
糸井さんから
直接お電話いただいたんですよね。
|
| |

|
| 糸井 |
あのときは、こういうことで
電話するのってイヤだなぁと思いつつ、
どうしてもかけたい、って思ったんです。
もしかしたら、
この作品、評判わるいかもしれない、
という気持ちがあったんですよ。
「ぼくはいいと思います!」
っていうことを
言っておいたほうがいいなって(笑)。
|
| 宮藤 |
へえー!
|
| 糸井 |
で、じぶんで電話をかけたものの、
この漫画をどうほめていいのか、
わかんないんだよ!
「お、お、オレは、
い、いいと思うんだよねぇ」みたいな。
なにを言ったんでしたっけねぇ?
|
しり
あがり |
いや、あの、
「おもしろいよ」って言っていただいて。
それまでは『弥次喜多』のことは
もう忘れようかなって思ってたから。
|
| 宮藤 |
ええええええええっ??
|
| 糸井 |
わはははははははは!!
|
しり
あがり |
あの、その節は
どうもありがとうございました。
今日この場を借りてあらためて‥‥
(ごにょごにょごにょごにょ)。
|
| |
(つづきます)
|