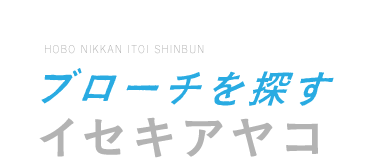 |
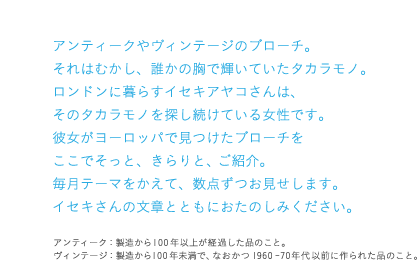 |
|
 |
||

私が育った京都の家の向かいには、 彼の両親は、近所でも仲のいい夫婦で知られていた。 夏休みになると、男の子はきまって家族で 中学生になると、私たちはもう一緒に遊ぶことはなくなったが 湯気を立ちのぼらせながら、おじさんは制服姿の私に気づくと おじさんが不慮の事故で亡くなったと 突然すぎて、その出来事が現実味を帯びて 数ヶ月後、私は実家に帰省した折に、お焼香をあげに行った。 おばさんはお盆にお茶を乗せて持ってくると、そばに座って言った。 私はうつむいた。 「うちの留守番電話にな、 夫を亡くした経験のない私が何と答えても、 遺影の中のおじさんは、いつもとおなじ、優しい笑顔だった。 **************************************************************************** イギリスには、黒いジュエリーが大量に作られた時代がある。 政略結婚だったとはいえ 女王が、いつ公の場に現れても喪に服した恰好でいる様は 私は、こうしたアンティーク・ジュエリーを見るたびに考える。 日本で育った私がイギリスの古いジュエリーの由来に (つづきます) |
2014-02-24-MON

