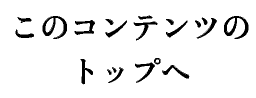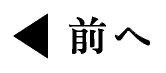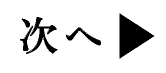「ブリティッシュカレー」という言葉はほとんどの人にとって耳慣れないものだと思う。それどころか、日本のカレーの直接的なルーツがイギリスであることすら意外と知られていない事実である。
イギリスからブリティッシュカレーがやってきたのは、明治維新の頃。「散切り頭を叩いてみれば、文明開化の音がする」と表現されている時代だ。ちょんまげ頭から卒業したての日本人は、西洋文化に大きな憧れがあった。ヨーロッパからきたものはなんでも眩しく見えただろう。ブリティッシュカレーがどれほどの輝きを持っていたかは計り知れないが、とにかく、そこにあった。
イギリスから日本へのカレー伝来には大きくふたつのルートがある。「洋食メニューのひとつとして」というものと「海軍メニューのひとつとして」というものだ。どちらのルートであろうと、イギリスで新たに生まれ、一時代、親しまれていたカレーを総称して「British Curry」と呼ぶ。
いったいどんなカレーだったのだろうか。いま、少なくともロンドン市内には昔ながらのブリティッシュカレーを食べさせてくれるレストランは存在しない。僕が2014年に3か月間滞在し、隅々までくまなく探して見つからなかったのだから、きっと姿を消してしまったのだろう。その後、ブリティッシュカレーの残存と思しきカレーをアイルランドで発見したが、その姿は、ひと言で言えば、小学校の給食で食べたようなカレーである。味も似たようなものだった。まずくはないがうまくもない。それが僕の抱いた印象である。
その後、大英図書館に何日もこもって古い文献を調べた結果、19世紀後半に紹介されたレシピがいくつかも見つかり、おかげで当時のカレーの姿をイメージすることができ、試作することもできた。
そんな記録の上でのブリティッシュカレーの中で特にメジャーだったスタイルのひとつが、「サンデーローストの余り肉を使ったカレー」である。イギリスにはサンデーディナーとかサンデーランチローストとか呼ばれる習慣がある。日曜の午後に家族や友人が集まって、大きな肉の塊をオーブンで焼き、それをメインにした食事をゆっくり楽しむのだ。このロースト肉、大量にできあがるため、たいてい残る。月曜以降、その残った肉をあの手この手で料理して消費するのだが、そのうちのひとつとしてカレーというメニューが生まれたようだ。ほかにもイギリスにもともとあるシチューをカレー風味にアレンジしたようなものも見つかった。
これらのブリティッシュカレーの共通点は、「カレー粉を使う」というものだ。カレー粉はご存じの通り、複数種類のスパイスをブレンドしたもので、イギリス人が発明したと言われている。このカレー粉の誕生は、今も日本のカレー文化の根底を支えている革命的な出来事だった。イギリス人がカレー粉を開発した理由は、おそらくひとつ。インド人のように単体のスパイスを自由自在に組み合わせてカレーを作る技術がなかったからだ。きっとカレーを作るのに必要なスパイスの配合は、インド人に教えてもらったに違いない。それをあらかじめ混ぜた状態で置いておけば毎度のように頭をひねらせる必要はないというのは、なんともイギリス人らしい合理的な考え方である。
そもそもインドからイギリスへカレーが伝わったのは、インド植民地時代のことだ。世界史の教科書にも登場し、記憶のすみっこにある東インド会社なるものは、主にアジア貿易を目的に設立されたイギリスの勅許会社。17世紀から19世紀半ばにかけてアジア各地の植民地経営や交易に従事した。この時代にインド料理という食文化はイギリスに伝わり、徐々に親しまれるようになった。その後、1877年、ヴィクトリアを皇帝として推戴するイギリス領インド帝国が成立する。ここから加速度的にインド人がイギリスに流入し、インド料理も伝播するようになった。そんな状況下、インド料理からブリティッシュカレーが生まれたのである。
カレー粉最大の貢献は、複雑怪奇なインド料理のエッセンスをイギリス人でも再現できるようにしたことにある。このことによって多種多様な味わいを持つインドの食文化が、イギリス国内でブリティッシュカレーという画一的なメニューにすり替わってしまったことはやむを得ないことだろう。
象徴的なメニューの登場によって注目や人気を集め、シンプルなレシピで多くの人が再現、体験できるようになると瞬く間に広まっていく。このステップは、珍しくない。たとえば、かつて日本のイタリア料理黎明期において、さまざまなスタイルや味わいを持つパスタという食文化をもとにナポリタンという独自のメニューが生まれて一世を風靡したのに近い。
“インド料理のような”カレーをひとふりで生み出すことを可能としたカレー粉。便利な道具を手にしたイギリス人が、じゃあ、おいしいカレーを作ることができたかというとそれは疑わしい。少なくとも資料として残るレシピを見る限りはあまり出来のいいものではないし、実際にロンドン滞在時に試作したブリティッシュカレーは味気ないものだった。料理は、多くの人にとって手軽でおいしいものがいい。
その点、ブリティッシュカレーとは一線を画すカレーが当時のイギリスにはすでに存在していた。それは、アングロインディアンカレー(料理)である。植民地時代、アングロサクソンであるイギリス人とインド人が結婚し、共同生活を送り、混血人種が誕生する例は少なくなかった。結果、イギリス人の口に合うように改良されたインドカレーが発達することになる。それらの多くは、おそらくインド人女性の手によって作られたはずだ。イギリス人が作るカレーとインド人が作るカレーが同時期に存在した。さて、この戦い、結末はどうなっただろう?
軍配は、アングロインディアンカレーに上がることになる。スパイスを使ってカレーを作ることに長けているのはインド人なのだから仕方がない。またブリティッシュカレーが余り物の肉を処理するための料理という、いささか消極的な目的から生まれたのに対して、アングロインディアンカレーは、イギリス人とインド人がひとつ屋根の下で共同の食生活を送るためという積極的な目的から生まれた折衷料理だった。なくてもいいカレーとなくてはならないカレー。そこに大きな差がでるのは必然だったのかもしれない。
勝利をおさめたアングロインディアンカレーの代表格と呼べるのが、“チキンティッカマサラ”というカレーである。このカレーのルーツは、インド料理のチキンバターマサラ(ムルグマッカーニ)にあると僕は考える。日本のインド料理店にあるメニューでいえば、“バターチキンカレー”である。要するにヨーグルトとスパイスでマリネし、タンドールで焼いた鶏肉にトマト、バター、生クリームなどを合わせることによって作られる濃厚なカレーだ。
ちなみに“チキンティッカ”というのはインドでは、骨なしのタンドーリチキンを呼ぶことが多いことからも予想がつく。チキンティッカマサラはイギリス人の国民食だと主張する人も多い。どの街のスーパーを訪れてもチルドコーナーにチキンティッカマサラとライスがパックになった商品を見つけることができる。買ってきてオーブンで焼けばすぐに食べられる。そしてどれもクオリティが高く、おいしい。
イギリスにおけるインド料理の独自の進化は留まるところを知らない。特筆すべきはモダンインディアンレストランの流行だ。ひと言でいえば、高級インド料理。日本ならどんなに高いインド料理店へ行っても食べて飲んで1人5,000~6,000円程度で済むが、ロンドンで主流のモダンインディアンレストランは、夜の客単価が10,000円を軽く超える。そんな店が少なくとも10軒以上はある。インド料理をベースにフレンチのようなテクニックや盛りつけが施され、ワインと共に楽しめるメニューに仕上がっている。内装はおしゃれでわかりやすいインド音楽をBGMに流すような店は少ない。ミシュランガイドで星を獲得しているインド料理店が毎年5軒以上あるのもこのスタイルが受け入れられていることを立証している。
高級路線だけではない、モダンにアレンジされたインド料理をカジュアルに提供するレストランも多い。スタイリッシュでありファッショナブルであり、そしておいしい。インド料理の層の厚さやレベルの高さは、世界的に見ても例がなく、最近では、インド国内のファイブスターホテルのレストランがイギリスの物まねをし始めている状況だ。
イギリスで一時的に盛り上がったブリティッシュカレーは廃れていった。代わりにイギリス人が進化させたのは、独自のインド料理だったのである。その点において日本でのカレーはまるで違う道を歩むことになる。明治維新のころ、イギリスから日本に伝わったブリティッシュカレーは、ジャパニーズカレーへと独自の進化を遂げるからだ。インドカレーを知らない日本人がブリティッシュカレーと向き合った60年は、ジャパニーズカレーという新しい食べ物を確立させるのには十分な時間だった。