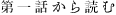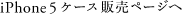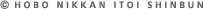「動かないで!」
マリは野太い声で怒鳴った。
周囲をにらむ彼女の視線には、たっぷりと陶酔が混じっている。視界はまるでカメラのファインダー。自分を取り巻く登場人物たちをいちいちとらえていく。
つなぎを着た初老の男、ちょっとすました小綺麗な女、おろおろしてる優男、昏睡している店主。
そして、蒸し暑い喫茶デュラムセモリナ。
「動いたら、だから、いま、動かないで!」
手にした風変わりの銃を右から左へパンする。その銃口が、誰かに向くときのひやりとした感覚ときたら。ひゃあ、とマリは思った。たまらない。
その無邪気さに危険を感じ取ったからこそ、鳥飼は口を開いた。事態が膠着しないうちに仕掛けたほうがいいと思ったからだ。
「あのね、お嬢さん」と鳥飼は紳士的に言った。
「それは、まったく意味がないよ。彼はもう去った。銃を置いていいんだよ。誰もあなたを見張ったりしてないんだ」
しかし、それは逆効果だった。マリは誰かに見張ってほしかったのだ。
「黙りなさい」
今度は低く、仕事のできる女のようにマリは言った。こういうキャラクターもいい、とマリはさらに陶酔を深めた。
ふと思い立って、銃のグリップを下から横にして持ち替えてみる。なんか、映画とかでこうしてるじゃない? こうじゃない? 合ってる、これ?
「動いたら、撃つ。本気なんだわ」
自分の言葉に自分でぞくぞくする。銃のグリップを元の位置に戻す。うん、両手で構えたほうが、それっぽい。
そしてマリの中に、まがまがしい好奇心が生じる。それは夏の夕方に都市部を襲う突発的な雨雲のようにもくもくと広がり、光を遮る。マリはこう思った。
──撃ってみよっかな。
そう思っただけで、耳の奥に血が集まるようだった。撃ったら、どうなるだろう。この、人差し指をぐいと押すだけで、すごいことが起こる。きっとすごい音がして、すごい衝撃で、両手がすごくびりびりしちゃうだろう。それはきっと、ふつうの人が一生経験しないようなすごいことだ。
耳の奥に集まった血が頭のてっぺんに向けて一気に駆け上がる。鼓動を目の裏側あたりに感じる。ひたひたと流れる汗が心地よい。
──撃ってみよっかな。どんなかな。
マリの瞳が不自然に大きくなり、口もとにうっすらと笑みが浮かぶ。
まずい、と鳥飼は感じた。由希子も、自分が安全な状況にないことを感じ取る。
なにしろ、彼女の行為に根拠がなさすぎる。起こっている出来事は、不条理で、無差別だ。しかも、具体的な被害をもたらす可能性が大きい。
ふと由希子は視線を感じた。
向かいの席から、謙一が自分を見ている。まっすぐに、真剣に。
謙一は口を開いた。どういうわけか、はじめて聞くような声だった。
「由希子、謝っておかなきゃいけないことがある」
謙一がなにを言っているのか、由希子にははじめわからなかった。
「キミが言うように、こないだの連休のとき、ぼくは仕事なんかじゃなかったんだ」
由希子は、その意味を考える。
「そう、あの日、ぼくはメグミと会っていた。憶えてないかな、デザイナーの、コウタの二次会で会った子。黄色いヒヨコのiPhoneケースをつけてて、由希子がそれどこで買ったの、とか言ってた、髪の長い子」
ああ、そういうことがあったような気がする。由希子は、謙一が何について話しているのか、ようやく理解しはじめた。こめかみがカッと熱くなる。
「こないだの連休、ぼくはメグミといっしょにいた。ずっと一緒にいた。たしかに、キミの言うとおりだ。ぼくはウソをついてた」
そうだ、もともと私たちは、この喫茶店でその話をしていたんだ。その話がこじれたとき、次々に人が入ってきたんだった。
「ごめん。でも、信じてほしい。ぼくは、キミと離れたくないんだ」
謙一は由希子を見つめた。
「たぶん、ぼくは、いろんな信用を失ったと思う。メグミとのことをごまかそうとしたし、あと、その、お金を持ってるのを言い出さなかったし、それから、肝心のところで勇気が出ないっていうか、すぐびっくりしちゃうっていうか……」
そこで謙一は少し黙り、由希子に顔を近づけて言った。
「でも、ぼくは変わるよ。いまから、それを証明してみせる」
そう言って謙一は立ち上がる。そして、歩き出す。まるでスポットライトが当たってるかのようなその場所へ。謙一は立ち止まり、軽く手を広げた。
そして、マリに向かってこう言った。
「銃を、置いて」
マリはきっと唇を噛みしめ、握る両手に力をこめた。銃口を、そこへ向ける。
「来ないで!」
しかし、マリの内面はとろけそうだった。ああ、狙うべきものが定まった。向こうからやって来た。いいわ。そこへ撃つしかないんだ。だって、どうしようもないんだもの、これ。
「撃つぁわよ!」
マリの声がひっくり返る。押し寄せてくるすさまじい恐怖を受け止めながら、謙一がもう一度言う。
「銃を、置いて」
「うるさい!」
マリが野太い声で叫ぶ。謙一は言う。
「撃ってどうするんだ? 意味がないだろう?」
「意味がないわけなんてないじゃない!」
むしろそれはマリの動機に火をつけた。
「ほんとに撃つわよ、ほんとにほんとだから!」
鳥飼がその銃口をにらむ。撃ったとき、そこからどんな音がするのだろう?
謙一は銃を持つマリに向かって言う。
「いいから、それを渡すんだ」
しかし、銃口はそれない。
「来ないで!」
マリが人差し指に力を込める。
「撃つわ!」
「撃ってみろ」
謙一の顔つきが変わる。
「来ないでって!」
しかし謙一はさらに一歩近づく。
「来ないで! 来ないで!」
「撃ってみろ、撃ってみろ」
「い、い、い、ひゅ、ひゅ、ひゅぁぁあ」
マリの喉の奥から甲高い奇妙な音がした。思わず由希子が両耳をふさぐ。
そして、謙一の中に張り詰めていたものが消滅した。彼は絶望の黒い淵に立っていた。否、足もとに地面はない。すでに、出来事は起こっている。
戻れない、という不安と恐怖が黒い固まりとなって、謙一の尾てい骨のあたりをすっぽりと包んだ。
謙一は感じた。それが、やってくる。自分をめがけて。
「ぁあっ!」
マリが叫んで目をつぶる。筋肉が収縮し、指先が強い負荷を感じる。人差し指は曲がる。すごい速さで。
やめて、と謙一は叫びたかった。しかしそれは間に合わなかった。
──銃声。
乾いた破裂音が古い喫茶店の蒸し暑い空気をつんざく。
気持ちよさそうに寝ていた今村が、びくっと体を震わせる。鳥飼が目を見張り、由希子が何か叫ぶ。
銃からパッと火花が散る。ケミカルなにおいが充満する。
マリの両腕に衝撃が走る。反動で華奢な体が後ろへ飛ばされる。数歩、よろける。
反射的に額をおさえた謙一は、その体勢のまま、崩れ落ちた。腰が落ちる。背中が汚れる。
マリは立ち尽くす。全身から力が抜けてしまった。頬に一筋、涙が流れる。ぼやける視界の中に、男が倒れている。
そしてその男が、ゆっくりと起き上がる。両手をゆっくりと額から離し、信じられない、という風に両方の手のひらを見つめている。
撃たれてない、と謙一は感じた。
「……だから、だから言ったじゃないか!」
鳥飼は汗びっしょりになりながら言った。
「音を聴けばわかるんですよ。ほら、空砲だって言ったじゃないですか!」
マリがその場に座り込む。
謙一は椅子の背につかまりながらゆっくりと立ち上がり、自分の無傷を何度も確かめる。額も、胸も、腹も、首も、大丈夫だ。なんともない。近距離で大きな音を聞いたせいで、耳だけがキーンとしびれたようになっている。
よろよろと謙一は歩み、自分の席に戻る。震える手で椅子の背をつかみ、そこへ腰を下ろす。目の前に、由希子がいる。
「……やったよ、オレ」
謙一は声を振り絞る。
「だから、もう一度、やり直そう」
喫茶デュラムセモリナに、謙一の声が響く。
「……許してくれ、由希子」
そう言って謙一は精一杯、微笑んだ。由希子もシンクロするように微笑んだが、いわばそれはカモフラージュのようなもので、真実の動きは右腕の移動にあった。由希子の動きは謙一の視界の片隅に入ってはいたが、なにしろ彼は大仕事を追えた後で全体の活性が下がりきっていた。
由希子の右腕はその場所へ到達する。謙一は反応できない。
白くて細い指先が机の上のコップをつかみ、腕はそのまま前方へと勢いよく繰り出されながら、手首をくるりと返した。コップにはなみなみと水が注がれている。
謙一の顔に正面からコップの水がぶちまけられる。一直線に、ものの見事に、水は顔面で跳ねて、肩や首筋に流れた。
謙一は、ずぶ濡れである。
由希子は空っぽになったコップを静かに机に置く。
そして由希子は謙一に言う。
「それとこれとは、話が別」
(THE END)
|