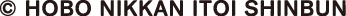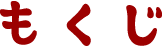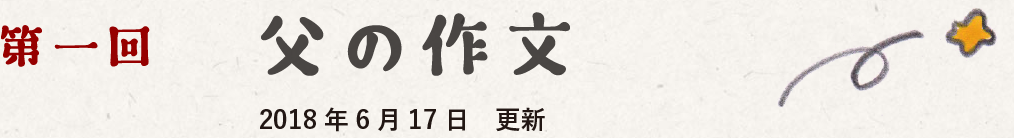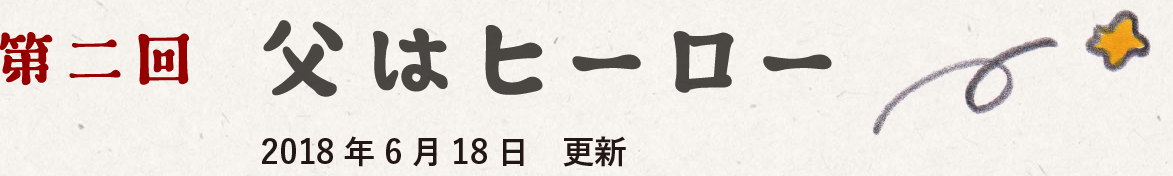中前結花
ほぼ日の塾◉第4期生
イラスト◉ちえ ちひろ
日ごろ、誰かの暮らしや仕事、
時には人生の話をうかがいながら、
記事にまとめるような仕事をしています。
そんなわたしが、「ほぼ日の塾」ではじめて
自分について語る記事に取り組んでみました。
これを「エッセイ」と言うのでしょうか。
わたしにとって、なんともおもしろい体験でした。
それから数ヵ月後、塾の集まりのときに、
「中前さん、なにか書いてみたら?」と、
うれしいお誘いをいただきました。
「なにか」と聞いて思い浮かべたのは、
いちばん近くて、いちばん遠い、父のこと。
父のことをお伝えしたところ、
「せっかくですから父の日に掲載しましょうか」と。
みなさんにも、みなさんのお父さんのことを
ふっと思い出してもらえたらなあ、
とそんな思いで、書いてみます。
父の部屋の隣は、
住人が集まる「集会室」になっていて、
そこに居たご婦人に、
「お世話になっています」とわたしは頭を下げた。
父は「東京におる娘です」と紹介しながら
メガネの端をポリポリと掻く。
いつもの癖だ。
「まあ!」とご婦人は上品な笑顔を見せて、
「お世話になってるのは、こちらなんですよ」と
丁寧に腰を折って挨拶を返してくれた。
「本当に本当にお世話になっていて」
と続けてくれるものだから恐縮してしまうが、
父は「ははは」と、歓迎するような顔をしていた。
なんでもご婦人は、
以前2年ほど家族の看病で家を空けていたことがあり、
ひとり自宅に残された70代のご主人のことが、
心配でたまらなかったのだという。
「背中まで流していただいて‥‥」
と話したところで、父とご婦人は大笑い。
聞けば、父はいつも心細そうにしている
ご主人を誘って銭湯に出かけ、
話を聞きながら、背中まで流していたのだそうだ。
今は、ご夫婦の暮らしに戻っている。

「最近は、話を聞いてもらってばっかりですけれど。
毎日のように、管理人室の前で愚痴を聞いてくださるから。
ついつい喋り過ぎてしまって」
と恥ずかしそうにする笑顔がまた上品だった。
「でも、ここに住んでるみなさん、そうじゃないかしら。
みんな管理人室の前でお話聞いてもらえるのを
たのしみにしてるんちゃいますか」
人の話を黙って聞くところなど想像できない父が、
人々の相談や不満ごとを、一手に引き受け
「うん、うん」と頷きながら、
ときには解決策を講じるのだという。
まさか、と父の顔を覗くと
「ははは」とメガネの端を掻いている。

それからも、道すがら
「父がお世話になっています」と挨拶すると、
「こちらこそお世話に‥‥」
とたくさんの話を聞かせてもらった。
「故障だ」と困っているひとがあれば、
掃除機の修理までこなすこと。
車椅子で暮らす方のゴミはいつも父が運ぶこと。
ひとりで具合の悪いひとがあれば、
翌日決まって部屋まで訪ねること。
お年寄りも増えていく中で、
不安なひとがあれば、
父は病院の検査の日まで覚えているという。
救急車の手配や対応はお手のもので、
事情で急ぎがあれば父の車で病院に駆けつけたことも
一度や二度ではないのだそうだ。
小さな軽自動車は「ドクターカー」と呼ばれていた。
小学生にも、なにやら人気があり
運動会が近づくと、練習の成果を見せようと
管理人室の前で子どもたちがダンスを踊るのだという。
「うまいうまい!」と父の拍手が響くそうだ。

春には、面倒を見ている花壇にめいいっぱい花が咲くこと。
冬には、マンションの外観に電飾を取り付け、
サンタのぬいぐるみが屋根を登る演出まで用意したこと。
「帰ってくると、ほっとする」
と、その出来がみなの間で好評であったこと。
雨の日には、そのサンタに
そっと傘を持たせてやっていたという。
機械音痴なひとがあれば、
ラジオのチャンネルを合わせてあげること。
旅行に出かけているひとがあれば、
「代わりに」と草木に水をあげること。
遠方のご家族から連絡があれば、
行って、様子を見てくること。
まるで「そういう者にわたしはなりたい」と
続けてしまいそうな逸話の数々に、
やっとの思いで「そうですか‥‥」と相槌を打つ。
それが精一杯だった。

他人には関心を持たぬひとだと思っていた。
なにしろ、わたしの就職先も
いまいちピンと来ぬまま東京に送り出した父だ。
自分の目で見たわけではないから、
にわかには信じがたい気持ちでいっぱいだったが、
あれほどに人の好さそうな人々が
みな口をそろえて言うのだから、疑いようもない。
アイアン製のスーツで派手に敵と戦うことはなくとも、
パン工場の車でパトロールし、
みなにパンを分け与えるような、
頭の中でそんな庶民派ヒーローとイメージを被らせた。
マンションの平和を願い、あらゆることを買って出る
「マンションのヒーロー」に父は変身していたのだ。

わたしの知らない父。
突然の出会いに動揺しながら、
離れて暮らしていた父の数年間を思ってみるが、
なかなかうまくはいかなかった。
しかし、このあと
わたしの「腑に落ちない」思いは、
見事に吹き飛ぶことになる。
その夜わたしは、
父の手配する救急車で病院に担ぎ込まれてしまうのだった。
2018-06-18-MON