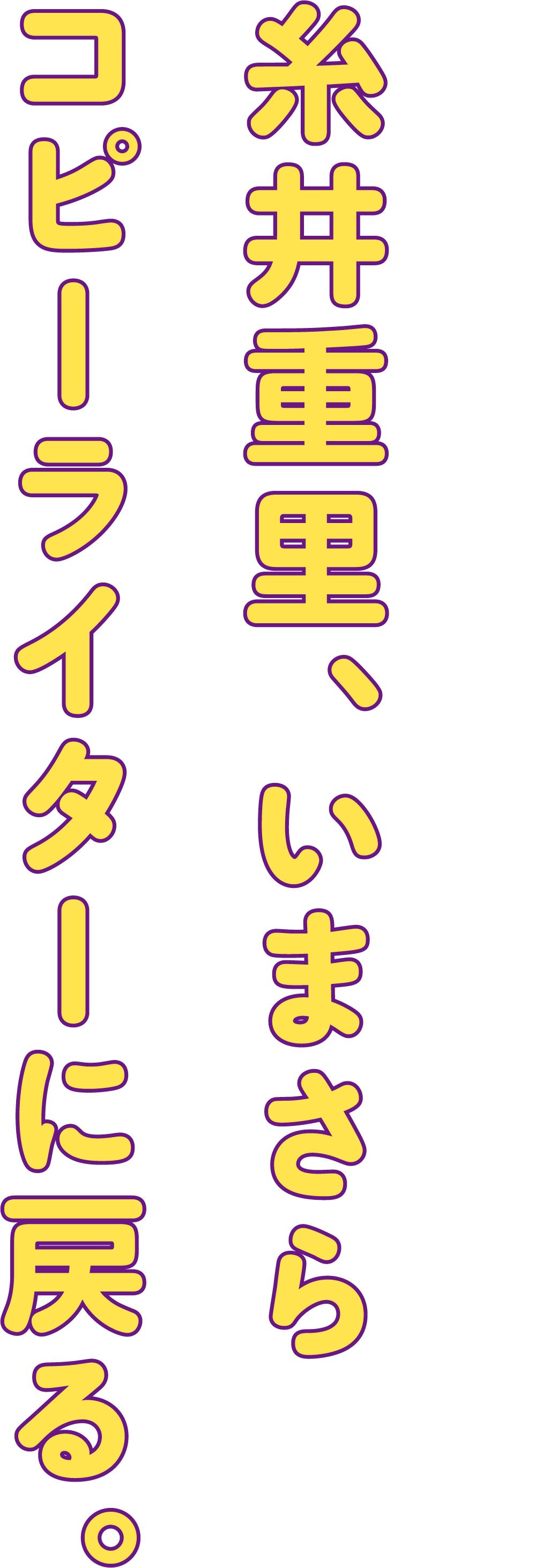
糸井重里は「ほぼ日」をはじめてから、
コピーの手法や技術についての話を
積極的に伝えようとはしてきませんでした。
でもやっぱり、一時代を築き上げた
広告コピーの話はじっくり聞いてみたい!
そんな機会をずっとうかがっていたら、
「前橋BOOK FES」の新聞広告で
糸井さんがひさしぶりにコピーを書くことに。
ほぼ日の編集者であるぼく(平野)は、
コピーライター出身なので興味津々です。
新聞広告を振り返りながら教わりました。
糸井さん、あのコピーってどう書いたんですか?
- ――
- 新潮社の「想像力と数百円」の頃から、
糸井さんは本との縁がありましたよね。
- 糸井
- ぼくは昔から「本好き集まれ」とは言わないけど、
本について考えていたことが
昔あったのはよかったですね。
- ――
- 1987年のコピー年鑑のコメントで、
「死ぬまで肩書は
コピーライターであり続けるつもりです」
とおっしゃっていたようです。
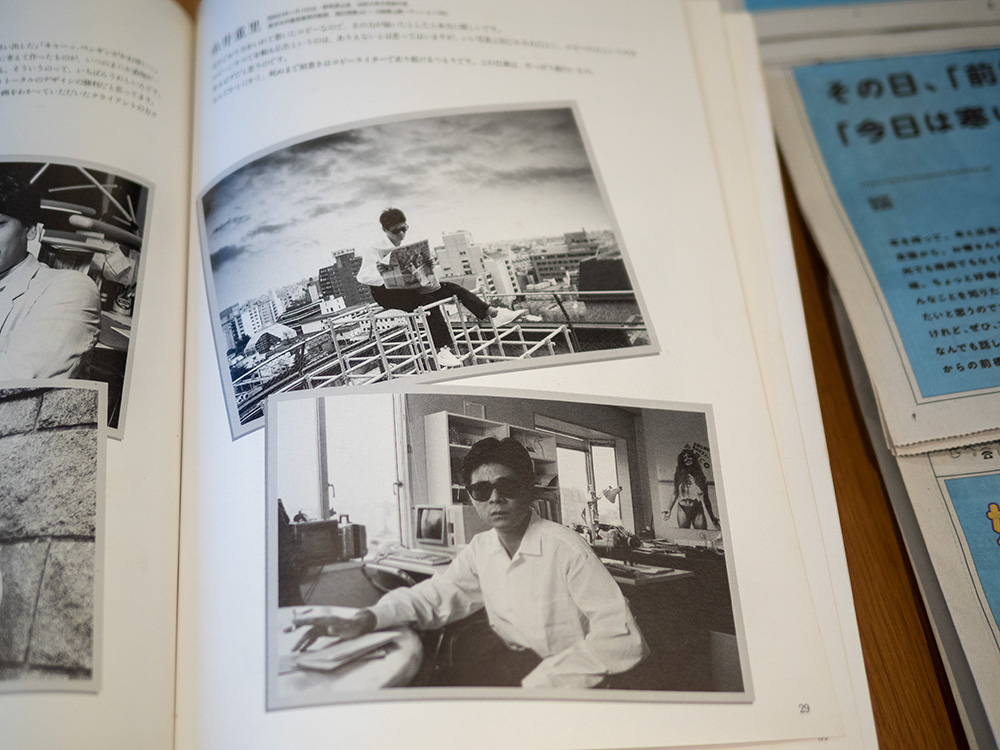
- 糸井
- ああ、結局そうされちゃってますよね(笑)。
ぼくは昔からコピー年鑑に載せるために
上手なコピーを書こうなんて意識はことさらなくて、
いい広告で、いいビジョンを
いっしょにつくりたかったんです。
岡本太郎が「太陽の塔」をつくって、
それと比べるようなことじゃないけれど、
ああいうふうに、
なんでもない人に見上げてもらいたかったんです。
岡本太郎は売るための絵じゃなくて、
壁画とかそういうのばっかりやっていた人だったから。
前橋には「太陽の鐘」を持ってきたけれど、
地元の人に「鐘を突いてみせます」みたいな気分を
この広告には入れられたんじゃないかな。
- ――
- この広告、もしぼくが任されていたとしたら、
それこそ1回目や2回目にあったような
「この情報は入れてくださいね」という要素を
入れなくちゃなあと考えてしまいそうなんです。
特に、イベントが近づくにつれて、
「こういうゲストが来ますよ」とか、
「参加の仕方をもっとわかりやすく」とか。
そこをかなり省いていたのも、
やはり意図されていたわけですよね。
- 糸井
- ああ、それはやっぱり
ぼくがクリエイティブディレクターだったから。
この仕事を下請けでやっていたら、
そういう要素も入ると思うんです。
強みだから出そうって話はよくありますよね。
いわゆる強みだとか得だとかに合わせて
人が動くものだって思うよりは、
せっかく本の話なんだし、
読んでうなずいてくれる人と会いたかったんです。
広告を読んだ全員がわかってくれなくてもいいの。 - たとえば、このシリーズ全体のデザインも、
文字のフォントは同じだけど、
袋文字にしたり黄色も黒もあったりして、
じつはデザインがバラバラなんですよ。
その全体像を最初から計画していたら、
そのバラバラさは許せないはずなんです。
ただ、それはデザイナーが自分でやったことで、
その統一感みたいなものよりも
大事なことがあるって考えたからなんですよね。
- ――
- ちなみにこの広告のシリーズって、
群馬県民の方々が読んでいたときに、
糸井さんが書いたってわかっていたんですかね。
- 糸井
- いや、それはわかってないんじゃないかな。
- 上毛新聞
- 我々も正直、知りませんでした。
おそらく、県民も知らなかったと思います。
- 糸井
- そこに「糸井重里」はいらないと思ったんです。
ぼくの名前を出しちゃうやり方も、
発想としてはあるんですよ。
- ――
- 糸井さんはこのイベントの発起人でもあるから、
「エグゼクティブプロデューサーの
糸井重里さんにインタビューしました」
という広告でもよかったわけですもんね。
- 糸井
- うん、それもできますね。
でも今回の広告では、
コピーライターに戻りたかったんですよ。
ぼくがマイクを持って言っているんじゃなくて、
町から湧いてきたようなことばにしたかったから。
ただ、プレッシャーはありましたね。
ぼくはもう長いこと、
「コピーライターはもうしないよ」と言っていたのに、
「これは、おれがやる」と言ったからには、
隠れるわけにいかないじゃないですか。
いま、糸井がコピーライターをやるとしたら
こういうことやるんだよって考えて、
後になっても恥ずかしくないものをつくりたくて。

- ーー
- 糸井さんにとって
地元だったことの影響はいかがですか。
- 糸井
- やっぱり地元だったのは大きいですよ。
イベントの最後の挨拶で「初めて甘えました」っていう
言い方をして泣けてきちゃったんだけど、
それまで地元とか、土地の人に対して
甘えてこなかったんですよ。
「おまえはおまえ、おれはおれ」
みたいなところがあったんだけど、
このイベントは本当に信じきらないとできなかった。 - その意味で「来年もやってくれるよね」というのは、
言ってみれば甘えなんですよね。
でも、そう言える関係って、
他の町でだったら言えないんじゃないかな。
「甘え」という表現をしたけれど、
信じる・信じないの部分なんです。
フェス全体にも言える話なんですが、
自分を変えるようなイベントでしたね。
ボランティアに応募してくれた人があれだけいて、
地元の人たちの意見もだいぶ聞けたけれど、
「本当に奇跡だ」って言ってくれました。
- ――
- そうですね。
- 糸井
- ぼくも奇跡だと思いますね。
お天気がよかったのもそうだし、
率先してこのフェスを盛り上げようとしてくれた
人たちの態度がモデルになって、
地元の人やお客さんとして来たみんなに
うつっていったんじゃないでしょうか。
お金で雇われたんじゃなくて、
自前のお金でボランティアしに来てくれた人が
あれだけいたっていうのは奇跡ですよね。
- ――
- ほぼ日のボランティアさんだけで
延べ90人でしたからね。
- 糸井
- ありがたい話ですよねえ。
フェスのやり方としては、
「そんなに人が集まるんだろうか」なんて
言っていたらできないですよね。
そこを信じられなかったらできませんでした。
- ――
- しかもボランティアのみなさん、
お客さんとしてもちゃんと参加していましたし。
- 糸井
- そうだよね。
商店街の人が言っていたことですけど、
こういう賑わいがあったとしても、
商店街にはお金を使わないのが多いそうなんです。
でも、ブックフェスではみんなが寄ってくれたみたい。
そういえば、ぼくもおもちゃ屋さんに寄ったなあ。
- ――
- あの商店街の中で
エコバッグがめちゃくちゃ売れたみたいですよ。
ヨシタケさんのイラストの
オリジナルバッグも売っていましたが、
あれもすぐに売り切れちゃったので。
- 糸井
- なるほど、本を持ち帰るからだね。
来年があるなら、もっと作るでしょうね(笑)。
ここに来なければ手に入れられない
たのしいものを用意しておけば、
買いたい人はいっぱいいると思うんですよね。
うーん、やっぱり「来年はどうですか?」が
いちばんの悩みかなあ。
- ――
- あの、糸井さん。
これを聞いていいものか迷いつつ、
ブックフェスは来年もあるんですか。
- 糸井
- うーーーっん、
ぼくと田中仁さんの気持ち次第かなあ。
- 一同
- (笑)
- 糸井
- そこはまあいろいろあって、
一種の経営判断ですからね(笑)。
ただ、次にやるとしたら、
宿泊のあたりが課題になるんじゃないかな。
そこは前橋の人が一所懸命に考えたらできますよ。
本からはじまって、カルチャー全体に及ぶような
人と人との貿易ができるといいなあ思うんです。
次回をやりたい理由は、ぼくの中にはあります。
ただやっぱり、本当に地元の人のことを
信じきらないとできないんですけどね。
- ――
- また今度は、前橋のみなさんが
ちょっと試されているんですかね(笑)。
- 糸井
- 上毛新聞は十分に応えてくれましたから(笑)。
やれることは、まだいっぱいありますよね。
途中途中でプロセスを伝えていくと
地元のみんなも勇気が出ますから、
その意味で1年間いいネタができたと思って、
「来年だったら、もっとこうしようよ」
という特集もできるし、おもしろいと思いますよ。
- ――
- 次回があるかまだわかりませんが、
またたのしみになってきますね。
糸井さん、上毛新聞のみなさん、
どうもありがとうございました。

(おわります)
2023-02-27-MON
