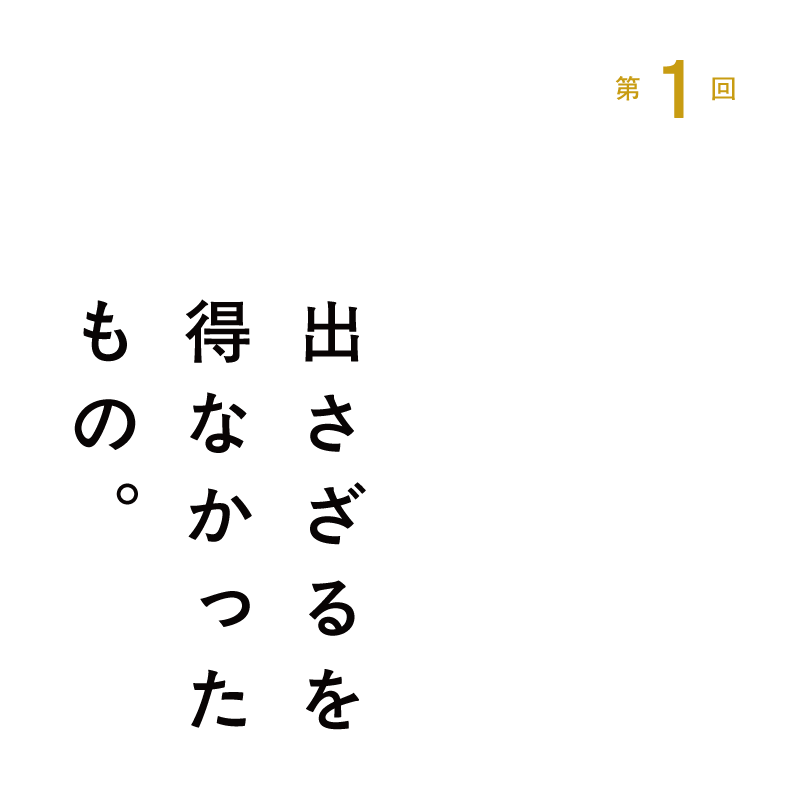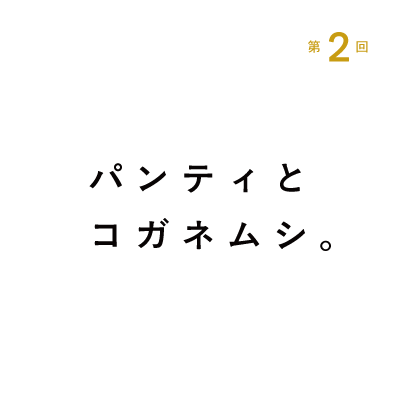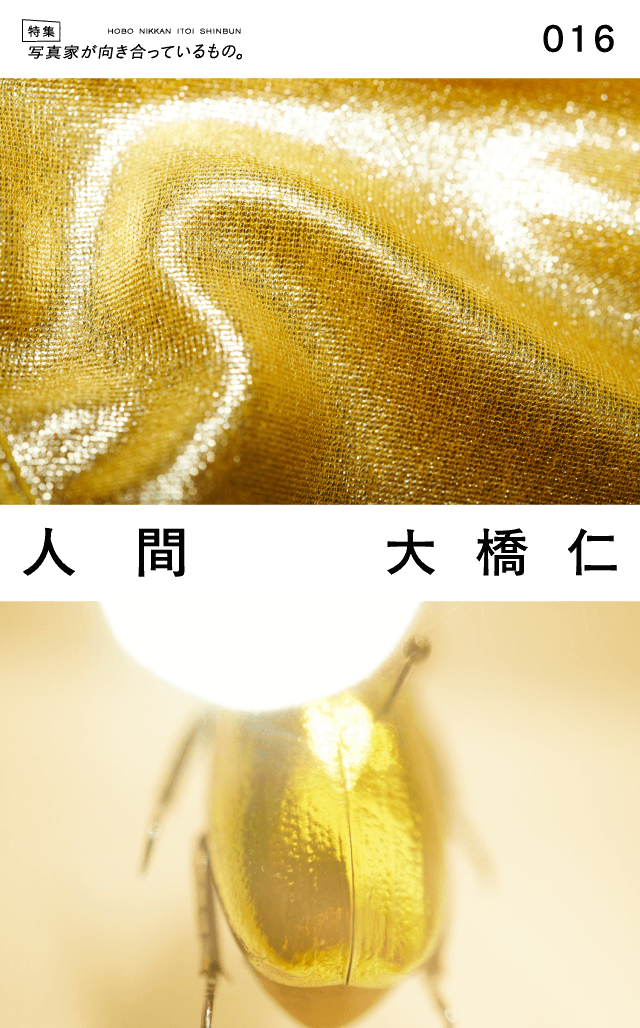
この写真家にインタビューできなければ、
この現代写真家インタビュー連載には、
決定的な「欠け」があると思っていました。
なのに、長らくできなかったのは、
その作風のせいか、
勝手に「怖い人」というか、厳しい人、
激しい人じゃないかと思っていたからです。
実際の大橋さんは、
自分の欲求に対して真摯で真面目で、
人間や生命の不思議や謎を探り続けている
少年探検家のようでした。
センセーショナルな写真集で
世間を賑わせている側面ばかり見ていては、
「大橋さんの写真」のことを、
理解しきれないままだったろうと思います。
全7回、担当はほぼ日の奥野です。
- ──
- 自分は素人ながら写真が好きなんです。
- 大橋
- 本当ですか。うれしい。
- ──
- これまで気になっている写真家さんに、
折に触れてインタビューしてきました。 - 写真家のみなさんって、
「写真」と「カメラ」は共通ですけど、
話す内容の種類とか次元が、
まったくもって、人それぞれじゃないですか。
同じ職業だと思えないほど。
そのことがおもしろくて、続けてます。
- 大橋
- なるほど。
- ──
- 大橋さんの写真集も拝見していました。
- で、最新の第4作目を見たときに、
「ああ、大橋さんは、一貫して
ひとつのものを追いかけてきたんだな」
と感じたんです。
その目で、もういちどあらためて、
過去の作品‥‥とくに3作目についても
「ただセンセーショナルな写真集、
というわけではなかったんだ」
ということに、わーっと気づいたんです。
- 大橋
- あ、本当ですか。うれしいです。
- ──
- 1作目の『目のまえのつづき』では
自殺を試みたお父さんの「血」、
2作目の『いま』では10名の妊婦の「出産」、
3作目の『そこにすわろうとおもう』では、
何百人もの男女を一箇所に集めて撮った、
生命のきっかけとしての「性行為」ですね。 - 今回の4作目の『はじめて あった』では、
ご自身の「性癖」と「昆虫」と‥‥。

- 大橋
- はい。
- ──
- そうか、大橋さんは、
ずっと「生命」とか「人間」の不思議、
みたいなものに向き合ってきたのか、
ということに気づいたんです。 - そういう意識って、ご自身でも、
一貫してお持ちだったんでしょうか?
- 大橋
- 何ていうのかな、いままでの作品も、
今回の作品も、自分としては
特別なことをやってる感覚はないんです。
日常の自分の中から
ふわーっと浮かび上がってくるイメージがあって、
そういうものに
こっちから寄っていくみたいな感覚で撮って、
構成してるだけなんです。
- ──
- なるほど。
- 大橋
- コンセプトやテーマというものが
事前に存在しているわけではなく、
意識して
生命に向き合ってきたと言うことでもなく、
ただ自然に
自分にとっての日常を生きる中で
起こった出来事であったり、
自分の生命が感覚的に感じたことに対して
素直に反応して撮影していたら、
いつの間にか
生命に向き合あわざるをえなくなっていた。 - だから、写真集をつくっても
「出したぞ!」とか「見てくれ!」
みたいな高揚感も、そんなにはないんです。
刷り上がった本を前に、どこか
いつもの自分の顔を鏡で見ているみたいな、
「ああ、これこれ」って感じなんです。
- ──
- その感覚って、なかでも物議を醸した、
3作目の
『そこにすわろうとおもう』でも‥‥。
- 大橋
- 同じですね、ずっと。
- ただ、ぼくの場合は、どうしても
「自分をさらしてしまう」傾向があって
個人的には「こんなものを見せていいのか?」
みたいな気持ちは毎回あるんですが、
その一方で、作品としては
己の暴露は必要だという考えも同時にある。
そしていつでも、
「作品が優先される」という状況なんです。
- ──
- 自分でもヤバいかも、みたいに感じていながら、
出さざるを得ない。
それって1作目から、ですか?
- 大橋
- はい、そうですね。
本心から思ったことや感じたことなどを、
できるだけそのまま、
正直に出そうとしているだけなんですが、
まるで
世間に向けて裸でチ◯ポ出しちゃってる、
みたいな感覚にもなって、
「いいのかなあ?」って思うんですよね。
- ──
- たしかに「むき出し感」はありますね。
大橋さんの作品には。 - 具体的な何かっていうより雰囲気的に。
- 大橋
- あることについて、俺はどう思うんだ、
とかって考えはじめちゃうと、
そこから、逃れられなくなるんです。 - いちど写真に撮ってかたちにしないと、
次に行けなくなっちゃうんです。
 大橋仁『はじめて あった』より
大橋仁『はじめて あった』より
- ──
- 写真で思考してるというか?
撮ることで「解決」してる?
- 大橋
- んー、どうなんですかね。
自分は女性ではないので
こういうたとえでいいのかわかりませんが、
「出産」に近いのかもしれない。 - 時間をかけて自分の中で育っていく‥‥
子どもというか、もう一人の自分というか。
でも、いちど宿ったイメージを
かたちにして出さなければ、
次には、どうしても行けない。
ぼくが「出す」のは、
この先も生きていくために必要なこと。
自分にとっては、
「出すこと」が自然で必然なんですよ。
- ──
- これまで、ずっと「撮る」じゃなくて、
「出す」と表現しているのが、
たぶん、大橋さんらしいんでしょうね。
- 大橋
- そういう感覚なんです。
- ただ、3作目までは、
自分が目にした光景や思ったこととかを
そのまま出してきたんだけど、
今回の4作目に関しては、
もっと自分の奥に潜ってる感じがあって。
- ──
- 潜る。
- 大橋
- 意識の底の、無意識の領域というか、
自分の頭の奥のほうへ、入っていった感覚。
3作目までがフィジカルっぽいとしたら、
4作目は
脳細胞やメンタルやDNA、
生命の記憶の領域へ足を踏み入れてる感じ。
- ──
- いったん「出したい」と思ったら、
出さざるを得なくなっちゃう‥‥のって、
写真家としての衝動、
みたいなものなんですかね。性というか。
- 大橋
- たぶん、その「衝動」がなくなっちゃうと、
写真家としてはヤバいでしょうね。
自分は「創造行為」だとか、
「何かを表現している」みたいな感覚って、
ほとんどないんですけど。
- ──
- 写真とは「自分が現れる」ことであり、
写真を撮らせるのは「衝動」であり‥‥。
- 大橋
- あとはやっぱり、鏡で自分の顔を見て、
「あー、こんな感じか」みたいな感覚。
- ──
- 「これが、いまの俺か」という確認?
- 大橋
- そうかもしれないですね。
その本を出したタイミングの自分が
そのまま写真集になっているといいなと
思っています。 - 「この本が、51歳の俺です」みたいな(笑)。
- ──
- 写真が「大橋さん自身」だとしたら‥‥。
- とりわけ3冊目の写真集は、
いろんな取り上げ方をされていましたよね。
- 大橋
- ぼくは、ぼくの作品にたいして、
何か言ってもらえるのがうれしいんです。 - 言ってもらえるなら、批判でもいい。
「おまえ、ウ◯コ!」でも何でも(笑)。
その意味では、
今回の『はじめて あった』に関しては、
すごく「反応がない」んですよ。
 大橋仁『はじめて あった』より
大橋仁『はじめて あった』より
- ──
- そうなんですか。
- 大橋
- あまりにも、3作目の
『そこにすわろうとおもう』との落差が
激しすぎちゃったのか、
地味な作品として受け取られているのか、
今回は、さざ波も立ってない感じです。 - 3作目は、あんなに大炎上したのに。
飽きられたのか、忘れられたのか、
時代が変わったのか、あの嵐は何だったんだ?
性癖丸出しの今作のほうが
よっぽど炎上向きなのになぜ炎上しない‥‥
みたいな。
- ──
- 実際、『そこにすわろうとおもう』って、
世の中のご意見としては、
やっぱり批判なものが多かったんですか。
- 大橋
- いや、それがじつは、批判というよりも、
好意的な反応のほうが多かったんですよ。 - 中身を大々的には見せられなかったので、
自然発生的に広まって、
誰かの感想が感想を呼んでいった感じで。
- ──
- たくさんの人がコメントを寄せてるのを、
当時、いろいろ見ていました。 - 荒木経惟さんの帯の言葉の
「これが現代アートだ!」をはじめ。
- 大橋
- 荒木さんのその言葉は、
当時、写真を現代アートにしてしまった作品群への
強烈な皮肉だったんです。
「現代アートよ、この肉団子写真集を食らえ!」
的な。 - で、今回の4作目はドボーンって投げたんだけど、
まったく波紋が起こらない(笑)。
「俺、水面じゃないところに投げたの?」
みたいな。
- ──
- アスファルトとかコンクリートとか、
硬質な地面にドサッみたいな感じですか。
- 大橋
- それもないです。無音。「しーん」です。
- ──
- そのことについては、どう思ってますか。
- 大橋
- もう、自分でさえ、
状況に沈黙しはじめちゃってますね。
- ──
- ゴッホが何をしたかったのかって、
《ひまわり》を1枚だけ見ただけじゃ、
たぶん、わからないと思うんです。 - だから、大橋さん自身でさえも、
ご自身の「やりたいこと」については、
はじめのうちこそ
曖昧だったかもしれないけど、
いまは確信を持ってるんだろうなって、
4作品を見返したら感じたんです。
- 大橋
- うん、うん。
- ──
- ちょっと前のインタビューで読みましたが、
「生命の痕跡」とか
「人間の在りよう」みたいなものを、
1作ずつ突き詰めてきてるじゃないですか。 - その目で、今回の4作目を見たら、
深い作品だな‥‥と。
何しろ「自分の性癖」をさらしてるわけで。
- 大橋
- ぼくだって、さらしたくなかったですよ!
できれば。自分の性癖なんか。 - はっきり言って。
- ──
- あ、そう‥‥ですよね(笑)。
- 大橋
- でも、ここ数年間に起きたできごとが、
自分的には、
どうしても避けて通ることができない、
すごく大きな出来事だったんです。
- ──
- それらが写ってるわけですね。4冊目には。
- 大橋
- はい。そのなかのひとつが、
「己の性癖に対する気づき」なんです。
- ──
- だから「出さざるを得なかった」、と。
衆目にさらさざるを得なかった。
- 大橋
- そこに、「母の死」も、絡んできたんです。
母の死と、
自分という個的な生命・記憶の循環の輪と、
自分の性癖という
生命そのものの根源的な記憶の循環の輪、
それらが重なって大きな柱になっちゃった。 - 「不思議だなあ」という「性癖」と、
「こういうことだったのか」という「母の死」に、
向き合わざるを得なかったんですよね。
向き合うってことは、
つまり、自分の場合「撮る」ってことなんですが。
で、向き合っちゃったし、
撮っちゃったんで、出さざるを得なかったんです。
- ──
- どっちかっていえば、気が進まなかったけど。
- 大橋
- 自分にとっての「写真」って、
自分が死ぬことで
必然的に完結するんじゃないかなって、
漠然とした感覚があるんです。 - だから、そのときそのときで
自分が思ったことを排除しちゃったら、
自分の生命から逃げるというか、
自分の生命に
嘘をついてしまうことになる気がして。
- ──
- 己の性癖を、出さざるを得なかった。
- 大橋
- いかに自然に、ありのままに‥‥と思うと、
避けては通れない道だったんです。
 大橋仁『はじめて あった』より
大橋仁『はじめて あった』より
(つづきます)
2024-11-07-THU
-
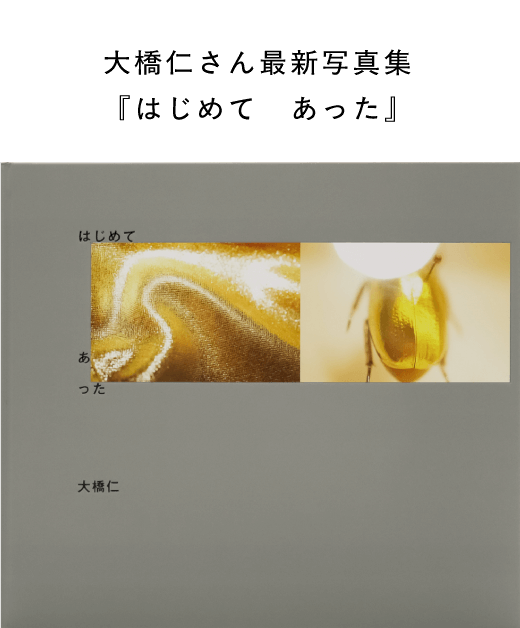
荒木経惟さんをして
「これが現代アートだ」と言わしめた作品
『そこにすわろうとおもう』から10年、
大橋仁さんが
「過去の3作品とくらべて、自分の頭の中、
脳細胞やメンタルやDNA、
生命の記憶の領域へ足を踏み入れてる感じ」
と位置づける第4作。
写っているのは金のパンティとコガネムシ。
(もちろん、それだけではありませんが)
このインタビューを読んで、
もし「大橋仁」という写真家、
というか「人間」に興味を持たれましたら、
ぜひ、手にとってみてください。
みなさんの感想を、聞いてみたいです。
販売サイトは、こちらです。