私がエルサレムを訪ねたのは、
2006年の7月だった。
旅するのにいい時期とは、とても言えない。
その1週間ほど前に、イスラエルがレバノンに侵攻、
国境沿いでミサイルの応酬が激しくなっていた。
つまりイスラエルは戦時下に入っていたのだ。
そんな時期に旅行するアジア人は、
かなり怪しい存在だったに違いない。
テルアビブのベン・グリオン空港でのチェックは、
これまで人生で体験した中で、最も執拗なものだった。
まず飛行機を降りたところで、
名誉なことに銃を持った兵士に呼び止められた。
パスポートチェックを受ける。
「なぜよりによって戦争中の今の時期に、
わざわざエルサレムを旅するのか」という質問を、
手を変え、品を変えて繰り返す。
旅行を計画した時にはまだ戦争は始まっていなかった、
と答えても、いっこうに信じてくれない。
「じゃあ、戦争が始まったのに、
なぜ予定を変更しなかったのか」と訊かれ、
「安いチケットは変更がきかない」という、
私にとっては切実な問題を訴えても、
彼らにとって説得力のある答えとは言い難いようだった。
実際、日本の外務省の渡航情報でも、
テルアビブとエルサレムは、
注意すれば安全に問題はないとのことだった。
30年以上前におきた日本人の乱射事件の記憶が、
彼らにあるのだろうか、と考え始めたとき、
ようやく、長き尋問から解放された。
パスポート・コントロールも同じだった。
質問は永遠に続くかに見えた。
さらにパスポート・コントロールを抜けたところで、
別の兵士が待っていた。
やれやれ。

私がエルサレムに入ったのは、金曜の午後だった。
ユダヤ人にとって、
金曜の日没から土曜の日没までは安息日にあたるからか、
街はすでに静けさに包まれていた。
私は日が暮れるのを待って、
ホテルを出て旧市街地に向かった。
東エルサレムにある旧市街は
1キロ四方の小さな区域で、すべて城壁に覆われている。
その狭い敷地の中に、3つの宗教の聖地が同居している。
ユダヤ教徒の聖地である『嘆きの壁』、
イスラム教の聖地である『岩のドーム』、
キリスト教の聖地である『聖墳墓教会』だ。
城壁にいくつか設けられている入り口のひとつ、
ヤッフォ門から入る。
狭い石畳の道の両脇にはこじんまりした店が
びっしりと並んでいた。
アラビア語で、スークと呼ばれる市場だ。
私の姿を見て、店の主人が
「ニーハオ」と声をかけてくる。
闇が落ちてくる。
アラブ系の少年たちが
私の周りを何か囃したてながら回っている。
目の前を、ユダヤ人の夫婦が歩いている。
山高帽に立派なあご髭をたくわえて、
黒い礼服を着た夫に、
やはり黒いドレスをまとった妻がしたがっている。
彼らも嘆きの壁に行くのだろう。
10分ほど歩くと、検問があった。
セキュリティーチェックを受け、
狭いトンネルのような門をくぐると、
急に広場が開けた。
すでに大勢の人々が広場を埋め尽くし、
あちこちから祈りの声が聞こえてくる。
嘆きの壁が正面に見える。
20メートルほどの高さの壁がライトアップされて、
鮮やかに浮かび上がっていた。
祈っているのは多くが男性で、
女性の祈る場所は右隅に設けられ、
入り口も分けられていた。
壁にそばには礼服を着た男たちが集まり、
頭を壁につけて声を発したり、
背の高い台にヘブライ語の聖書を置いて、
上半身を激しく前後に揺らしたりしている。
円陣をくんで歌っている若者たちもいた。
ひときわ大きな歌声に振り返ると、
大勢の少年たちが肩を組んで歌いながら近づいてくる。
彼らだけではない。
いくつものグループが、
やはり肩を組んで大声を張り上げて、
壁を目指して近づいてくる。
集まったユダヤ教徒は、
ゆうに千人は超えていただろう。
彼らは広場を埋め尽くし、大合唱を始める。
私は言葉を失ってその渦の中に佇んでいた。
ユダヤ人たちは何かにとりつかれたように、
一心不乱に祈り、歌っている。
安息日の夜には毎週これほどの人が集まるのか、
それとも戦争をしている最中だからなのかわからない。
しかしそこには、
熱狂という言葉がふさわしい光景が繰り広げられていた。
ユダヤ人にとって『嘆きの壁』は、
2千年前に土地を追われた恨みと、
祖国復興の象徴でもある。
彼らにしてみれば、2千年間離散し、差別され、
ホロコーストまで経験して、
ようやくイスラエルという国を取り戻したのだ。
国際的なルールにどれだけ背こうとも、
他国からどれだけ非難されようとも、
自分の国を守ろうとするだろう。
そのために中東最強の軍事力、
そして核兵器を持つことも、当然だと思うだろう。
嘆きの壁で繰り広げられる熱狂の前では、
すべての理想論も空虚なものに思えた。
旅で知り合ったひとりのユダヤ人は、私にこう語った。
「イスラエルは中東で唯一の民主主義国家です。
そして文明化されていない野蛮な国に囲まれています。
我々は危険で特殊な環境に置かれているんです。
自分の国は自分で守らなければ、
誰が守ってくれるでしょうか。
帰る国がないつらさを、
2度とわれわれの子孫に経験させるつもりはありません」
彼に、まったく迷いというものは感じられなかった。

アメリカがこれほどイスラエルに加担することは、
果たしてアメリカの国益になるのか。
アメリカ議会の『9・11調査委員会』は、
ハリド・シェイク・モハメド被告の行動のきっかけは、
パレスチナ問題だと記している。
ハリド・シェイク・モハメド被告は、
9・11同時テロの中心的立案者とされている。
「彼自身の説明によれば、
ハリド・シェイク・モハメドの米国に対する敵意は、
米国での学生時代の経験に根ざすものではなかった。
それはイスラエルに好意的な米国の外交政策への
激しい反発から来たものだった」(報告書P147)
「2000年にイスラエルの野党党首だった
シャロン(後の首相)が、エルサレムの
神殿の丘(イスラム教の聖地がある丘)へ
挑発的な訪問(警官1000人を引き連れて行った)を
行ったあと、
ビン・ラディンは攻撃の日時を早めるように促した。
ビン・ラディンは
特定のターゲットにぶつけなくていいから、
飛行機を落とすだけでいいんだと言った」
(報告書P250)
さらに、ビン・ラディン容疑者は
2001年にシャロン首相が
ホワイトハウスを訪問すると知った時にも
やはり攻撃を早めようとしたと、
ハリド・シェイク・モハメド被告は証言している。
つまり9・11同時テロは、
アメリカのイスラエルへの外交政策も
引き金になっていたことを、
報告書は明らかにしているのだ。
最近になってアメリカの学者たちからも、
イスラエルへの過度の支持が
アメリカの国益を損なっている
という論調が出始めている。
シカゴ大学のジョン・J・ミアシャイマー教授と
スティーブン・M・ウォルト教授が記した論文は、
アメリカがどれだけイスラエルに特別な支援を与え、
イスラエルロビーが
いかにアメリカの政策をゆがめてきたかを
膨大な資料をもとに描いたうえで、
「こうしたアメリカの外交政策は、
米国の国益に適ってない。それどころか、
イスラエルの長期的な利益をも損なう」
と結論づけた。
おそらくこれまでで最もこの問題に
深く切り込んだふたりの論文は、
アメリカで掲載を断わられ、
2006年になってイギリスで掲載された。
論文への反響はすさまじく、
著者のふたりはアメリカ国内で
激しい批判にさらされる一方で、
高い評価も勝ち取った。
しかしアメリカ以外の国での評価のほうが、
はるかに好意的だったと著者は語っている。
オバマ政権の外交をつかさどる国務省の長官に
ヒラリー・クリントン氏が就任した。
彼女はニューヨークを地盤にし、
ユダヤ人脈に支えられている。
また国務省のふたりの副長官のうち
政策担当の副長官はユダヤ系アメリカ人だ。
その下の中東和平担当特使に
アラブ系の重鎮を選んだとはいえ
外交を行う国務省のトップ3人のうち2人は
明らかに親イスラエルと言ってもいいだろう。
さらにホワイトハウスを取り仕切り、
大統領に最も近い政策アドバイザーとも言われる
大統領首席補佐官も、
ユダヤ系アメリカ人がそのポストについた。
オバマ大統領は『チェンジ』を合言葉に、
ブッシュ政治との決別を訴えた。
しかし、ことイスラエル政策に限っては
チェンジすることは難しいだろう。
一方で、中東和平に積極的に関与する姿勢を
みせているオバマ大統領は
そのバランスをどうとっていくのか。
そしてもし「変化」がもたらされなければ
アラブ諸国の人々はこう思うに違いない。
「オバマよ、お前もか」、と。
(終わり) |


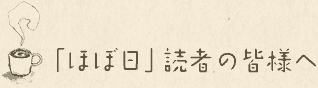
![なぜオバマ大統領もイスラエルに加担するのか [4] なぜオバマ大統領もイスラエルに加担するのか [4]](images_new/vol08_title.jpg)

