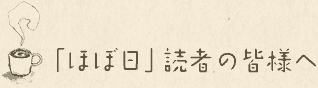人生の終わりが近づいていると感じた時、
あなただったら、
店じまいをする前に何をしたいと考えるだろうか。
ニューヨーク郊外に住むヴィック・ヴォーゲリンさんは
80歳になってある決意をした。
それは108通の手紙を
会ったこともない異国の人に手渡そうというものだった。
ヴォーゲリンさんは、18歳のとき
アメリカ軍の兵士として
日本軍が待ち受ける硫黄島に上陸した。
1945年のことだ。
戦闘は2、3日で終わるとたかをくくっていたが
ことはそう簡単ではなかった。
仲間の米兵が次々と撃たれ
遺体が海に浮かぶ光景を目の当たりにした。
「暗くて大混乱でした。
けが人を次々と運んでいきました。
今も頭から離れません」
激しい戦いのあと
ヴォーゲリンさんは浜辺で
かばんを見つける。
拾い上げて中を見ると
たくさんの葉書や手紙が入っていた。
日本兵のものであることは
すぐにわかったが、
何が書いてあるのかわかるはずもなかった。
ヴォーゲリンさんは軽い気持ちで
そのままアメリカに持ち帰り
トランクに入れて自宅の片隅にしまっておいた。
手紙はヴォーゲリンさんの記憶の
奥の引き出しにしまい込まれたまま
硫黄島の戦いは歴史のひとつになった。
それから60年以上が過ぎ、
手紙を長い眠りから覚ますきっかけとなる
1本の映画が封切りになる。
クリント・イーストウッド監督の
『硫黄島からの手紙』だった。
映画を観たヴォーゲリンさんは
手紙を日本の家族に返すことを決意する。
「持ち帰ったときは
戦争の思い出の品として
いい考えだと思っていました。
ところが歳をとるにつれて
ひどいことをしてしまったと
思うようになっていたのです」
ヴォーゲンさんは
その時の心情をこう語った。
どうすれば手紙の持ち主の家族を
見つけることができるのか。
手紙に何が書いてあるかもわからない。
困り果てたヴォーゲンさんは
大胆にもクリント・イーストウッドに頼もうと考えた。
『硫黄島からの手紙』を撮った監督なら
興味を持つかもしれないと思ったのだ。
カリフォルニアにある
イーストウッドの事務所を見つけ出して
電話をしてみたが、
受付と話すのがやっとだった。
無理もない。
相手は超多忙の映画監督なのだ。
それでもヴォーゲリンさんはあきらめなかった。
ニューヨーク州の日本総領事館に連絡するとともに、
地元の新聞社に記事にしてもらえないか売り込んだ。
新聞に載れば誰かが手紙を訳してくれて
手がかりが見つかるのではないか、
そう考えたのだ。
ヴォーゲリンさんの思惑は的中することになる。
地元紙が彼の申し出をうけて掲載、
わがニューヨーク支局のスタッフが
この記事を見つけて興味を示した。
これは面白いニュースの“ネタ”になると
彼が私のところにその記事を持ってきたのだ。
すぐにヴォーゲリンさんに連絡をとり
私たちは車で2時間ほど走って、
その日の午後にはニューヨーク郊外にある
ヴォーゲリンさんの自宅のドアをたたいた。
ヴォーゲリンさんは、にこやかに
私たちを迎えてくれた。
どちらかというと取材という行為は
嫌がられることのほうが多いのだが、
このときばかりは歓迎されるべき客人だった。
何しろようやく日本語が読める人間が
目の前に現れたのだ。
ヴォーゲリンさんは
さっそく部屋の奥から
古びた茶色のトランクを持ってきた。
あけてみるとそこには
葉書100通と8通の封書が
丁寧に束ねられて入っていた。
60年以上がたっているとは思えないほど
保存状態はよかった。
時代を感じさせたのはその紙質だった。
今の葉書よりきめが粗く、厚めで、
四方はきれいに裁断されておらず
ざらりとした手触りだった。
手紙にはすべて
『検閲済』という四角いスタンプが押され
検閲した担当者の苗字とみられる
赤い印鑑も押されていた。
宛名はすべて『松川正』、
差出人はほとんどが『松川正一』と記され
文字はかなりの達筆だった。
何通かの手紙を読むうち
ふたりの関係が理解できた。
宛名の松川正という男性が
硫黄島にいたであろう日本兵、
差出人の松川正一さんは、日本に住む父親だった。
父親が戦場に赴いた息子にあてた手紙だったのだ。
あて先の住所は、
すべて国内にある軍の施設となっていた。
息子がどこの戦地に赴いているかは
軍事機密として家族に知らされていなかったのだろう。
手紙に見入っている私を
ヴォーゲリンさんが
待ちきれない、といった様子で見つめる。
私は手紙から読み取れる状況を説明したあと
書かれている内容を
一枚ずつヴォーゲリンさんに伝えていった。
たとえばこんな具合だ。
「昨夜は二人共
興奮して眠れませんでした。
戦況を聞いたものですから。
お赤飯をいただきました」
「今はめっきり寒くなりました。
手足が凍えるようです。
父母共、元気ですから安心してください。
貴君も元気と知りまして、安心いたしました。
母も喜んでおります。
では体に注意してしっかり」
中にはまだ学生である弟からの葉書もあった。
「この1年死にもの狂いでがんばります。
決して兄上に負けません。
そして兄上のあとに続きます」
さらに硫黄島の正さんが
日本にいる恩師にあてて書いたものの
結局、出せなかった葉書も中に含まれていた。
そこには神風特攻隊の戦果を聞いて
自分もあとに続く決意を述べるなど
硫黄島の決戦へのたかぶりが
感じられる文面だった。
ヴォーゲリンさんは
身じろぎもせず聞いていた。
時おり声をあげてうなずき、涙ぐんだ。
そして言った。
「この手紙を家族の元に返してあげたい」
手がかりは父子の名前と、
父親が鹿児島にある女学校の校長であると
手紙に記されていたことだった。
私は鹿児島の放送局にお願いして調べてもらった。
すると弟が関西に住んでいることがわかり
今度は大阪の局に調査を依頼、
弟はいま神戸に住んでいることまでわかった。
ニューヨークから鹿児島、そして大阪と
リレーしながらたどり着いたのだ。
ヴォーゲリンさんが喜んだのは言うまでもない。
ただ問題はどうやって渡すかということだった。
ヴォーゲリンさんは、当初
日本から家族に来てもらって
アメリカで渡すことを思い描いた。
ところが神戸に住む弟さんは病気がちで
もはや長旅はかなわぬ夢だった。
ヴォーゲリンさんは
自分が日本に行って直接手渡したいと思い始める。
しかしそのためには、誰かが
ヴォーゲリンさんの航空運賃や宿泊費などを捻出し、
日本までアテンドする必要があった。
日本領事館に預けて
代わりに渡してもらうという案を
ヴォーゲリンさんに持ちかけてみたが
自分が知らない人間に託すことには
抵抗があるようだった。
私は厚生労働省に相談し、
日本のある民間団体にも持ちかけてみた。
丁寧に対応していただいたものの、
そう簡単にことは進まなかった。
それと並行して
ヴォーゲリンさんの物語を
アメリカのテレビ局に売り込むことにした。
これは日本にとってもニュースだが
アメリカにとってもニュースになるに違いない。
イーストウッドの『硫黄島からの手紙』は
もちろんアメリカでも話題になっていたのだ。
3大ネットワークのひとつ
CBSテレビがすぐに飛びついて
夕方ニュースで取り上げ、
ヴォーゲリンさんの顔が全米に流れた。
救いの神は思わぬところから現れる。
ヴォーゲリンさんの友人である
アメリカの経済紙の関係者が
手紙を届ける役を買って出たのだ。
信頼できる知人が日本に行って
手紙を直接手渡してくれるのなら
自分が行かなくても構わない、
ヴォーゲリンさんはそう考えた。
硫黄島の砂浜で拾われ、
アメリカまで旅した108通の手紙は、
62年の時を経て、今度は日本に向け
配達されることになった。
手紙は神戸のホテルで家族に返された。
私はその場面に、立ち会っていないので
詳しく書くことはできないが、
家族はアメリカのヴォーゲリンさんと
電話をつなぎ、初めて会話を交わした。
そこでヴォーゲリンさんは
日本兵の家族の話に初めて触れることになる。
手紙の宛名だった正さんが
硫黄島にいたことは
家族の誰にも知らされていなかった。
鹿児島で育った正さんは、
京都大学在学中に学徒動員で
海軍に入り、南方の戦線に送られた。
家族がわかっていたのはそこまでだった。
終戦から半年ほどが過ぎた1946年の1月、
政府の担当者が自宅を訪れ、
正さんが南方の戦地で死亡したと告げた。
遺骨もなければ、詳しい状況すらわからない。
一枚の死亡通知だけだった。
父親の正一さんはそれを受け取ろうとしなかった。
その後、父親が亡くなり、母親もあとに続いた。
そのとき初めて正さんの名前は
墓石に刻まれたという。
クリント・イーストウッド監督の
『硫黄島からの手紙』は、
日本兵から見た硫黄島の戦いを描いている。
アメリカ人の監督が
日本兵たちを主役にして
その人間的側面を描き込んだ映画を
つくるのはこれまで記憶にない。
108通の手紙を前に
ヴォーゲリンさんは語った。
「この手紙の日本人にも愛する人がいる。
クリント・イーストウッド監督が
背中を押してくれました」
人々を動かすものはいったい何だろう。
おそらく精巧な論理でも立派なスローガンでもない。
心の奥深いところまで届く“物語”が
より大きな力を持ちうることを
ヴォーゲリンさんの言葉は教えてくれる。
(終わり) |