私はやはりこのインタビューは
厳しいかもしれないと思い始めていた。
だが次の質問で、その考えを変えることになった。
私はクロンカイトにとって、
おそらく最も輝かしい瞬間について触れることにした。
ベトナム戦争をめぐる彼のコメントだ。
1968年、ベトナム戦争が泥沼化する中で、
クロンカイトは現地で取材し特別番組を放送した。
クロンカイトはこれから述べることは
個人的な意見であると前置きし、次のように語った。
「今日、われわれは勝利に近づいていると言うとすれば、
それは、これまで明らかに過ちを続けてきた
楽観主義者を信じることにほかなりません。
一方、われわれは
敗北の淵に立たされているというとすれば、
それは、いわれのない悲観主義に
屈服することであります。
したがって、われわれは
こう着状態という泥沼にはまり込んでいると言うのが、
不満足ではありますが、唯一、
現実的な結論のように思われます」
クロンカイトは戦況をこう分析したうえで、
次のように結論づける。
「ここから抜け出すための、
理にかなったただひとつの道は、
勝利者としてではなく、
民主主義を守るという誓いに忠実に
最善の努力をしてきた名誉ある国民として
交渉の場に臨むことであるとの思いを、
私は一段と深めるにいたりました」
それまでクロンカイトが
自分の意見を番組で言ったことはほとんどなかった。
禁欲的だったクロンカイトが、
一線を踏み越えたことから、
その効果は絶大なものとなった。
当時のジョンソン大統領は
「クロンカイトを失ったということは、
アメリカの主流を失ったも同然だ」と漏らしたという。
ノンフィクション作家のデイビッド・ハルバースタムは
著作『メディアの権力』の中で、
「テレビのアンカーマン(キャスター)が
戦争の終結を宣言したのは、歴史上かつてなかった」
と記している。
私は次のような問いかけを、彼に発してみた。
「もし今、あなたが
イブニング・ニュースの
アンカーマン(キャスター)だったとしたら、
イラク戦争についてどのようにコメントしますか?」
当時、イラク戦争が始まってすでに3年がたっていた。
私は「もしあなたがいまアンカーマンだったら」
という部分を繰り返した。
クロンカイトはかすかに表情を緩めて言った。
「中東でも、私が極東で言ったことを
繰り返すでしょう。
なぜなら私はイラクから
出るべきだと思っているからです。
私は、イラク戦争は失敗だと思っています。
最初から行くべきではなかった。
CIAの情報が間違っていたのは明らかです。
国のどこにも大量破壊兵器はありませんでしたし、
我々を危険に陥れるような核兵器も
ありませんでした。
この戦争を始めた理由は
本当ではなかったんですから、
イラクから出るべきです」
クロンカイトはきっぱりと答えた。
「ニュースのキャスターは
意見を言うべきなのでしょうか?」
「言うべきだと思います。
ただし意見であるとわかるよう
区別することが必要です。
ニュースには意見を交えず、
ストレートに出さなくてはなりません」
そこまで言ったあと、
クロンカイトは声がかすれて、
言葉が出なくなった。
秘書が用意していた水をクロンカイトに手渡す。
彼はプラスチックのコップを
ゆっくりと口元に持っていき、
水を口の中に流し込んだ。
私はコップを受け取ると、
クロンカイトの椅子の足元に置いた。
クロンカイトはひとつ咳払いをすると、
私のほうを見て
「今の答えをもう一度最初から」と
しぼり出すような声で言った。
「リポーターにはふたつのスタンスがあります。
ひとつはニュースを伝えること、
もうひとつは個人的な意見を言うことです。
ふたつは常に分けなくてはいけません。
常にニュースと意見を
区別して伝えられなくてはならず、
まぜこぜにすべきではないのです。
まずニュースのリポートだけをやる、
そして私がベトナム戦争の時にやったように、
これからこの問題について個人的な意見を言います、と
前置きしてから言う。
それが大事なのです。
私のベトナム戦争の放送は
すばらしく価値がありました。
大統領が
自分は職を失うかもしれないと言ったのです。
これ以上価値のあるものがあるでしょうか」
クロンカイトはそう言って、
このうえなく満足そうに微笑んだ。
ベトナム戦争報道について語るクロンカイトは
生気に満ちて、
エネルギーが溢れているように見えた。
「あなたのベトナム報道、
そしてエド・マローのマッカーシー報道は、
権力へのチェック機能という
メディアの最も大事な仕事をしていると思います。
現在のメディアは、権力へのチェック機能を
果たしているでしょうか?」
「活字メディアもテレビメディアも
何が起きているか事実を伝えることで、
機能を果たしていると私は思います。
新聞の場合で言うと、
社説のページでは新聞としての意見を述べ、
コラムニストも彼らの見方を提示しています。
放送はそこまでやってはいません。
ただ代わりに、
私がそれを好きかは別問題ですが、
トークショーと呼ばれるものがあります。
これは放送で意見を言うのとは
ちょっと異なりますが、
この手の番組はたくさんありますし、
大衆も好んでいるようです。
我々が何十年か前に
やっていたのとは違うやり方で、
大衆は個人的な意見を聞くことができます」
このあと、私は宿題であるテレビの公共性、
さらに新聞とテレビの役割の違いや、
アメリカの保守とリベラルについて訊ねた。
そのたび秘書が大声で通訳してくれた。
約束の時間はとうに過ぎていた。
私はテレビのニュースに携わる人間が抱える、
永遠のジレンマについても訊ねてみた。
「テレビニュースに携わるものは、
視聴率を気にするべきでしょうか」
これに対するクロンカイトの答えは
はっきりしていた。
「はい、視聴率に目を向けなければなりません。
大衆の支持が得られないと、
新聞は発行部数が落ち、
テレビは視聴者を失います。
この仕事を続けられなくなります。
だからこそ自分の放送が観られているか、
新聞が読まれているかどうか、
ある程度関心を持たなければならないのです」
インターネットをめぐるクロンカイトの思いは
興味深いものだった。
彼の現役時代には、
インターネットなど想像すらできなかっただろう。
「インターネットは若い人にとても人気があります。
新しいスタイルですし、
読みたい記事を選ぶことができます。
理解できないニュースや、
知りたくないニュース、
またそれについて全く知らないニュースに
耳を傾ける必要がなくなります。
その結果、彼らのニュースへの知識は
非常に限られたものになるのです。
興味を狭めてしまいます。
彼らはインターネットで
新しいことを学ばないうえに、
テレビのニュースを見なくなっています。
テレビよりインターネットを好んでいます。
これは本当によくないことです。
今の時代の知識を広げられないし、
限られたニュースしか見なくなります。
そして心配なのはテレビの視聴者が
高齢になっていることです。
若い人はテレビを観なくなっています。
もし視聴者が減って広告も減り、
もうからなくなったらと、
テレビ局を経営している人々は懸念しています」
こう話した上で、クロンカイトは語気を強めた。
「すると経営陣は文句とともにこう言います。
もっと面白く(ENTERTAINING)するようにと。
ですがニュースは
面白く(ENTERTAINING)するものではありません。
こうは言えるでしょう。
もっと興味深く(INTERESTING)するべきです。
ENTERTAINING よりも
INTERESTINGにするのです。
なぜならニュースは娯楽番組ではありません。
事実に基づいているのです。
それは常に視聴者もジャーナリストも
思い起こさなければなりません」
ニュースは『面白く(ENTERTAINING)』ではなく、
『興味深く(INTERESTING)』しなければならない。
クロンカイトの言葉は、
今の時代のテレビニュースへの強い警告のように思えた。
もうひとつ訊いておきたいことがあった。
「あなたは毎日番組の最後に
“that's the way it is”
(きょうはこんなところです)と
締めくくっていました。
いつどのようにして、
このフレーズを思いついたのですか」
クロンカイトはしばらく考えてから口を開いた。
「最初のころニュース時間は15分でした。
これが30分になったとき、
私はたっぷり時間があると思いました。
ところが30分でも
充分ではないことはすぐにわかりました。
私は通信社で長く働いていましたので、
世界のどこに居ても、
悲しい物語も楽しい話も
わすか1、2段落で送るよう求められました。
世界中の支局が送るのです。
新聞はこの中から選んで
一面のどこかに載せたものでした。
私はニュース枠が30分になって時間が増えた時に、
これを番組の最後でやろうと思いました。
ところが、ある日は悲しい話、
ある日は楽しい話を伝えたあと、
なんとかして番組を締めくくらなければ
ならないことに気付きました。
そうした話を包み込むような
フレーズでなければなりません。
私が思いついたのは
『きょうはこんなところです』でした。
それから番組のしめくくりの言葉になったのです」
クロンカイトは穏やかな表情で続けた。
「私が試みたのは、
その日のしめくくりを示すような
何かを言うことでした。
上司のひとりはこのフレーズを嫌っていました。
彼はこう言うんです。
『きょうはこんなところです、って言うけど、
そんなこと保証できるか』と。
確かにその通りでした。
ですがもう視聴者に受け入れられていたので、
これで行こうと決めました」
クロンカイトはさもうれしそうに付け加えた。
「私がこれまでもらった最も愉快な手紙のひとつは、
五歳の少年から届いた、走り書きのような手紙でした。
そこにはこう書いてありました。
クロンカイトさんに
『きょうはこんなところです』って
もう言わないように頼んでください。
じゃないと、クロンカイトさんがそう言ったら、
ぼくは寝なきゃいけないんです」
そう言って、クロンカイトはなつかしそうに微笑んだ。
「時間をとっていただきありがとうございました」
私はインタビューのお礼を言った。
「とてもいいインタビューでしたね」
クロンカイトは
インタビュアーに気を使うことも忘れなかった。
彼は秘書に手を引かれて、
ゆっくりと自分の机に移動し、
柔らかな大きな椅子に腰を降ろした。
すべてはスローモーションの世界だった。
我々は機材を片付けて部屋の外に出し、
椅子やテーブルを元あった場所に戻した。
あとはクロンカイトの執務風景を撮影するだけだった。
秘書が「音は入りませんよね」と、気にしている。
クロンカイトはジョージ・クルーニーと
電話で話していた。
スピーカーフォンを大音量にしていたので、
我々にもジョージ・クルーニーの声が
はっきりと聞こえてきた。
私はその風景を見ながら
クロンカイトとの1時間を振り返っていた。
インタビュアーが訊きたいことを
どれだけ引き出せるかがインタビューだとすると、
決してうまくいったとは言えなかった。
だがクロンカイトが私の質問に関係なく、
話したいことを話したのは間違いない。
それはテレビジャーナリズムについて
彼がどうしても言い残しておきたいことでも
あるように思えた。
そうした意味では
私は『クロンカイトの遺言』とでもいうべきものを
聞いたのかもしれなかった。
後に驚いたことがある。
オフィスに戻ってVTRをチェックした。
画面で見るクロンカイトは、
実際よりはるかに強い印象を発していた。
耳の遠さや足元のおぼつかなさは一切感じられず、
かくしゃくとし、威厳を放っていた。
彼の現役時代を知らない私にとって、
クロンカイトがクロンカイトであることを
実感した瞬間だった。
もうひとつエピソードを紹介して、
この文章を終えようと思う。
クロンカイトの後をついで、
20年以上『イブニング・ニュース』の
キャスターをつとめたダン・ラザーは、
番組の最後で「That's part of our world」
(きょう、世界ではこんなこともありました)
というフレーズを好んで使った。
クロンカイトの「That's the way it is」
(きょうはこんなところです)と比べると、
時代が透けて見えるようで面白い。
テレビが茶の間の王様だった頃のクロンカイトと、
ケーブルテレビやインターネット、
果ては携帯電話まで出現して、
地上波テレビが多くのメディアの
ひとつになったダン・ラザーの時代を、
彼らのフレーズが
そのまま映し出しているようにも思えるのだ。
(終わり)
|





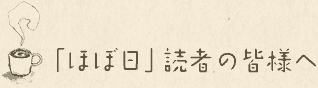
![クロンカイトの遺言 [2] クロンカイトの遺言 [2]](images_new/vol22_title.jpg)