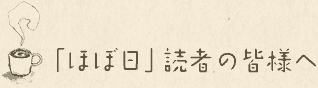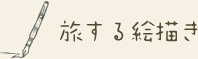好きなことをして暮らす。
そしてそれが誰かの心に届き、仕事になる。
こんな幸せな生き方はないだろう。
自らを“絵描き”と呼ぶ下田昌克さんも、
たぶんそのひとりだ。
しかもその道のりは、
「好きなことをしたいなら努力しなさい」
というもっともらしい説教も、
とたんに説得力を失ってしまうほどの軽やかさだ。
下田さんの自宅を訪ねたのは、3月の終わり、
寒さがわずかに和らいだ午後だった。
東京渋谷区にあるアパートの薄暗い階段を登っていくと、
急に視界が開けて
テラスのようなスペースが広がっている。
ふと見るとハンモックがかかっていて、
そばに下田昌克さんが立っていた。
初対面だったのでもちろん挨拶をしたのだが、
よく覚えていない。
それよりもハンモックがかすかに揺れていて、
下田さんがそばにいるその風景が心に焼きついた。
ハンモックの心地よさといったらない。
沈み込むソファーとも、ふかふかのベッドとも違う、
不思議な浮遊感に包まれる。
それからというもの、
下田さんとハンモックのイメージが、
私の中で分ち難いものとして育っていくことになる。
「東京に18歳で出てきて、ここに住んだんですけど、
まさかここで40を迎えるとは」
そう言って、下田さんは少しばかり
照れくさそうな表情を浮かべた。
下田さんはTシャツにGパン姿、短髪で、
無精ひげが口の周りにはりついている。
そしてその笑顔は、
私が今まで接したことのないものだった。
人の警戒心を一瞬にして解かせる力を持っている、
魂がむき出しになった動物のような笑顔だった。
ドアをあけて自宅におじゃまする。
42歳で独身、お世辞にも片付いているとは言えない。
玄関を入ってすぐ、
右手に壁に立てかけられた巨大な絵が目にはいる。
去年亡くなったロックシンガー、
忌野清志郎さんだとすぐにわかる。
壁いっぱいほどの大きさの顔だ。
「高校時代から好きで、
覚えているうちに描かなきゃって。
高校のとき、ライブ見に行ったから、
思い出しながらいきなり描き始めて。
全然似てないでしょう。
でも写真見て描くのは悔しいじゃないですか」
私から見ると、一目で清志郎とわかるほど似ていた。
ただ自分の描くものは似顔絵ではないので、
似ていることに意味があるわけではないと、
下田さんは言う。
何より、そのタッチが新鮮だった。
さまざまな色の線が、
重なりあって顔が形作られていた。
「どうやって色を選んでいくんですか?」と私は訊ねた。
「なんとなく。普段、色鉛筆で書いていくんですが、
色鉛筆は色数が限られているので、60色くらいかな」
キッチンの奥に、小さな部屋がある。
真ん中に大きな四角いテーブルが置かれ、
そこが仕事場にもなっているようだった。
部屋にはたくさんのスケッチブックが
無造作に置かれていた。どれをあけても、
そこには色鉛筆で描かれた人の顔であふれていた。
顔は決して肌色などではなかった。
赤、紫、オレンジ、青などなど、
色という色の線ですべての顔はできていた。
そこに輪郭は必要ない。
それでもひとりひとり違う顔になり、
異なる表情を浮かべている。
それにしても、どうして色鉛筆なのだろう。
「ほら、油絵とかだと準備とか、
後片付けとか面倒でしょう。
それって好きじゃないから。
色鉛筆だったら、削っとけばいいので」
そう言って、下田さんは大きく笑った。
下田昌克さんは、1967年に兵庫県で生まれた。
小さい頃から絵を描くのが好きで、
高校時代は美術科で学んだが、
プロになろうと思っていたわけではなかった。
東京に出てデザイン研究所で学んだあと、
いくつかの会社につとめたが、
どれも長続きしなかった。
そして25歳でリストラにあう。
「100万円たまっていたんです。
だからこれを持って中国に行って、
北京ダックを食べて豪遊しようと思ったんです。
神戸から出ている船に乗って、
上海に向かいました」
ところが北京ダックもすぐに飽きてしまう。
ついでにと、その足で向かったチベットが、
その後に下田さんの人生を決定的に変えることになった。
下田さんは、日記代わりに、
色鉛筆で会う人会う人の顔を描いていく。
「この人とは、市場で出会ったんですけど、
描いていたら人が集まってきて、
恥ずかしくなったのか、いなくなっちゃった」
下田さんはスケッチブックを開きながら、
なつかしそうに思い出を語ってくれた。
「彼女は学生で、放課後、街を案内してくれたなあ。
この彼は、洋服屋で働いていたんだ」
描いたひとりひとりのエピソードを
いまも覚えているという。
「日記のつもりで人の顔を描いていたら、
だんだん面白くなっていったんですね」
彼はチベットのあと、ヨーロッパにも立ち寄った。
気がつくと、2年がたっていた。
あり金も使い果たした彼は、
250枚ほどの顔を持って日本に戻る。
その後のあてがあったわけではなかった。
ところがある日、
飲み屋でスケッチブックを見せていたら、
編集者を紹介してくれる人が現れて、
少しずつ仕事が舞い込むようになった。
2年の旅の記録が本にもなった。
「Private World」というタイトルのこの本は、
旅の途上で描いた世界の人の顔、
写真やチケットなどがコラージュされている。
こんなのあり? という声が聞こえてきそうなほど、
幸せな本だ。
北京ダックを食べるぞという不純な動機で始まった旅が、
れっきとした商品になったのだ。
下田さんが私の顔を描いてくれるという。
部屋を出て、屋上にのぼる。
360度、東京が見渡せるすばらしい眺望だ。
椅子を置いて、向かい合って座る。
その日、私はノーネクタイながらスーツを着ていた。
スーツを着ている人を描いたことあるかなあ、
と下田さんがつぶやく。
最初に黄土色の色鉛筆を手にして、最初の線を入れる。
描き始めるとあとは早い。
次々と色鉛筆を持ち替えて、線を重ねていく。
「仕事はどうやってくるの? 売り込むんですか?」と
描いている下田さんに訊ねた。
「あまり売り込んだりしないなあ。
本作りたいときは、
協力してくれる人を探したりするけど、
基本、ぼーっとして待ってます」
「いま42歳という年齢はどうですか?」
「こんなんじゃないと思っていました。
経済力とか人格とか落ち着きとか、
自動的に身につくと思っていたけど、
全部に努力がいることに数年前に気がつきました」
好きなことが仕事になっていることを、
彼はどう思っているのだろうか。
「絵とか描いて生きていけるなんて、
日本ってすげえって思います。感謝しています」
「でもいつもこんなはずでは、と思ってきました。
今こうなっているのも、
もちろん目指していたんでしょうけど、
どこか消去法だった。
(リストラされて)
会社員やらせてもらえなかったとか、
30歳になって続けられそうなのが
これしかなかったとか。
本当はこういう仕事は
力強く目指していないといけないと思うけど‥‥。
なんで人に出来ることができないんだろう、
と思ってた。
同級生とか、みんな会社につとめているのに、
なんで僕にはできないんだろうと。
みんなは家族もつくってちゃんとやってるのに、
ぼくはこの体たらく‥‥」
「好きなことをやっている負い目は感じます。
みんなが家族とか抱えてやっているのに、
こんな好きなことばっかりやってていいのかな、と。
でもどこを大事にするかが問題のように
思うようになってきました。
好きじゃないけど家族のためにがんばっているとか、
かっこいいと思う。
最近は何やってても一緒の気がするんです。
会社員でも、いきなり好きなことできないでしょう。
周りを説得しなきゃいけないし、
結果を積み重ね、自分の居場所つくって‥‥、
何やってようと関係ないんじゃないかと思うんですよ。
どこをどう大事にするかが、
わかってればいいんじゃないかあ」
描いているときに、話しかけられるのは嫌じゃないと、
下田さんは言う。
でもしゃべればしゃべるほど、
ふだん考えてないことがわかるなあ、と苦笑した。
その間も、私の顔を見てはキャンバスに目を落とし、
休みなく線を描き続けている。
「10年後、どうしてるでしょう?」
「絵を描いていたらいいなあ」
「どんな存在になりたい?」
「ぼくはずっと名刺をちゃんと作ってないんです。
肩書きを書いたら、それになれそうな気がして、
いい肩書きを考えて、
決まらないままに10年すぎちゃった」
「画家ではない?」
「偉そうですよね。こんなの自己申告なんでしょうけど、
いいのが浮かばないんです」
描き始めて20分ほどたったところで、
雨粒が落ちてきた。
「やばい、これ水性なんです」
と言って下田さんは立ちあがる。
私は描きかけの絵を自分の横に掲げてみる。
「似てなかった?」とあわてたように下田さんが言う。
「似ていることに意味はないんですよね?」
と言ってみる。
「次からそんな言い訳しないようにします」
下田さんがおどけたように笑った。
下田さんはこれからも肩書きなどないまま、
地球に生きる人々を描き続けるのだろう。
そして今もハンモックを揺らしながら
次なる旅を密かに計画しているに違いない。
(終わり)
下田昌克さんの本
『Private World』はこちら。
また、下田さんのホームページはこちらです。
|