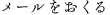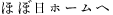しゃべりながら謙一は違和感を感じた。どうもおかしい。 しかし謙一は同じテンションでしゃべり続けなければならなかった。なぜなら、彼は相手を煙に巻こうとしていたからだ。ひとつひとつ丁寧に説明しているように見せて、大きな枠組みでは堂々巡りを繰り返す。これが、謙一が知らず知らずのうちに身につけてきた技術だった。 謙一は昔から異性にもてた。しかし、軽薄なつき合いに溺れたわけではない。彼は、少なくとも彼自身の認識によれば、ひとつひとつの関係に誠実に対応した。そのサイクルが短かろうと、頻繁に繰り返されようと、それは根本の誠実さを損なうものではない。謙一はそういった言い分を準備していた。しかし、そういった自己の解釈をいろんな角度から終えていたこと自体、ある種の後ろめたさの証明であるといえるのかもしれなかった。 また、謙一は別れ際に弱かった。彼は惚れっぽく、飽きっぽく、それでいて異性を惹きつける魅力に恵まれていた。つまり、資質としては遊びのように恋を重ねる典型だったが、終わりゆく恋に対して毅然と向き合うことができなかった。簡単にいえば、別れ際に彼はぐずぐずした。ほとんど関係が終わっていても、それを完全に終わらせることがどうしてもできなかった。 ちなみにそれは恋愛に限った話ではなかった。彼は、およそあらゆる「際」に弱かった。じゃあね、と言って歩き出すことのできない男だった。つまらないと感じても飲み会に最後まで残った。部屋や車やスーツが自分の生活に合わなくなってきても、簡単に換えられなかった。メールの往復を自分の番で終わらせることが嫌だった。とくに好きでもなかったバスケットボール部を、結局、中高6年間も続けた。眠りに落ちるぎりぎりまでテレビと部屋の灯りを消せなかった。 彼はフェードアウトを好んだ。いつの間にか変わっていたり終わっていたりするように彼は努めた。グラデをかけようとした。螺旋階段で移動しようとした。扉を開けたり脱皮したりするよりも、シームレスなメタモルフォーゼを彼は好んだ。 それで、ある恋が彼の飽きっぽさによって終わろうとするとき、原因が自分自身にあるにもかかわらず、彼は問題を棚上げしようとした。終止符を打つでもなく、修復を試みるでもなく、ただただ無責任にその場をやり過ごそうとした。 従って、相手はいつもわけがわからなかった。当たり前だ。 しゃべりながら謙一は、由希子の目からどんどん精気が失われていくのを感じていた。それは、謙一にとって都合のよいことだった。堂々巡りを繰り返していくと、今日こそは決着をつけようと意気込んでいた相手は次第にぼんやりしていく。そのようにして今日は無理かもしれないと相手に感じさせ、結論を少しでも先送りし、しかるのちに二人の接する間隔を空け、だんだんと謙一は終わらせたかった。だから、由希子の瞳の光が鈍くなっていくことは、謙一にとって歓迎すべきことだった。 けれども、謙一はさっきから違和感を感じていた。おかしい。 いま、由希子の反応は、謙一の想定するいずれのパターンにも当てはまらなかった。高ぶった感情が落ち着き、だんだんと言葉が少なくなる。そこまではいわば予定通りだった。しかし、そこから諦めに向かわず、違ったフェイズに由希子は入っているようだった。 ひと言でいえば、彼女はそわそわしていた。なにか別のことを忙しなく考えているようだった。あらぬ方向を見ていて、落ち着きがなかった。 反論しようとしているわけではない。泣き叫ぶパターンとも違う。怒りに震えてもいない。ただ、なんだろう、ひどくそわそわしている。少し汗ばんでいるようだ。というか、彼女はいまどこを見ている? 瞬間、由希子の右肩が不自然に揺れた。連動するその指先が、テーブルの上を、何かを求めるように不規則に移動した。 そう、コップのあたり。 謙一の背中に短い電気が走った。あまりにもはっきりとそれが感じられたから、最初、謙一は持っている自分のiPhone5が着信して震えたのかと思った。ズボンのポケットからさり気なくそれを取り出して確かめたが、クマがプリントされているケースに覆われたiPhone5にはなんのメッセージもなかった。 すると違和感の元はやはり目の前の女性にある。そこまで確信すると、謙一はあえて由希子から目を切った。それは、ずいぶん昔の経験に基づいた自然な振る舞いだった。からだが覚えていた、というべきだろうか。 中学高校とバスケットボールを続けたのは謙一の本位ではなかったが、皮肉なことに謙一は最後の数年間で才能を開花させた。謙一は、県内でも屈指のポイントガードとして知られるようになっていた。人気漫画『スラムダンク』の登場人物とイメージが重なったらしく「国泰寺高のリョータ」と異名がついた。それがうれしくて髪型をリョータに似せようとしたが、床屋にうまく伝わらず、往年の中畑清のような刈り上げになった。あまり思い出したくない過去だ。 ともあれ、瞬時、感じ取った違和感は、謙一の五感を真夏の体育館へさかのぼらせた。コートを踏みしめるキュッキュッという音が耳に響くようだった。 試合終盤。もうこれ以上ポイントをやれない場面。ゾーンディフェンス。正面でドリブルする敵チームのエース。 なにか仕掛けてくる、と感じたときは、相手の目を覗き込んではいけない。そうではなくて、視線は相手を突き抜けてからだひとつ奥くらいに焦点を合わせる。感じ取るんだ。 右手から左手に移るドリブル。また右手戻ってくるボール。キュキュッと床の鳴る音。ダムダムと体育館の床を打つボール。 中へのパスか。カットインを警戒。いちばん怖いのはスリーポイント。繰り返すドリブル。刻まれる時間。逆転までに許された時間は、あと1分程度。 3年の夏、県大会準決勝の最終ピリオドで謙一が成功させたスティールは、後輩達の間でちょっとした伝説になった。敵チームのエースはまず低いドリブルを一発打ってカットインする素振りを見せた。フェイントはキレていた。が、謙一はピクリとも動かなかった。そして次の瞬間、謙一はマークした相手とまったく無関係な場所へ飛び出した。無謀。しかし飛び出したその場所にノールックパスが来た。どんぴしゃだった。 夏の体育館に轟くどよめきを背に受けながら、パスカットした謙一はそのままひとりで速攻。落ち着いてレイアップシュート──。 そう、相手の目を覗き込んではいけない。謙一は、あらためて由希子の気配を探った。彼女は、何をしようとしている? 煮え切らぬ別れ際に、コップの水をぶっかけることによって幕を引こうとしている由希子は、腹を決めてはいたものの、技術的な未知に戸惑っていた。そして、彼女もまた、場に漂う尋常鳴らざる空気を感じ取っていた。 謙一の目が正面から自分を見据えていた。否、その視線は自分を射貫いて、からだひとつ奥のあたりに焦点を結んでいた。 行かなければ、と由希子は思った。行動は状況に押し出される形となった。つまり、不自然だった。そこへ向かいかけたが、リスクを感じて由希子のなかにせめぎ合いが生じた。瞬発しかけた上半身が、つんのめる。 謙一の研ぎ澄まされた感覚はその隙を逃さなかった。そのドリブルは、フェイクだ。本当の目的は、そっちじゃなくて、逆。 謙一は感じ取った場所を見た。そこにあるのは、コップだ。なみなみと水の注がれたコップ。まさか、彼女は? 言葉にするより速く、謙一の右手は反応した。 つんのめった由希子の指の先にあるコップを、謙一は鮮やかにスティールした。そしてそのまま自分の口もとに持っていくと、ごくごくごくごくごくごく、と一気に飲んだ。コップは一瞬にして空になってテーブルの元の位置に戻った。 ああっ、と由希子は思った。 (続く) |
| 2013-05-25-SAT |

 |
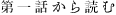 |
 |

 |
|||
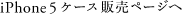 |
|||
 |
|||
|
|||
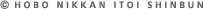 |