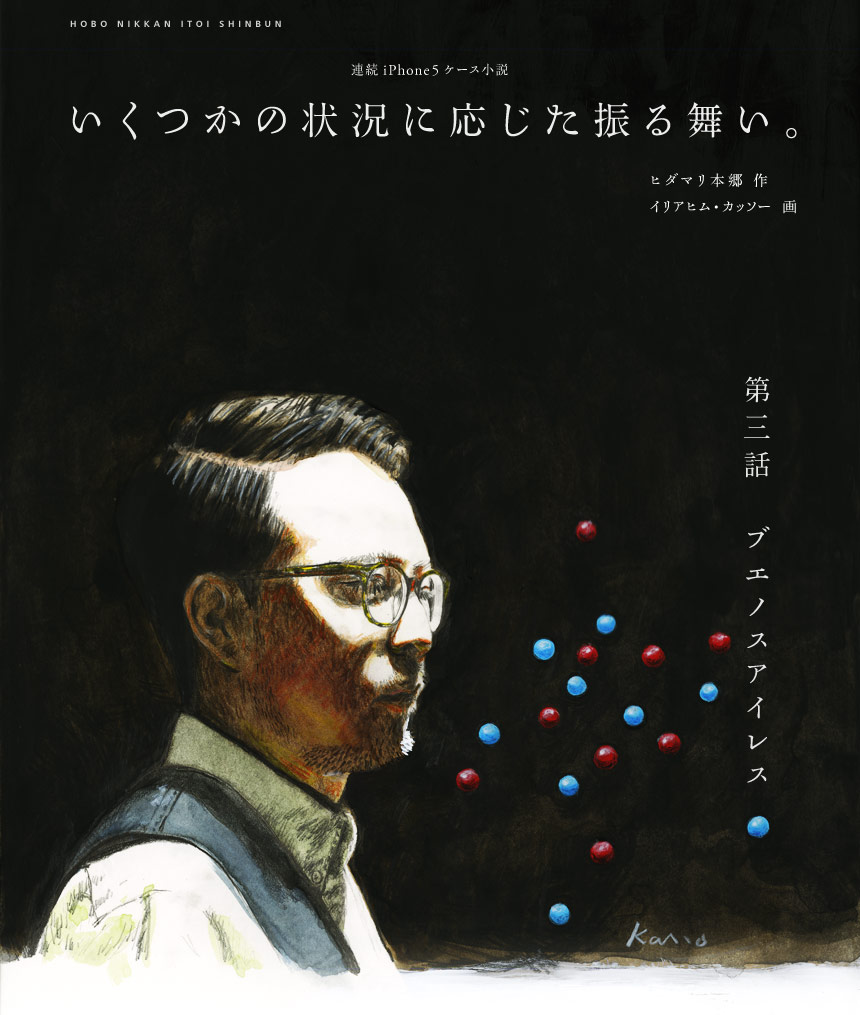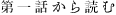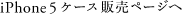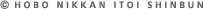いま、まさに、目の前の男にぶっかけようと思っていたコップの水が、その男によって飲み干されていく。かといって由希子に為す術はなかった。謙一は最後の一滴まで喉へ流し込むと、空になったコップを誇らしげにテーブルへ戻した。タン、という小気味のよい音がした。
由希子は、空になったコップを見つめた。しばし、呆然とした。男にぶっかけるべき水はもうない。まったく予想しないことだった。いや、男にコップの水をぶっかけるという自分の行動こそ、まったく予想しないことだったはずだ。しかし、それはまるで相手に読まれていたかのようで、事実、謙一は由希子が事に及ぶその間際にコップを奪って水を飲み干してしまったのだ。
由希子は、呆然としていた。
一方、謙一は根拠のない達成感に包まれていた。自分が何を成し遂げたのかは、わからない。だが俺はやったのだと謙一は確信していた。遅れてきた快感の電撃が背中の真ん中をじわじわと駆け上がっていった。そう、あの夏の体育館と同じだった。
謙一は由希子を見た。由希子は空のコップを見つめたまま動けずにいた。頬は幾分青ざめ、瞳は鈍く淀んでいた。さっきまで全身を研ぎ澄ませていたライバルが、いま、ゲームセットの笛を受け入れられずコートに立ち尽くしている。
そんな由希子を見ていると、思いがけず謙一の胸に切ない思いがこみ上げてきた。それは、渡り合った好敵手と去り際にことばを交わしたくなる、とてもスポーティーな感情だった。いま謙一は、由希子を違った価値観で大事に感じていた。
なんと声をかければいいだろう、と謙一は思った。しばし、ふたりはそのままだった。
今村はカウンターのなかでグラスを磨くふりをして、一部始終を見ていた。もちろん、両者の細かな思惑まではうかがい知れない。けれども、高まった緊張と張り詰めた空気が何かのはずみに霧散し、どういうわけか明暗が分かれたということを、今村は感じ取っていた。
今村は、察する男だった。そして察するがゆえに、行動できない男だった。誰にとっても事情というものがある。今村にはいつも相手の事情がよく見えた。しかし、相手は今村の事情に興味がないことがほとんどだった。そしてそういう構造そのものを、今村はよく察した。それで今村はまず相手の事情を尊重し、自分の行動や主張をいつも後回しにした。
それは優しさであると同時に煮え切らなさでもあった。結局、自分の離婚の原因もそこにあると今村はわかっていた。自分は決定的なミスを犯したわけではない。しかし、悪循環の全体を引き受けるべきは自分だった。煮え切らないというのは、ある状況におけるひとつの態度をいうのではなく、暮らしの底にずっと停滞しているゆるやかな渦のようなものである。その曖昧な渦が妻を息苦しくし、やがて今村自身をも飲みこんでいったのだ。そのようにして二人の関係は去年終わった。
彼の元妻は先月からブエノスアイレスへ移住していた。せめてそれに反対するくらいの態度は表明してよかったが、意見を求められてさえ、今村は相手の事情を察して尊重した。それはそれで仕方がないことだと今村は諦めていたが、娘に会えないことだけがひどくつらかった。
こんなつらい思いをするくらいなら、少しぐらいは他人の事情を軽んじてもいい、と今村は思った。自分が自分のために行動することを、遅まきながら今村は学ぼうとしていた。誰にとっても事情はある。しかし、それは自分も同じだ。
今村はポケットからiPhoneを取り出し、パスコードを入力してロックを解除した。4桁の数字は娘の誕生日だった。待ち受け画面には先週送られてきた娘の笑顔の写真。笑顔の背後に異国の街。どこなんだそこは。ブエノスアイレスってどこなんだ。ブエノスアイレスの気温は何度なんだ。ブエノスアイレスへは何処経由で行くんだ。ブエノスアイレスはいま何時なんだ。ブエノスアイレスは首都なのか。ブエノスアイレスってちょっと名前として長すぎるんじゃないのか。ブエノスアイレスにはブエノスアイレス料理があるのか。ブエノスアイレスはブエノスとアイレスに分かれてるわけじゃないのか。まったく、ブエノスアイレスときたら。ふたり合わせてブエノスアイレスです。どこなんだそこは、ブエノスアイレス。
今村はiPhoneをスリープさせ、それをひっくり返して背面のワニのデザインを眺めた。その特徴あるデザインのiPhoneケースは、娘とペアで買ったものだった。「なにこのヘンな絵」と笑う娘に、今村は「テリー・ジョンスンだよ」と説明したが、娘はただケラケラと笑うだけだった。どうあれ、彼女がテリー・ジョンスンのセンスをおもしろがってくれてよかった、と今村は思った。
テリー・ジョンスンとブエノスアイレス、と今村は小さく口に出してみた。それだって、自分なりの行動だと今村は思った。他人の事情は知らない。
「テリー・ジョンスンと、ブエノスアイレス」
今村は娘の笑顔に勇気をもらって、カウンターから出た。以前の彼からは考えられないことだ。放っておけばいい。自分には関係ない。いや、むしろ、迷惑なだけだ。察するがゆえ、今村にはわかった。第三者としても、店の主としても、介入するべきではない。けれども、今村はいまカウンターから離れて歩いていく。その席へと近づいていく。右手には容器をもっている。
うつろな表情で由希子は座っていた。生き生きと熱弁を振るう謙一の前で、彼女にはどんな選択肢さえなかった。彼女は萎縮し、精神的に飲まれていた。大げさにいえば、彼女には希望がなかった。
そこへ、近づいてくるものがある。由希子は気づいた。謙一も背後に気配を感じて軽くそちらを見た。見た瞬間、謙一のアスリート的な本能がなんらかの警告を発した。謙一がその信号を解析し終わる前に、今村は速やかに行動した。さり気なく、当たり前に、自然な振る舞いとして。
今村は、空っぽになったコップを手にとり、ピッチャーからその中へなみなみと水を注いだ。コップは、再びいっぱいになった。
終わったはずの試合が動き出す。まさかのリスタートだった。由希子の頬に、さっと赤みが戻る。さぁ、1本! 謙一が慌ててコートへ戻る。ディフェンス!
行動を終えた今村は静かにカウンター内の自分の持ち場へと戻っていく。
ふたりが机をはさんで身構えたそのとき、喫茶デュラムセモリナの入口の扉についている古風なドアベルが、カラァンカラァンと鳴った。
いらっしゃいませ、と今村は反射的に言ったが、厳密に言えば、入ってきたのは客でなかった。
(続く)
|