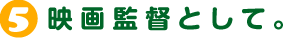 |
| 糸井 |
『ザ・マジックアワー』のように
脚本家と監督を両方やるときは
どっちのほうにウェイトがかかるんですか? |
 |
| 三谷 |
うーん‥‥じつは、脚本家と監督って、
もう、分けられなくなってきてるんですよ。
現場で撮影をしているときに
決定稿ができあがっていくみたいな感じなんです。
もちろん、事前に台本を書き上げて、
それをもとにみなさんが演技をするんですけど、
現場で化学変化みたいなことが起こって、
どんどんよくなることもあれば、
思ったほどうまくいかないときもある。
それを見ながら僕が整理して、
ほかのことばに直していく、
というような作業を続けていくと、
できあがったものを観たときに、
そこに流れているセリフは
脚本家が書いたセリフではあるんですけど、
7割くらいは現場でつくっている
というような感覚があるんです。 |
 |
| 糸井 |
あああ、なるほど、なるほど。 |
| 三谷 |
だから、じつは、脚本家としては、
自分で演出をする、監督をやるっていうことは
決していいことじゃないような気がするんです。
つまり、どんどん雑になっていく。 |
| 糸井 |
脚本が。 |
| 三谷 |
ええ。最初の本が。 |
| 糸井 |
雑になっていくというか、
ゆるくなっていくんですね。 |
| 三谷 |
ゆるくなりますね。 |
| 糸井 |
でも、それは脚本家にとっても
いいストレッチになるんじゃないですかね。
大づかみには作れるようになりますよね。 |
| 三谷 |
ええ。それで、できることはできるんです。
実際、舞台の脚本を書いているときなんかは、
もっとゆるかったりするんです。
「稽古でつくっていけばいい」って思ってるから、
自分が演出するときなんかは、
「現場で口で言えばいいや」みたいな感じで
ト書きも書かなかったりするんです。
だから、結果的にできたものがよければ
なんの問題もないんですけど、
一脚本家として考えると、あまりよくないですね。 |
 |
| 糸井 |
でも、4作目ということで、
だんだん慣れてきてはいるんじゃないですか。
その、ふたり組としての自分の役割に。 |
| 三谷 |
そうなんです。
やっとコンビネーションが
うまくできてきた感じはちょっとしますね。 |
| 糸井 |
それは、どっちの自分が
うまくなってきたんでしょうね。
やっぱり、監督でしょうか。 |
| 三谷 |
そうですね‥‥。
やっと、もう、遅いぐらいなんですけど、
監督をするというのがどういうことなのか、
おぼろげながら見えてきた感じなんです。 |
| 糸井 |
ほぅ。 |
| 三谷 |
つまり、監督というのは、
ぜんぶを決めなきゃいけないんです。
単にアングルを決めるとか
芝居をつけるとかっていうことだけではなく、
映っているもの、全部。
役者さんの髪型から衣装から、
腰掛ける位置の深さまで。
そういうところこそがセンスというか、
監督に求められるものなんだなって。 |
| 糸井 |
うん、うん。 |
| 三谷 |
これは、このあいだ、『BRUTUS』の記事で
立川談志師匠とお会いしたときに出た話なんですが、
エルンスト・ルビッチっていう映画監督の
『生活の設計』という昔の映画があるんです。
いま観るとちょっと古いコメディなんですけど、
すごく品があって、おもしろいんですよ。
で、この映画のなにがいいのかと思ったときに
象徴的な場面がひとつあって、それは
主人公の好きな人が自分の部屋にやってくる
という場面なんですけど、
ドキドキしながら待っているとノックの音がして、
「あ、来た」と思ってドアを開けると
そこに知らない子どもが立っているんです。
その、子どもの身長がすごくちょうどいいんです。 |
 |
| 糸井 |
なるほど(笑)。 |
| 三谷 |
あれ以上、小さすぎてもダメだし、
大きすぎてもおもしろくない。
あれ、たまたまそこにいた子どもを
使ったわけじゃないと僕は思うんです。
オーディションしたのがどうかわかんないけども、
もっというと意識的にやったのか
無意識にそうしたのかわかんないんですけど、
やっぱり「ベストな背の高さ」の子どもを
選んでそこに立たせていると思うんです。
それを選ぶのが監督の仕事というか、
センスなんだなというのが、ようやく、
なんかちょっとわかってきたんです。 |
| 糸井 |
そういうことを、三谷さんは、
「脚本ということばの中においては」
すでに散々やってきたはずだと思うんです。
たとえば、ある人物がしゃべるセリフの助詞が
「なぜ『が』じゃなくて『は』なのか」
というようなことは、
その古い映画の中の子どもの背の高さのように、
もう、当たり前に、選んできた。 |
| 三谷 |
そうですね。 |
| 糸井 |
で、そういうことばの仕事をしているときは、
「子どもの、ぴったりの背の高さ」ということには
逆に、目を向けちゃダメだと思うんですね。
つまり、「うわ、ちょうどいい子どもが
いなかったらたいへんじゃん!」って思いながら
脚本を書くわけにはいかないから。
だから、そういうことには目を閉じて書いてきた。
ところが、監督を何回かこなしてみたら、
いままで目を向けないようにしていたことが、
散々選んできたことばのひとつひとつみたいに
見えてきたということなんじゃないかな。 |
| 三谷 |
そうですね。そういう意味では、
舞台と映画比べてると、
映画のほうがはるかに多弁なんですよね。
もう、ことばにあふれてますから。 |
| 糸井 |
そうですね。 |
| 三谷 |
だから、
決めなきゃいけないことがたくさんあるぶん、
間違いやすいというか
間違う選択肢もたくさんある。
でも、その意味では、今回の映画で、
ちょっと自分を信じられるようになった
というのはありますね。 |
| 糸井 |
ああ、いいですね。 |
 |
| 三谷 |
あの、僕は本当に、自分が映画監督として
才能があるっていうふうにずっと思ってなくて、
むしろ、ないと思ってたぐらいなんです。
それはやっぱり、映画は大好きで
ずっと観てたんですけども、
やっぱり脚本家として観てしまうので、
「あ、この伏線の張り方はおもしろいな」とか
「この脚本はよくできてるな」
という見方はするけれども、
「この演出はすごいな」とか、
「このカット割り、このアングルはいいな」
っていうふうには観たことがなかったので、
自分で映画を撮るときも、もう本当に、
脚本を素直に映像化することが
自分の仕事だとしか思ってなかった。 |
| 糸井 |
なるほど。 |
| 三谷 |
だから、
「なんて自分はアングルの
見つけ方がヘタなんだろう」とか、
現場を引っ張っていくという意味でも
「監督として、なんて不的確なんだろう」
というようなことばっかりで、
それは、いまだにそうなんです。
ただ、自分が意識して、あるいは無意識に、
なにか細かいことを選んでいく部分。
それは結果的にその映画が豊かになっていくことに
つながっていく細かい選択だと思うんですけど、
その選択については間違えてないと思ったんです。
AとBのうちのAを選んだとか、
この色を選んだとか、この帽子を選んだとか、
そういう細かいことに関していうと、
僕は間違えていない。
少なくとも自分にはそう思えた。
だとしたら、ひょっとしたら僕は映画監督として
大丈夫なんじゃないかっていうことを
はじめて思ったわけなんですね。 |
 |
| 糸井 |
なるほど、なるほど。 |
| 三谷 |
もちろん、それ以外のいろんなこと、
ずっと僕がダメだなと思ってたことは
いまだにダメなんですけども、
でも、それだけじゃないんだってことが
ちょっとわかっただけでも、
この映画をやってよかったなって気はしますね。 |
 |
|
(続きます!)
|