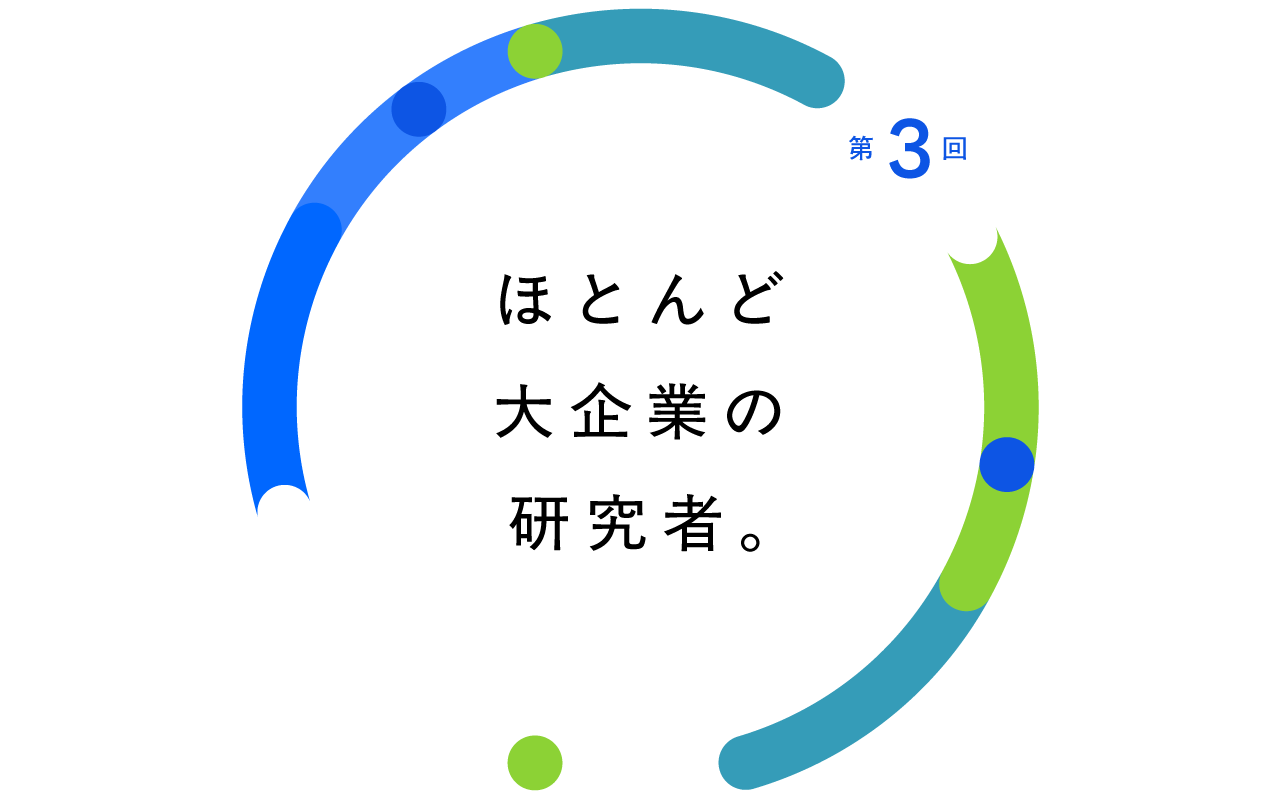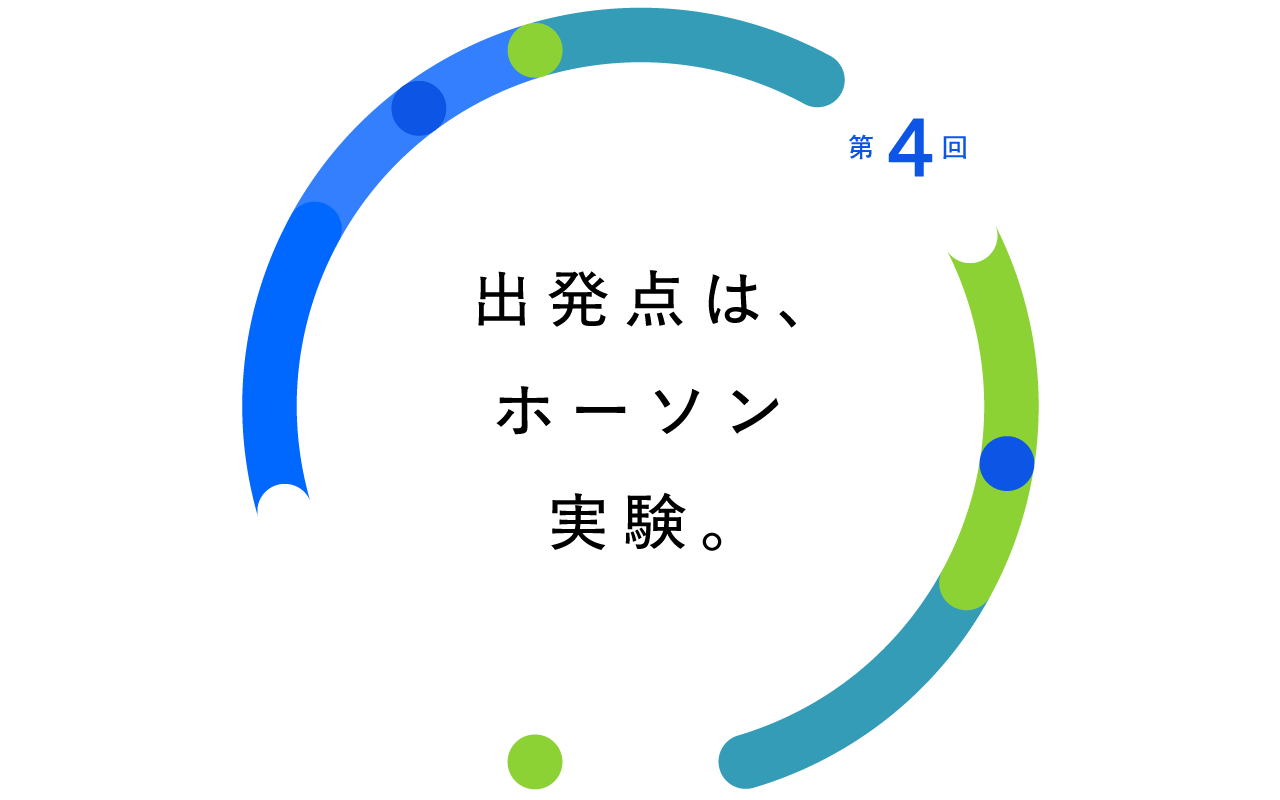主として「田舎の中小企業」を研究している
経営学者の三宅秀道先生が、
「ここ10年くらい、
ずーーーっと考え続けてきたこと」の一端に
触れる機会を得ました。
なぜ、経営学は「都会の大企業」ばかりを
学問の対象にしてきたのか?
そんな素朴な質問をしに行ったはずなのに、
先生の思考は、キリスト教の歴史など
遥か遠く(に思える)場所まで飛んでいき、
ふたたび「経営学」へと戻ってきました。
大宇宙を駆ける、ハレー彗星の軌道みたいだ。
ああ、人の脳みその自由自在よ。
全10回、担当は「ほぼ日」の奥野です。
三宅秀道(みやけひでみち)
経営学者、専修大学経営学部准教授。1973年生まれ。神戸育ち。1996年、早稲田大学商学部卒業。都市文化研究所、東京都品川区産業振興課などを経て、2007年、早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学。東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究センター特任研究員、フランス国立社会科学高等研究院学術研究員などを歴任。専門は商品企画論、ベンチャー企業論、ファミリービジネス論。
- ──
- これまでうかがったような
都市と田舎のビジネスの違いの考察、
まずは
おもしろいなあと思ったんですが、
高度経済成長期の東京では、
どういった感じだったんでしょうか。
- 三宅
- 東京にいれば、工業化の波に乗って、
新技術を活かした製品を、
周囲を気にせず
どんどんつくっていたと思いますよ。 - 工業化のプロセスそれ自体が、
新しい市場をうみだしてましたから。
経済のパイが広がっている場所では、
生々しい淘汰が起きずに済む。
- ──
- 負けても致命傷になりにくい側面も、
成長局面では、あったりとか。
- 三宅
- 勝ったり負けたりするけど、
たがいの切磋琢磨につながりますし。 - 戦いに負けてしまった会社が、
それでも倒れず、
別分野に活路を見出していくことも、
ふつうにありましたよね。
- ──
- 西田敏行さんが主演なさった映画
『陽はまた昇る』は、
家庭用VTRの規格の競争で
VHSがベータに勝った物語ですけど、
あのとき負けたのは「ソニー」ですもんね。
- 三宅
- そういう勝ち負けだとか競争こそが
「社会の活力」ですから、
否定する気は、もちろんないです。 - そもそも経営学者という存在自体が
他学問の研究者に比しても、
大都市に偏在してる気がするんです。
つまり、ほとんどの経営学者は、
大企業を研究の対象にしているので。
- ──
- おお、おもしろい。
- 文化人類学の研究者みたいですね。
調査対象の近くに住んでる。
- 三宅
- 大学の教員というのはたいてい、
進学校からいい大学へ入って
同級生が大会社へ入社していく中、
自分は大学院に残った人なんですよ。 - そうすると、ほとんどの経営学者は、
興味の対象が「大企業」になる。
まるでゲームのように競争ができて、
心置きなく相手を負かせる人たちが、
メインの研究対象なんです。
- ──
- 先生は、そういうことに、
いつごろから気づいていたんですか。
- 三宅
- 就活の学生の相談に乗っていたとき、
地方から上京してきた学生が、
「競争」というものに
倫理的抵抗を感じてるんじゃないか、
ということに気がつきました。 - 経営学には「競争とは勝つべきもの」
という暗黙の前提がありますし、
地方の中小企業を研究していた
ぼくにとっても、盲点だったんです。
「そうか、みんな、そんなにも
競争を嫌がってたんだ」
という新鮮な発見がありましたので。
- ──
- なるほど。
- 三宅
- その意味では、ぼくの故郷の神戸は、
近代化以降に集まった人ばかりなので、
非常に例外的な街ですね。
- ──
- 経営学はアメリカ生まれだという話で、
あるていど納得したんですが、
「経営学の研究対象のほとんど」が
「大企業」だった理由を、
もう少し詳しくお聞きしたいのですが。
- 三宅
- 水戸黄門に出てくる越後屋みたいな
「企業」自体は、
もちろん近代以前からありましたが、
ジェネラル・エレクトリックや
デュポンみたいな大企業って、
それまでのような、
「親方」がいて、
そのもとで100人の職人が
船をつくってるような世界じゃなく、
フォーディズムなどの
新しい経営思想を持っていたんです。
- ──
- フォーディズムというと、
ヘンリー・フォードが導入した
自動車の大量生産方式、のことですね。
- 三宅
- 何百人どころか、何千人、
何万人もの従業員を抱える大企業が、
急にビジネスの主体、
社会のメインプレイヤーとして
台頭してきたのが、
20世紀のはじめのころなんですよ。 - ある意味、そのことへの驚きで、
近代の経営学は、うまれてるんです。
- ──
- うみの親が、大企業。そもそも。
- 三宅
- 社員が「100人、200人」だったら、
社長さんが
マメにコミュニケーションを図れば、
顔の見える関係を維持できるし、
社員それぞれの気心も、
なんとか知れる範囲だと思うんです。 - でも、1000人なったら無理ですよ。
- ──
- なるほど。その意味では
1000人以上の社員さんのお名前を
覚えてらっしゃった
六花亭の先代社長の小田豊さんは、
やっぱり特別なんですね。
- 三宅
- そういう方はさすがにレアです。
しかも、ただ工場のラインに立って、
ひたすら
電球にカバーを乗っけていく係では、
何のためにはたらいているのか
実感を持てなかったり、
自分の持ち場のずーっと先のほうで
最終的にできあがるものが、
まったく
想像のつかないものであったりする。 - 農村でチーズをつくっていたときは
お客さんの笑顔が見れたのに。
つまり、どうやって
社員のモチベーションを維持するか、
みたいな課題が発生したんです。
何百人ぶんの人材管理や労務管理も、
誰もやったことないし。
- ──
- ええ。
- 三宅
- そこで、当時の人たちは、
それまでの世の中に存在しなかった
巨大企業を動かすために、
行政や軍隊から学んだりしたんです。 - 人間をひとつの目的の下に統率する、
そのための「ノウハウ」を。
- ──
- ああ‥‥じゃ、フォード副社長から
米国防長官に転身して、
データ重視で、ヴェトナム戦争の
舵取りをしようとした
ロバート・マクナマラという人は、
ある意味では、
「もといた場所へ戻ってきた」
とも言えるわけですか。おもしろい。
- 三宅
- だから戦略論とか、ミッションとか、
ビジネスの世界には、
軍事学とか行政学由来の語彙が多い。 - まあ、ちょっと話がズレましたけど、
そんなわけで
いまの日本の経営学者の95%は、
大企業の研究をしていると思います。
- ──
- でも先生は、中小企業論をやってる。
- 三宅
- そもそも中小企業論は異端ですけど、
でも、中小企業って
日本経済にとっては大事らしいから、
経営学部に
1人くらいはいなきゃいけないねと。 - そのときに、
町工場を歩き回ってるやつがいたな、
あ、いたいた、三宅だということで、
わたしがやってる感じですかね。

(つづきます)
撮影:福冨ちはる
2024-12-04-WED
-
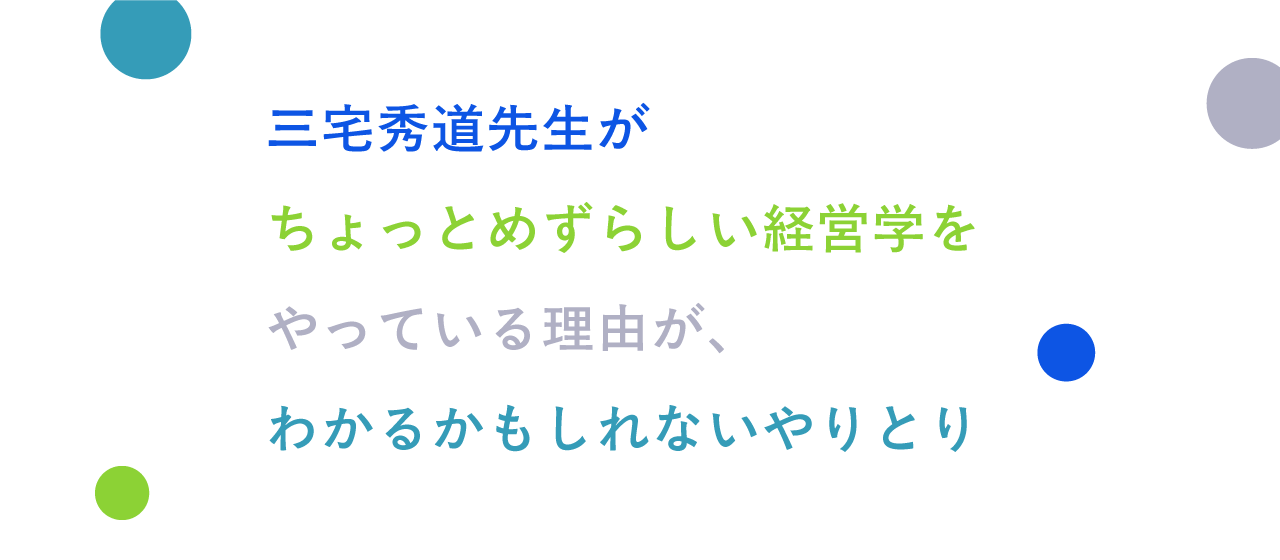
三宅先生は、研究対象としてなかなか注目されない
「田舎の中小企業」を見つめ続けてきました。
ふとしたやりとりのなかに、
その理由の一端が
理解できるかもしれない(?)くだりがありました。
先生が、この連載で話していることの、
ひとつの「補助線」になるかもしれないと思って、
先生のご許可をいただいて、
メッセージの文面を以下に転載させていただきます。
あの人はどうしてそこを見つめているのか、
誰かが何かをなす「動機」とは。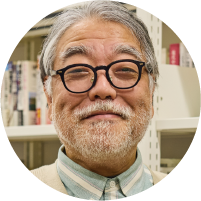 わたしは、ちいさいころ、
わたしは、ちいさいころ、
親の「上昇志向」のプレッシャーをかけられて
ずいぶん苦しみました。
かなりのスパルタ教育だったと思います。
その理由は、イエの歴史をたどるとわかるんです。
うちの父親は、祖父が
いわゆる御妾さんに産ませた庶子だったんです。
だから、正妻の家庭への対抗意識が、
出世志向になったんだろうなといまでは思えます。
だからわたしも大学で上京するまでは、
親に叩き込まれたメリトクラシーを奉じてました。
他の価値観を知らなかったのです。※「メリトクラシー」とは、
「能力で社会的地位が決まる社会」のこと。
対する「アリストクラシー」は、
「血統で社会的地位が決まる社会」のこと。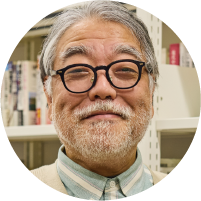 祖父は、社会的経済的に大成功した起業家でした。
祖父は、社会的経済的に大成功した起業家でした。
そして祖母は祖父のだいぶ年下の御妾さんでした。
貧しい境遇からは這い上がれたかもしれませんが、
屈辱はあったと思います。
戦前の話ですが、
当時60歳の祖父に囲われたときの祖母は、
17歳くらいなんです。
そんな妾宅で育った父が、何としても社会的栄達、
経済的成功をつかみたがった原動力、
ルサンチマンの元は、そこにあると思っています。
われわれ子どもへの教育方針は、粗暴な根性論。
だからわたしは、ずいぶん無理やりに勉強をして
東京の大学(早稲田大学商学部)に入学したんです。
そういう背景があったので、わたし自身が、
人を押しのけて競争に勝つという欲望の奥底には
一体なにがあるんだろう‥‥と思いながら、
経営学をやってきたようなところがあると思います。