
2024年、ほぼ日の「老いと死」特集が
満を持してスタートしました。
そのかたすみで、
ひっそりと生まれた企画がひとつ。
「正直、老いや死のことを、
まだあまりイメージできない」という
2、30代の乗組員が、ざっくばらんに話し合う
「老いと死の歌座談会」です。
おそらく私たちの手に負えるテーマではないけれど、
いま考えていることを、気張らずに話してみます。
‥‥タイトルの「歌う」が気になっている方も
いらっしゃるかもしれません。
よくぞ気づいてくださりました。
そうなんです、座談会の最後は、
毎回のおしゃべりから誕生した歌を
みんなで歌います。
どんな歌が生まれるのか、少しだけ、ご期待ください。
担当は、ほぼ日の20代、松本です。
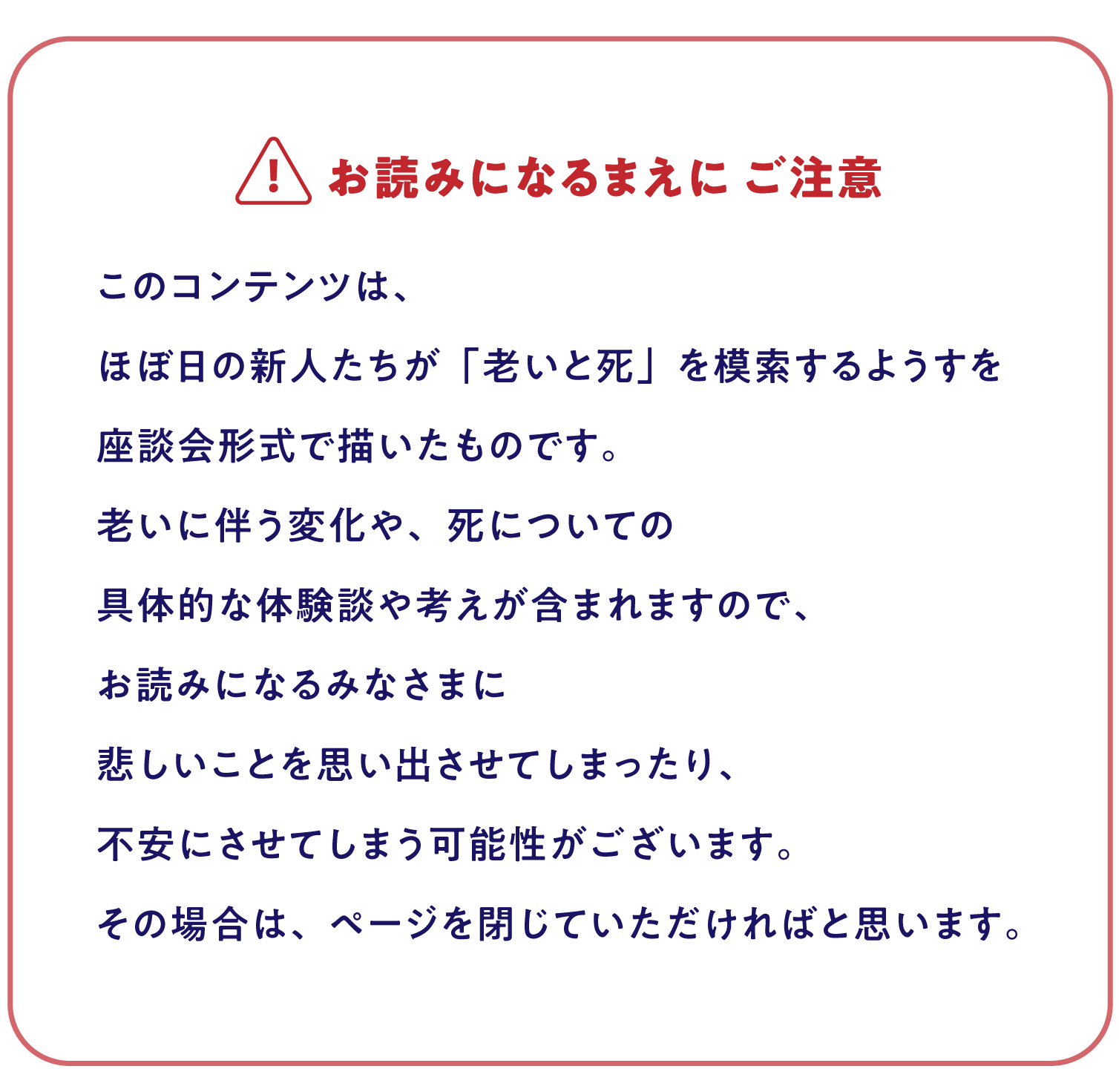
- 向江
- 私は、いままではなんとなく、
生きていくことに対する、
漠然とした不安があったんです。
死が、あまりにも未知すぎるから。
- 菅野
- うんうん。
- 向江
- でも最近は、
いまのところ誰もよくわかっていない
「死」のことと、
実際に日々生きている生活のことは、
切り分けて考えないと、
やっていけないなと思うようになりました。
- 松本
- そういえば、向江さんは以前
「3年後に死ぬつもりで生きる」
という心構えの話をしてくれましたよね。
その考えはいまでもあるんですか。
- 向江
- ああ、それは、
大学の先生が話してくださったことで、
いまも実践しています。
「明日死ぬつもりでやれ」みたいなことは、
たまに言われますよね。
でも、ほんとうに急に明日死ぬとなったら、
お金も全部使い切ってしまうだろうし、
現実味がないと思うんです。
- 菅野
- そうだね。
- 向江
- でも「3年後」だと、
ある程度貯金もしておこうと考えますし、
人間関係を保つ努力も続けられます。
それから、3年間本気を出せば、
やりたいことはだいたいなんでもできると
思うんです。
「どうせ3年だし」と、思い切れることもあれば、
「3年間でできるだけ頑張ろう」
という気持ちにもなれて。

- 菅野
- へえー、おもしろい。
20年くらいの長い道のりだと、
なかなか想像できないものね。
- 松本
- 向江さんからこの話を聞いたとき、
すごいと思って、心に残っていたんです。
向江さんが、死についての考えを、
生活とは少し切り離しておくと言っていましたよね。
そのことと、「3年後に死ぬつもり」というのは、
つながってるような気がします。
- 向江
- ああ、たしかに。
- 松本
- 死を「すごく悲しいこと」として
日々考えるのはたいへんだけれど、
向江さんのお話は、
いま生きやすくなるために、
死を生活に取り入れるということですもんね。
その、死との付き合い方は、
なんだかいいなぁと思いました。
- 菅野
- うん、そうだね。
- 松本
- それから、第3回の座談会でも少し話したのですが、
老年期の課題というのは、
いままでの自分の人生を振り返って
「私の人生にはこういう意味があったんだな」と
統合することらしいんです。
でも、最終的にその状態を目指すのなら、
いまの段階から、人生のいろんなできごとを
「自分にとってはこういう意味があるんだな」
ととらえてもいいんじゃないかなと考えました。
- 菅野
- なるほど。
そうしたら、失敗してしまったときなども
「この失敗にも意味があるんだ」と思えるかもね。
- 松本
- はい。ここまで死についていろいろ話してきて、
いまさらなのですが、私はどちらかというと
「生きてる意味はない派」なんです。
- 千野
- そうなんだ。
- 松本
- でも「どうせ生きてる意味ないしな」と
思ってしまったら、やる気が起きなくて。
死ぬときも
「いろいろな思いをしたけど、
全部、意味なかったんだよなぁー!」
という気持ちになってしまったら
むなしいな、と(笑)。
だから、もう勝手に、例えば
「こういう文章を残したことが、
私の生きてきた意味だったんだ」
と意味を付けて死んでいけるようにしたいです。

- 菅野
- 自分で自分を納得させるんだね。
- 松本
- 人生単位でなくても、日常のできごとに対して
「これは私にとってこういう意味があるな」
と考えて、統合の練習をしていったら、
老年期もうまく統合できるんじゃないかなと思って。
- 菅野
- 私もよく、悩んだり迷ったり困ったりしたときに、
「迷うくらい選べるような、恵まれた環境なんだ」
と考えて乗り切っています。
それもある種の「統合」ですよね、
自分なりの納得というか。
だから、言ってしまえば、
すべて自己満足だと思うんです。
それでいいと思います。
- 松本
- いいんでしょうか。
- 菅野
- 全然いいですよ。それですよ、正解は。
- 松本
- そうか‥‥。
- 全員
- (笑)
- 松本
- でも、「結局、自己満足だ」と割り切ったら
楽になる気持ちもありつつ、
「誰かのためにがんばろう」みたいなやる気は
なくなってしまいませんか。
- 菅野
- うーん。
私は「この人のためにやったけど、
結局、自己満足だったな」と思うことが、
けっこうあります。
逆もそうで、
「一生懸命やっているのはわかるけど、
たぶん、自己満足になってしまっているな」
と感じることもある。

- 松本
- ああ、そうか。
自己満足と自己満足で、
みんな関わり合ってるんですね。
- 菅野
- 私はそう思います。
- 松本
- お互いの自己満足が、
何かのタイミングで奇跡的にちょっと触れ合って、
お互いのためになる、
みたいなこともありますね、きっと。
- 菅野
- うん。自分自身の興味のために
何かを極めている人で、
「あ、この人すごいな」
と感じさせてくれる人もいますよね。
そういう方と出会うことも、私にとっては喜びです。
- 松本
- たしかに。
ということは、むしろ、
自己満足を極めていったほうがいいんでしょうか。
人それぞれの自己満足を。
- 千野
- 「人それぞれ」ってワードで、
なんでも解決できてしまいますね。
- 松本
- たしかに(笑)。
- 千野
- 中学、高校くらいのときって、けっこう
「こういう子とは仲良くしたくない」みたいな
固定観念のようなものがあったと思うんです。
- 菅野
- うん。
- 千野
- でも、大学のときの友だちが、ふと
「人それぞれだから、
その人はそういう人なんだと思えば、
全然大丈夫なんだよ」と言ってくれて。
- 菅野
- うん、うんうん。
- 千野
- それを聞いてから、
この人はこういう人、あの人はああいう人と、
相手のありのままを受け止められるように
なってきました。
苦手な人は苦手だけど、
それもその人が悪いわけではなくて、
「自分とは違う人なんだ」と割り切れる。
割り切ったうえで、
「自分とは違うからこそ、
どういう人なんだろう?」と、
おもしろがれるようになりました。
これもある意味、自己満なのかな(笑)。
- 松本
- 自己満だとしても、
自己満は人間関係をよくしてくれる
場合もあるということですね。
- 向江
- 私は「人それぞれ」はすごく便利な言葉だからこそ、
気をつけないといけないなとも思っていて。
- 千野
- うん、うん。
- 向江
- 「人それぞれ」で片付けてしまうと、
それ以上相手を理解をしようとしなくなってしまう
気がするんです。
- 松本
- ああ、そこで考えるのをやめてしまう。
- 向江
- それがちょっと怖くて、
気をつけているところではあります。
- 松本
- 人それぞれという言葉を
「それ以上考えなくていい免罪符」として使わずに、
千野さんみたいに
「人それぞれなんだ」から、さらに
「どう違っているんだろう」
というところまで知っていこうとできたら、
楽しいのかもしれませんね。
思考停止すると、それこそ、
その瞬間から老いてしまうのかも‥‥。
(第5回その5に続きます。いよいよ、最終回の最終回です。)
2024-12-27-FRI

