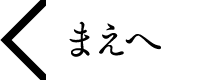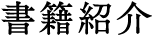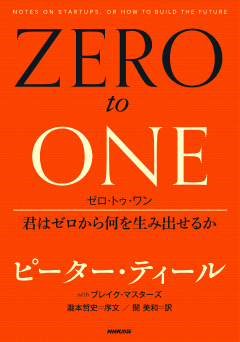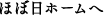「ほとんど賛成する人がいないような
大切な真実とは、なんだろうか?」
それについて、私がどう答えるかということを
今日は、お話ししていきたいと思います。
それでは、まず最初の答えです。
『ゼロ・トゥ・ワン』の
おもなテーマにも関わってくることですが、
多くの人たちは、
「資本主義」と「競争」を同義語だと考えます。
けれども、私は
「資本主義」と「競争」は反意語だと思っています。
資本主義者は資本を蓄積しますが、
完全競争の世界では、
「すべての利益が競争によって失われていく」
と私は思っています。
起業家は唯一無二な地位を築こうとします。
つまり、「独占」を目指すわけです。
社会にとって、独占がいいことなのか悪いことなのかは、
いろいろと議論がありますけれども、
企業側から見ると、やはり「独占する」というのは
とても魅力的なことです。
企業に投資する側から見ても、
やはり独占している企業に魅力を感じます。
競合がいないということは、
ものすごく独創性の高いことを、
非常に上手にやっているということですから。

私の本のなかでは、悪いビジネスの例を挙げています。
それは、たとえば、
お寿司のレストランを東京で開く、といったことです。
私が住んでいるサンフランシスコで
お寿司のレストランを開くというのも
非常に難しいですが、
東京では、もっとたいへんだと思われます。
東京のお寿司はとてもレベルが高くて、競合のお店も多い。
消費者にとってはすばらしい環境ですが、
レストランを開いて成功するというのは非常に難しい。
似通ったお店ばかりが並んでしまい、
自分のレストランを差別化していくのが
非常に難しくなります。
逆に、たいへんうまくいっている独占の例として、
わかりやすいのはGoogleです。
Googleは、いまや唯一無二の
テクノロジーを持つ企業となりました。
2002年以降、Yahoo!やMicrosoftに大きな差をつけていて、
十数年間、大きな利益を上げ続けています。
それは、競合がほとんどまったくいないからです。
この「独占」対「競争」の考えこそ、
ビジネスを理解する上で非常に大切であるにもかかわらず、
多くの人々がなかなか理解できていない。
それは、なぜか。理由がふたつあると思っています。
「知識としての問題」と、「心理的な問題」です。
まず、知識の問題としては、
「ある会社が独占していることは話題にのぼらない」
ということがあります。
なぜなら、独占をしている人たちは、
「独占している事実を伏せたがる」からです。
もしも自分たちが独占していたら、
「自分たちが独占している」とはアナウンスしません。
「独占している」と言うと人々は警戒しますから、
できるだけ独占していることを明かさないようにします。
といっても、ウソを言うわけではありません。
どうするかというと、
たとえば、独占していることを隠すために、
「自分たちがビジネスをしている市場はとても大きい」
というふうに表現します。
Googleの場合だったら、自分たちの業務を、
「検索エンジンビジネス」と
狭義に定義することはしません。
逆に、もっと定義を広げ、曖昧にして、
Googleは自分たちのことを
「テクノロジー企業だ」というふうに言うわけです。
つまり、
「Appleとも競争しているし、
Facebookとも、Amazonとも競争している。
自動運転の自動車の分野では、
世界の自動車メーカーとも競合している」
ということを言って、
自分たちの企業をテクノロジー企業だと
定義しようとするわけです。
そうすることで、自分たちは
厳しい競争にさらされているのだと主張することができ、
当局から独禁法違反に問われることもないわけです。
いまの話と対になることをお話ししましょう。
みなさんの中には、今日の話を聞いて
「ピーターが言っていることには、まったく賛成できない。
自分は東京でレストランを開く」
と思って会場を出る人がいるかもしれません。
しかし、実際にレストランを開業しようとすると
いろいろと困難に直面することになるでしょう。
たとえば、資本を調達するのが難しい。
そんな事業をスタートさせるのはたいへんだよ、
と言われて、投資を受けることもできない。
そうすると、ある種のフィクションを
つくりたくなってしまうんですね。
どうするかというと、
これから自分が立ち上げようとする事業を、
非現実的なほどに狭く定義しようとするのです。
たとえば、お店をアピールするために、
その人はこんなふうに言うでしょう。
「うちの店は、イギリス料理とネパール料理が
融合したユニークなレストランで、
東京では、うち以外にこんなお店はないんだ」と。
たしかに、それだとオリジナリティが感じられて、
唯一無二の事業だといえるかもしれませんが、
それは、現実を歪曲して、
市場を狭く定義してごまかしているにすぎません。
このような形で、事業の競争環境は
いつも歪曲されて理解されていると思います。
実際、Googleの人と話をすると、
トップの5人か10人くらいしか、
私がいまお話ししたことを理解していません。
残りの大勢の社員に
「Googleがなぜ成功しているのか?」と聞くと、
それぞれが独自の解釈を展開します。
たとえば、
「素晴らしい福利厚生があるから」
「優秀な人材がこの企業を伸ばしているから」
「オフィスでマッサージを無料で受けられたり、
床に大きなクッションが置いてあったりするから」
そんなふうに語ったりします。
事業モデルの観点とは、
まったくかけ離れた解釈しか出てこないのです。
つまり「独占」について
十分に理解されていないということです。

いまお話ししている「独占」の概念は、
さまざまなところに応用できる考え方です。
たとえば、事業戦略の考え方に応用すると、
一般論とは真逆のセオリーが得られたりします。
一般的に、事業をはじめるときには
できるだけ大きな市場から、と言われています。
しかし、「独占」を重視する考え方に基づくと、
なによりもまず、
大きなシェアを取れる市場を狙うべきである、
ということになります。
ですから、新しい事業ををはじめるときには、
むしろ比較的小さな市場ではじめるべきです。
それが大きな市場シェアを獲得する最速の方法だからです。
PayPalをスタートさせたときの話をしましょう。
私たちは、PayPalのようなネット上の決済システムが
いずれ世界的に拡大するはずだと確信してはいました。
しかし、まず私たちは、そのはじまりに、
オークションサイトの大手である
「eBay」を日常的に利用している
約2万人のコアなユーザーをターゲットにしました。
彼らは、市場全体から見れば
小さなセグメントに過ぎませんが、
決済に関してはっきりと課題を抱えていました。
ですから、彼ら2万人に対して
よいソリューションを提供できさえすれば、
ゼロからはじめて半年も経たないうちに
35~40パーセントのシェアを獲得できたのです。
また、Facebookが2004年にハーバード大学で
スタートしたときには、対象となる市場は、
ハーバード大学の学生1万2千人しかいなかったんです。
あまりにも小さな市場ですから、
もしこれを事業計画として提案しても、
誰も投資はしなかったでしょう。
でも、市場が小さかったからこそ、
ゼロからはじめて、10日間で60パーセントの
シェアを獲得することができたんです。
Facebookはそのようにして
非常に幸先のよいスタートをきり、
その後、数年をかけて、
その成功をさらに拡大しました。
つまり、事業を戦略的に考えるなら、
小さな市場でスタートし、
その市場を制圧したあと、
同心円状に拡大すべきだと私は考えます。
逆に、ありがちな間違いとしては、
あまりにも大きな市場を狙ってスタートする、
ということが挙げられます。
たとえば、過去10年のシリコンバレーにおける
再生可能エネルギーの分野に
よくあった間違いをお話しすると、
彼らはプレゼンの最初のスライドを見せながら、
こんなふうに言うわけです。
「我々はこのエネルギー市場に参入する。
何十億ドル、何兆ドル規模の市場だ。
その中で獲得できるシェアがごくごく一部だとしても、
事業規模としては十分大きくなる」
しかし、私は、「大海の中の小魚」には
決してなるべきではないと考えています。
様々な方面での競争にさらされますし、
その後どのような課題に直面するかも予想できません。
たとえば、薄膜シリコン太陽光発電事業を
経営しようということであれば、
まず同業9社と競合しなければなりません。
さらに、その他の90社の太陽光発電企業、
さらに風力発電企業と競合しなければなりません。
それを乗り切ったとしても、
急に中国の安い企業が現れて
競争をしかけてくるかもしれません。
つまり、巨大な市場の中で
様々な競争にさらされることになります。
そこでなにかを得るのはたいへん困難だと私は思います。

「独占」の大切さが十分に理解されない
ふたつ目の理由として、
心理的な側面があると思います。
『アンナ・カレーニナ』(トルストイ)の冒頭に、
「幸せな家族はどれも同じように見えるが、
不幸な家族にはそれぞれの不幸の形がある」
と書かれています。
ビジネスにおいては、その反対が真実だと考えています。
幸せな企業は、それぞれの形があるのです。
それぞれ、独自のことを行っているからです。
一方、不幸せな企業はどれも似通っています。
つまり、他社との類似性から逃れられていないのです。
だからこそ、不幸せなのです。
類似性は、競争の本質です。
私の本の中に、
「幸福な企業はみなそれぞれに違う」という章があります。
この章の内容と同じものが
ウォールストリート・ジャーナルに掲載されたとき、
私はその記事のタイトルを
「幸福な企業はみなそれぞれに違う」から、
もっとインパクトのあるタイトルに書き換えました。
それは、「競争は敗者のもの」というタイトルです。
感情を逆なでするようなタイトルですよね。
ふつう、敗者とは、競争できない人を指します。
運動部でいえば、走るのがとても遅い人。
大学受験では、点数が足りない人。
決して、競争に異常なほどに執着して、
競争につぐ競争を重ね、その結果、
大切なものを見失う人を「敗者」とは思わないでしょう。
「競争」が、その分野における
成長や進歩をもたらすことは、まったく否定しません。
でも、一方で「競争」は、
視野が狭まり、全体感を見失うという
犠牲を伴うものでもあるのです。
(つづきます)