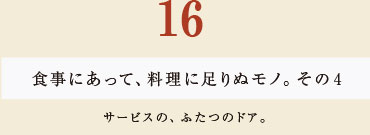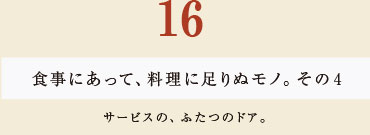どのくらい、寝ていたのでしょう。
ぼんやりとした寝覚めがきます。
高い天井。
クリスタルのシャンデリア。
深いワインレッドの緞帳のようなカーテンの、
端が光のフリルのようになっている。
だからまだ夜になってはいないというのはわかります。
テレビの音がかすかにします。
眠りに入る前に観ていたケーブルニュースの
チャンネルのまま。
けれどボクの眠りを邪魔せぬように、
リッコがボリュームを下げてくれていたのでしょう。
テレビを消してしまうのは、
その部屋の主人であるボクに対して失礼なコト。
テーブルの上に散らかしてあった雑誌も、
ほぼそのままで、けれど飲みかけだった紅茶は
銀のトレーと共に片付けられてた。
腰から下が冷えぬようにとブランケット。
そこはたしかにペントハウススイートのソファの上。
ボクがもし、今、クシャミのひとつでもすれば
リッコがどこからともなく姿をあらわし、
アスピリンをどうぞと差し出す。
‥‥、かもしれないなぁ、と思いながら
ボクはテレビの音を大きくします。
コホンと小さな咳払いがして、
それに続いてキッチンのドアがパタンと開く音がする。
おめざめですか‥‥、とリッコがそこに。
「水を一杯‥‥」
そういうボクに何か言いたそうな‥‥、
いや、聞きたげなリッコに続けて、ボクはいいます。
「おおぶりのグラスに小さな氷をギッシリ入れて、
ヴィッテルをなみなみに注いでちょうだい」
「もし」ヴィッテルがあるのならば、
と言葉を添えようとして、辞めにした。
だって、ボクが知っているモノなんて
たいていココにはあるんだろうから‥‥、
とそう思ったから。
「Perfect」と、リッコは小さくつぶやいて、
部屋をあとにする。
水を飲んだら、気晴らしに街にちょっとでてみようかと、
着替えを探しにスーツケースがあったはずの
クローゼットをあけたらなんと‥‥。
スーツがハンガーに下がってる。
しかもしわ一つなく、
そう言えば、眠りに落ちる寸前に
「パンツやジャケツにアイロンを
おかけいたしましょうか」
と言うリッコの声が聞こえたような、記憶が戻る。
シャツもカーディガンも、そして下着までもが
キチッと畳みなおされ、
キャビネットの中にキレイに収められていた。
こんなことなら、もっとマシなソックスを
もってきておくべきだった。
だって、この旅の間に捨ててしまおうと、
ボロボロになる寸前のものをワザワザ選んでもってきた。
まぁ、しょうがない。
カッコつけてもしょうがないんだから‥‥、
と、もう半ばヤケクソで、
そうそう、リッコも
「自宅で過ごすようにくつろいで」
と言ったじゃないか。
そう思いながら街着に着替え、
さて、部屋を出ようかと鍵を手にしたそのとき。
銀のトレイにギッシリ、氷を詰めた大きなゴブレット。
栓を抜いたばかりのヴィッテルの瓶を片手に、
トクトクとボクの目の前でグラスを満たして、
お待たせしましたとリッコが微笑む。
彼は一体、どこでボクの様子を伺ってるんだろう。
彼は一体、どこからココを出ていって、
どこでボクが必要なモノを調達しては
もどってこうしてくるのだろう。
不思議ばかりが頭に積もり、
考えるのも面倒になり水をあおって
エレベーターを呼んで乗る。
なんだか息がつまるような気がしたのです。
街の空気を吸いたかった。
ロビーに降りて、ボクはマネジャーを探します。
夕刻、ホテルのフロント回りが
あわただしさをます時間で、ロビーにはあふれる人たち。
「聞きたいコトがあったんだけど」
と、彼をみつけようとする前にボクが見つかる。
マネジャーがロビーを横切り、
ボクに近づきやさしい笑顔で
「ステイをたのしんでらっしゃいますか?」
と。
その質問に直接答えず、ボクは用意していた質問をする。
「チップをいつ、
どのように渡せばいいのかわからないのです」
切実でした。
あの部屋で、リッコという魔法使いのような人を
独り占めしておどろくべきサービスを受けているボク。
にもかかわらず、未だ一銭もチップを
わたしていないのですから。
申し訳なくてしょうがないのです‥‥、と。
支配人の答えは明快。
チップとはサービスの一区切りのタイミングで
手渡すモノ。
荷物を運ぶことが仕事のベルボーイには、
荷物を運び終えたときがチップの渡すタイミング。
レストランでは食事を終えたときに
チップを渡すでしょう?
リッコの仕事は、ミスターサカキが
今回のステイがすばらしいモノになるように
お手伝いするコト。
リッコのみならず、
今、このホテルにいる私たちすべてのスタッフは
あなたの心地よいステイをお手伝いするコトを、
この上ないシアワセと思っているのです。
ですからチップは、明日、ご出発になるときに‥‥。
|