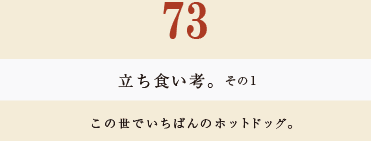 |
|
ただほとんどの店が、客席はなく立ち食いの店。 口さがない友人が、こうもいいます。 安い店に、すわり心地がいい椅子が沢山あったら たしかにそんな考え方もあろうかと、納得しながら、
|
立って食べる。 似たような行為でありつつ、イメージがかなり違って エスプレッソに砂糖をタップリ溶かしたモノを、 通りに面してカウンターのある小さな店で、
|
彼がくる。
|
| 2012-03-01-THU |
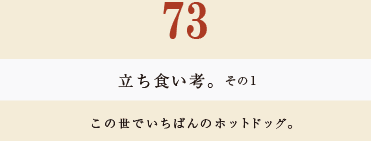 |
|
ただほとんどの店が、客席はなく立ち食いの店。 口さがない友人が、こうもいいます。 安い店に、すわり心地がいい椅子が沢山あったら たしかにそんな考え方もあろうかと、納得しながら、
|
立って食べる。 似たような行為でありつつ、イメージがかなり違って エスプレッソに砂糖をタップリ溶かしたモノを、 通りに面してカウンターのある小さな店で、
|
彼がくる。
|
| 2012-03-01-THU |