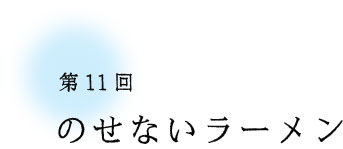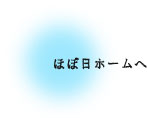| 糸井 | ぼくらにとっては、 自分がまだうまく走れなかった ローギアのころが たしかにおもしろかったけれども、 セカンド発進してる若い人たちがダメかというと 絶対にそんなことはないと思うんです。 |
| 白岩 | そうですか。 |
| 糸井 | それは、自分たちの世代だって、 上の人たちから見れば ローギアすっ飛ばしたセカンド発進だろうし。 |
| 白岩 | ああ、なるほど。 |
| 糸井 | ものや機会にめぐまれてることも、 悪いことじゃないと思う。 「貧すれば鈍する」の反対のことだって たくさんあると思いますよ。 やっぱり豊かさって、心をよくしますから。 豊かで、奪い合う必要がない民族がいたら、 そこはとっても平和だと思うなぁ。 『MOTHER2』でいうと、どせいさんですよね。 |
| 白岩 | ああ、どせいさん(笑)。 |
| 糸井 | うん。どういったらいいかな、 豊かなんだけど、 自分が豊かだと気づいてなくて、 そこで、すごく自然に、 自分のままでいることって いいことだとぼくは思うんですね。 |
| 白岩 | いいこと。そっか。 |
| 糸井 | たとえば、自分の子どもとラーメン屋に行くと、 ぼくなんかはやっぱり、 ラーメンにシナチクのせたり チャーシューのせたりするんですよ。 ふつうのラーメンって頼めないんです。 |
| 白岩 | ?? なんでですか? |
| 糸井 | 「なんでですか?」って言うでしょ(笑)。 |
 |
|
| 白岩 | うん。 |
| 糸井 | そこがいいなぁと思うんですよね。 だから、ぼくなんかは、こう、 より、おいしくしたい、 そのぶんのお金はないわけじゃないし、 って思っちゃうんですよ。 |
| 白岩 | より、おいしくなりますか? |
| 糸井 | そういうふうに 当たり前に思えるのが若い子なんですよ。 だから、子どもは「ラーメン」って ふつうに注文するんです。 ところが、ぼくは、 「どうしようかな、じゃ、メンマ大盛」とかね、 余計なことを言っちゃうんです。 |
| 白岩 | へぇーー、そうですか。 その考えは、まったくないなぁ。 |
| 糸井 | だから、ふつうに「ラーメンひとつ」って 頼める人たちの豊かさに、 もう、たじろぐんですよ。 |
| 白岩 | チャーシューなり、メンマなりを のせるのが正式なことだ、 っていうふうに設定されてるんですかね。 ぼくらは、なければなくてもいいしって思うけど。 |
| 糸井 | あるのに大盛にしちゃうっていう、 そういう貧しさなんですよ。ぼくらは。 |
| 白岩 | そこに価値がぜんぜん感じられないですね。 それをする意味がまずわからない。 |
 |
|
| 糸井 | それなんですよ。 それに、たじろぐんですよ、ぼくは。 たじろぐっていうかね、 親と子の年齢差があったとしても、 ただ「ラーメン」って言う人を、 「かっこいいー!」って思うわけ。 |
| 白岩 | かっこいいんだ(笑)。 |
| 糸井 | だって、立ち食いそば屋に行ったって、 ちくわの天ぷらとか いろいろのっけちゃいますよ。 下手したらちくわの横にコロッケのせて、 こんなに盛り上がったの食って、 「やったー」なんて思ってますよ。 |
| 白岩 | はーー。ぜんぜん、ないですね。 |
| 糸井 | ないでしょう? 白岩さんの小説もそういうところがありますよ。 つまり、のせてないんですよ。 |
| 白岩 | あ、そうか、そうか。のせない、のせない。 |
| 糸井 | ちくわの天ぷらも、チャーシューも。 |
| 白岩 | たしかにそうですね。 要らないと思っちゃうんですよね。 |
| 糸井 | そもそものせるってことを考えてないですよね。 ラーメン食べに来たんだからさ、って。 |
| 白岩 | 考えないですね。 もしも、たのんだものに、いろいろのってたら、 不快なものとして排除すると思いますね。 そうか、そんなふうにして、 知らないところでぼくらは成り立ってるんだ。 |
| 糸井 | この「ついのせちゃう話」っていうのは、 ぼくらが苗木として育ったときに いかに栄養が足りてなかったかっていう証拠で、 認識をあらためるようなことじゃなく、 もう、自分の歴史として刻まれてるんですよ。 ちょっと前に、東京タワーがにょきにょきと 生えていく映画がヒットしましたけど、 あれは、東京タワーが建っていくことに 感動した時代があったっていうことなんです。 ぼくらは、その世代だから、のせるんですよ。 |
| 白岩 | 東京タワーは、 もうずっと前から建ってたもんなぁ。 そっか、そんなことはまったく考えてなかった。 |
| 糸井 | ただね、いま、ぼくは、 「のせる側」の人たちが遠慮しすぎるのも よくないなぁと思ってるんですね。 |
| 白岩 | ああ。 |
| 糸井 | つまり、のせる方も、のせない方も、 両方、遠慮しちゃダメだなと。 |
| 白岩 | それはそうですね。 のせる人はのせるし、 のせない人はのせないし。 |
| 糸井 | うん。のせる人の数って ちっとも少なくないわけだし、 そのバランスは別にかまわないと思う。 |
| 白岩 | おもしろいですね、それ。 のせるとか、のせないとか、 そんな概念、聞いたこともなかった。 |
 |
|
| 糸井 | ああ、そうですか。 あの、違う言い方だけれども、 食べ物って、おいしいものを追求しながら どんどん歳を重ねていくと、 味があるんだかないんだかよくわからない、 みたいなとこまでいくんですよ。 |
| 白岩 | はい、はい。 |
| 糸井 | 「このお出汁は、 昆布をサッとお湯にくぐらせたもので」 みたいなところにいくと、もうそれ、 若い人にはおいしくないとさえ いえるものになってるわけです。 |
| 白岩 | うん、なってますね。 |
| 糸井 | ひとつのほうへ極端に進んでいくと、 そういうことになってしまう。 でも、それもおもしろくないというか、 すくなくともぼくは、 そこへ引っ張られちゃダメだなと思ってる。 で、ここのところぼくは、 急に「カツ丼だ」って言い出したんです。 |
| 白岩 | は? |
| 糸井 | カツ丼に目覚めたというのかな。 |
| 白岩 | ちょっと待ってください(笑)。 急にカツ丼とおっしゃられましたが‥‥。 |
| 糸井 | あのね、だから、ちょっと油断すると、 ぼくも「微妙な昆布のお出汁が」っていう 文壇の人たちがしゃべっているような世界に 口を出してみたいなっていう 気分になっちゃうんですよ。 だから、あえて意識して、 「のせる自分」も遠慮なく復活させていこうと。 その象徴として、「カツ丼だ!」と。 |
| 白岩 | はぁ。 |
| 糸井 | わかんないと思いますけど(笑)。 |
| 白岩 | そうですね(笑)。 そのカツ丼の思想には共感できないというか、 たぶん、ダメでしょうね。 |
| 糸井 | 知らないからね、カツ丼のおいしさを。 |
| 白岩 | じゃあ、もう、 のせない方向で行くしかないな。 こっちはこっちで。 |
| 糸井 | そうするとね、 ミニマルミュージックみたいになるんですよ。 |
| 白岩 | ミニマルミュージック? |
| 糸井 | だから、違うタイプの女の子に 一回、ガツンとふられたりすると いいかもしれませんね。 ミニマルミュージックなんてまったく聴かない、 カツ丼成分を秘めた女の子がある日現れてさ、 すごく魅力的だったりすると人は変わるから。 |
| 白岩 | そうなんですかね。むぅーー。 |
 |
|
| 糸井 | そういうのもありですよね。 |
| 白岩 | そっかー。しかし、小説の話から カツ丼までいくとは思ってなかったな(笑)。 |
| 糸井 | いや、ぼく、小説の話なんて、 たくさんはできないから しょうがないんですよ。 |
| 白岩 | いやいや、それはもう、 ぼくもいっしょです(笑)。 |
| (続きます) | |
| 2009-08-04-TUE | |
 |
 |