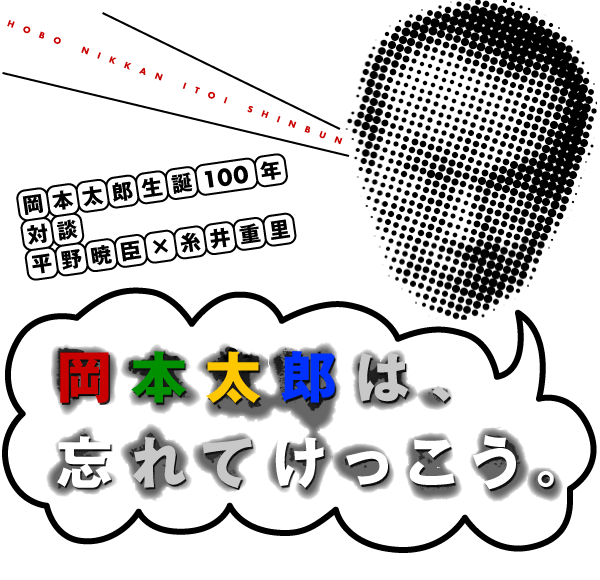
| 糸井 | 学者やえらい芸術家など 「位置」がある人たちのいるところには そのグループの 「山」が築かれています。 マルセル・モースもいれば、 ピカソもいる。 それはそれで、ぜんぶ「山」です。 その山の上で お互いに理解しあう人たちが会う。 そのすばらしさは確かにあります。 だけど、山で言っていることを 町に降りて来て言うと、 人に「はあ?」と言われるわけですよ。 |
| 平野 | ああ、そうかもしれませんね。 |
 |
|
| 糸井 | うん。だけど、もともと山の上でしていた 高尚で高度な話は どうしてはじまったのでしょうか? それは、太郎さんの「発見」した縄文の土器や (岡本太郎さんは1951年頃、 東京国立博物館で縄文土器に出会いました。 太郎さんはその美しさを再評価し、 日本美術史を書き換えたとも言われています) アルタミラの洞窟の絵などです。 それらは「はあ?」と言われないものでした。 そこから、もっといいものをつくろうとして 人は山にのぼっていって 誰にも邪魔されないように、 芸術として、学問として、磨いた。 その山の上で「どっちの人がすごいか」について みんな、興味がないわけじゃない。 だけど、そこでやっていることが はたして町で伝わるのか? それはやっぱり、やってみたくなることでしょう。 |
| 平野 | いわば、実験ですね。 |
| 糸井 | それは、やんなきゃダメですよね。 岡本太郎さんが、塔だの壁画だの、 自分のつくったものの多くを 町に放り投げていったのは そういう気持ちが多分に あったんじゃないかと思います。 そして‥‥存在そのものを 最もさらすことのできる町は、 あのとき、やっぱり テレビだったんだと思うんですよ。 |
| 平野 | うん、なるほど。 |
| 糸井 | 「芸術は爆発だ」って、本気で言ってる台詞が 笑いとともに受け止められる。 それは町の現実でした。 太郎さんはきっと どっちでもよかったんじゃないかなぁ。 |
 |
|
| 平野 | ああ‥‥そうか、 きっとそうだ、 太郎さんは、どっちでもよかったんだ。 いまやっとわかりました。 |
| 糸井 | そうだと思います。 岡本太郎が笑われてたときの太郎さんは、 自分が年取ったせいもあるんだけど、 「いいぞ!」と思います。 考えてみれば、太郎さんの親たちは 大衆芸術作家ですよね。 岡本一平もかの子も 高尚で典雅な芸術をやってたわけじゃない。 それを思うと、 岡本太郎がどうしてあんなに、 顔にこだわったかがわかります。 あれは、漫画のセンスだと思いませんか? |
| 平野 | いや、まったくそうですね。 『森の掟』だって、見方によっては、 あれは漫画ですよ。 絵柄はキャラクターの動物園状態だし(笑)。 近代美術の規範からはほど遠く、 どうひいきめにみても、 上品で上等な美術品とは言いがたい。 60年前にあの絵を見た人の衝撃って、 いまからは想像できないくらい 大きかったと思います。 |
| 糸井 | うん、そうでしょうね。 |
 |
|
| 平野 | 正統的な西洋絵画の作法を拠り所に生きていた 「美術」の世界の人たちは、 ものすごく不愉快だったろうし、 「こんなやつ、認めてなるもんか」 と思ったはずです。 |
| 糸井 | 太郎さんはパリから日本に帰ってきて 居心地が悪かったでしょう。 だから、みんなのびっくりする 漫画のような表現をぶつけることができた、 とも言える。 愉快ですよ。 「真っ裸」になったのは、やっぱり 日本に帰ってきてからなんでしょう? |
| 平野 | そうですね。 パリ時代はいわば「学び」の時期で、 自分の立ち位置をみつけようと試行錯誤していた。 それが、日本に戻って、 日本の文化や美術の状況を見たとたんに 怒りが込み上げてきて、 アドレナリンがドバドバ分泌され(笑)、 いろんなものがギュッとひとつになった。 「オレはこうする、それがオレなんだ」と 腹をくくったわけですね。 「岡本太郎の芯」ができあがった、 というか‥‥。 |
 |
|
| 糸井 | 岡本太郎だけじゃなく、ほんとうはみんなが 自分の裸の歌を持っているはずです。 だけど、自分がどこかで 得たり与えられたりした特定の役割で 生きています。 その「役割の生き方」が たとえ昨日まで役に立ったとしても、 ひとたびすべてを失ったら、 裸の「俺」として生きるしかない。 いろんなことを乗り越えて、ぼくらは そのことに気づかざるを得なくなっていきます。 そのときの「俺」は、 絵は描いてないかもしれない。 でも、太郎の言っていた「芸術」です。 |
| 平野 | 「人生、即、芸術」ですからね。 太郎もそう言えば、 パリから帰ってきて、戦争行って 全部を失いましたから。 |
| (つづきます) |
|
 |