きょうはインタビューについて書いてみたい。
そんな気持ちになったのは、
映画「フロスト×ニクソン」を観たからだ。
アメリカのニクソン大統領は、1974年に
ウォーターゲート事件で辞任に追い込まれた。
メディアはこぞってニクソン元大統領の
インタビューを取ろうとしたが、
彼は誰のインタビューにも応じようとしなかった。
結局、初のインタビューが実現したのは
3年近く後のこと、
しかも、モノにしたのは、
アメリカのジャーナリストではなく、
イギリスのトークショーの司会者だった。
映画では、一発大穴を当てようと
大金を注ぎ込んでインタビューに成功した、
司会者・デビッド・フロスト氏と、
“大統領の犯罪”にもかかわらず特赦で訴追を免れ、
政界復帰を目論むニクソン元大統領の、
人生をかけた闘いを描いている。
まだ観ていない人のためにも
映画の筋立てはこのくらいにするが、
2人の姿はまるでリング上で戦うボクサーのようで、
インタビューというものが持つ面白さが
リアルに描かれている。
インタビューは、最後は“人間力”だと思う。
どれだけ準備し、どういう聞き方をするか、
そうしたテクニックも大事ではあるに違いないが、
それ以上に聞き手の情熱や、心の有りよう、
さらに人としての幅の広さや深さ、
つまり人間力としか言いようのない部分が、
最終的にインタビューの出来を決めるように思える。
インタビュアーの持つ“人間力”をめぐって、
苦い思い出がある。
あれは1998年7月の参議院選挙だった。
バブルの後始末に追われた
橋本内閣の経済政策が問われた選挙で、
自民党は歴史的大敗を喫した。
開票結果の大勢が判明した当日の午後11時すぎ、
橋本首相が開票特番のスタジオと中継を結んで登場した。
いくつかのやり取りのあと、
スタジオの田丸美寿々さんが問いかける。
「責任問題で退陣という声も聞かれますが」
橋本首相は用意していたようにゆっくりと答えた。
「政治家の進退というものは自分で決めるもの。
加藤幹事長にあす役員会を開いてほしいとお願いした」
「なんらかの責任はとられると考えていいですね」
と私が続けた。
橋本首相は顔をしかめて答えた。
「進退は自分で決め、
あしたの役員会で考えを申し上げる」
これらのやりとりを受けて各メディアはいっせいに、
「辞任を示唆」といった内容の速報を打った。
当時このインタビューは、
首相の“クビ”をとったといわれたものだが、
お手柄は、他社に先駆けて最初のインタビューを
お膳立てした政治部にあるのは明らかだった。
この番組はテレビの賞である、ギャラクシー賞を受けた。
選挙番組の受賞は20年ぶりとのことだった。
これには後日談がある。
知人の結婚式に、
主賓として橋本元首相夫妻が出席していた。
私は橋本夫妻が座っているテーブルに
あいさつにうかがった。
橋本首相はこちらを向こうともせず、
代わりに奥さんが私の顔を見て、穏やかな声で、
たしなめるように言った。
「正しい報道をしてくださいね」
橋本氏が首相になる前から、
私があまり歓迎されないインタビューを
してきたからだろう。
会話はそこで終わり、
私は早々にテーブルから立ち去った。
奥さんの一言が耳から離れなかった。
ところが、橋本首相へのインタビューが、
次の選挙での“苦い思い出”につながることになった。
2年後の衆議院選挙、その開票特番の冒頭、
自民党がかなりの敗北をするとの出口調査の数字が出た。
しかし投票が進むにつれて、
それほど負けていないことがわかってきた。
議席数を大幅に減らしたとはいえ、最終的に
与党全体で見れば絶対安定多数を獲得していたのだ。
ところが開票作業と並行して進む番組中には、
最終的にどんな数字になるか、
まだはっきり見えていなかった。
私は明らかに気負っていた。
橋本首相へのインタビューの成功体験が
頭をよぎっていたに違いない。
議席を大幅に減らしそうだ、という一点で、
首相含めて自民党の幹部の責任を問おうとしたのだ。
結果、責任を認めるコメントを
執拗に引き出そうとする質問に終始し、
中味のない浅い“やりとり”になった。
番組のアンカーである筑紫哲也さんが
余裕を持って議論を深めていくそばで、
私は手柄をとろうと躍起になって、空回りしていた。
翌日、局としての番組の総括のひとつが
「キャスターの若さが出た」というものだったと、
幹部のひとりから伝えられた。
私は散々な評価よりも、
私心が紛れ込んだ、自分のあさましさを恥じた。
要するに“人間力”がまったくなっていなかったのだ。
“人間力”が足りずに、
相手を不愉快にさせたインタビューは数知れない。
政党を渡り歩く鳩山邦夫氏に
「節操がないとは思われませんか」と問いかけ、
小沢一郎氏には「なぜあなたの側近たちは、
最後は皆、あなたから離れていくんでしょう」と訊ねた。
そのたび、視聴者からお叱りを受けた。
日常生活では他人の心を乱すことすら恐れるくせに、
インタビューという形式で向かい合うと、
不思議と──それが適切な質問かは別にして──
聞きたいことを聞いてしまうのだ。
少々大げさに言えば、
まるで“インタビューの神様”が降りてきて
背中を押されているような感覚だ。
政治家へのインタビューというのは、
「フロスト×ニクソン」のように、
言いたいことを言おうとする政治家に対して、
言わせたいことを引き出そうとする聞き手という構図が、
普通だろう。
こうしたインタビューは、“インタビューの醍醐味”
という意味では、実はさほど面白いものではない。
個人的な意見だが、
予想もしなかった言葉が出る瞬間こそ、
インタビューの醍醐味ではないかと思う。
それはインタビュアーが予想していなかった
場合だけではない。
ごくまれに、インタビューを受けている人が、
自分でも気づいていなかったことを
口にする瞬間があるのだ。
バレリーナの吉田都さんにインタビューした時のことだ。
吉田都さんは、イギリスの名門、
ロイヤル・バレエ団のプリンシパルだった。
プリンシパルとは主役を踊る、
トップのダンサーのことだ。
彼女の繊細な踊りはそれまでも素晴らしかったのだが、
当時、何かが変わったように思えた。
それは技術ではない、
観客をよりひきつける存在感とでもいうべきものだった。
振付家のピーター・ライト氏は言った。
「都は、以前は観客に
冷たい感じを与えることもあったのですが、
2週間前に見た『ジゼル』で、
彼女は観客を感激させる踊りをしていました」
素人の私だけでなく、吉田都さんを指導し、
見続けてきた一流のプロが同じことを感じていたのだ。
私は意を強くして、「あなたに何が起きたのか」と
都さんに繰り返し訊ねた。
彼女は自分が以前とは違う存在感を
身にまとっていることを意識してなかったが、
訊ねていくうち、「もし、あるとしたら‥‥」と、
彼女の身におきた“ある出来事”を静かに語り始めた。
彼女が心の中を探索しながら、
選んでいく言葉にワクワクしたのを、
今もはっきりと覚えている。
それは、私に“問うこと”の奥深さを
改めて教えてくれたインタビューとなった。
映画「フロスト×ニクソン」を観ながら、
私はさらにふたつのインタビューを思いおこしていた。
それはウォーターゲート事件で人生が大きく変わり、
その後、対照的な人生を歩んだ
ふたりの人物へのインタビューだった。
(続く)

【「ほぼ日」編集部より】
吉田都さんへのインタビューは、
2001年3月の『ぼくは見ておこう』で掲載しています。
吉田都さんに起きた“ある出来事”のことは
そのなかで、書かれていますので、
興味のあるかたは、ぜひ、お読みくださいませ。
|




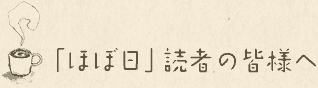
![インタビューの神様 [1] インタビューの神様 [1]](images_new/vol10_title.jpg)
