映画「フロスト×ニクソン」を観ていて思い起こした、
もうひとつのインタビューは、
カール・バーンスタイン氏だ。
きのうのコラムで紹介したコルソン氏が、
ウォーターゲート事件のあと“犯罪者”として
生きることを余儀なくされたのに対して、
バーンスタイン氏の人生はこの事件のおかげで
“栄光”に包まれることになった。
バーンスタイン氏は、ワシントン・ポストの記者時代、
ボブ・ウッドワード記者と一緒に、
ウォーターゲート事件を追及して、
ニクソン大統領を辞任に追い込んだ。
映画「大統領の陰謀」で
ダスティン・ホフマンが演じた記者だと言えば、
イメージがわくだろうか。
彼はこの成功でピューリツァー賞をとるなど、
一躍、スター記者になった。
無名の選手がいきなりヤンキースの4番をうち、
三冠王をとったようなものだ。
それから30年ほどがたった2005年は、
彼らふたりの記者にとって、
ひときわ感慨深いものになった。
ウォーターゲート事件追及の
最大の“ネタもと”である人物が、自ら名乗り出たのだ。
著作や映画「大統領の陰謀」で
“ディープ・スロート”と呼ばれ、
「カネの流れを追え」などと
彼らの取材を誘導した人物だ。
素性を隠すという条件で情報をもらった
“ネタもと(取材源)”をまもり、
それが誰なのかは決して明かしてはならない。
記者にとってイロハにあたるこのルールに従って、
彼らは“ディープ・スロート”をめぐる問いに対して
口をつぐんできた。
犯人探しが繰り返され、
様々な名前が浮かんでは消えたが、
“ディープ・スロート”の素性は謎のままだった。
ところが、2005年の5月、雑誌に
「私がディープ・スロートと呼ばれた男」という
見出しの記事が掲載された。
その中でディープ・スロートは自分だと、
事件当事FBIのナンバー2だったマーク・フェルト氏が
名乗り出たのだ。
(実際には認知症に近い症状だった
フェルト氏に代わって、
家族主導で公表に踏み切ったのだが。)
これによって、
「取材源が死亡するまで明かさない」としていた
ワシントン・ポスト紙もその事実を確認、
ウッドワード、バーンスタイン両記者も声明を発表し、
マーク・フェルト氏が
“ディープ・スロート”であることを初めて認めた。
バーンスタイン氏にインタビューしたのは、
この騒動さめやらぬ同じ年の終わりだった。
若き伝説の記者もすでに61歳、
ホテルに現れたバーンスタイン氏は、
映画で彼の役を演じたダスティン・ホフマンを
横にふた回り大きくしたような体つきになっていた。
「当時、ディープ・スロートが
誰なのかを知っていたのは、
ボブ・ウッドワードと私と、
ベン・ブラッドリー(ワシントン・ポスト編集主幹)の
3人だった。
どうやってディープ・スロートをまもるかについての
明確なルールを決めたわけではない。
大事なのは誰にも言わないことだった。
われわれが賢かったのは、
当時結婚していた妻にも言わなかったことだよ」
そう言って、バーンスタイン氏はにやりと笑った。
「マーク・フェルト氏自身が、
ディープ・スロートは自分だと認めたと、
私は思っていない。
あれは家族と弁護士が公表するのを決めたんだ。
フェルト氏がどこかの時点で、
自分がディープ・スロートだと家族に話したんだろう。
だからウッドワードと私は、最初は同じ反応だった。
フェルト氏本人がわれわれに
許可したわけじゃないので、
我々が認めるわけにはいかない、と」
「しかし実際には雑誌の記事に詳細が書かれていたので、
すでに公表されたと言ってもよかった。
おまけに多くのメディアが
フェルト氏の自宅に集まっていた。
フェルト氏の家族が考え抜いて
公表に踏み切ったのも明らかだった。
我々がこれ以上認めないままにしておくのは、
不誠実だと思われる恐れもあった。
だから、フェルト氏が
“ディープ・スロート”であることを、
本当にいやいや認めたんだ」
捜査機関であるFBIのナンバー2が
“ディープ・スロート”だったことは、
全米に大きな議論を巻き起こした。
フェルト氏は“裏切り者”なのか、
それとも“英雄”なのか。
「彼は国を裏切ってなんかいない。
国を裏切ったのはニクソンだ。
大統領が罪を犯し、合衆国憲法を傷つけた。
フェルト氏は、大統領が国を裏切るのを
止めようとしたんだ」
バーンスタイン氏は、強い調子でフェルト氏を擁護した。
“大統領の犯罪”を暴いた30年前と比べて、
今のメディアの“ありよう”を訊ねる中で、
彼は当時のような調査報道は難しくなっていると話した。
「なぜならアメリカの新聞やテレビ局は、
独立した経営をしていない。
世界的なコングロマリッド企業に所有されている。
たとえばタイムワーナー、バイアコム、ディズニーだ。
彼らは利益を出すことに興味があるが、
真実の追究など大事にしていない。
それに調査報道に取り組んできた新聞を読む人が、
どんどん少なくなっている。
しかも調査報道にはお金がかかる。
新聞社は、調査報道なんかに
金をかけたいとは思わない。
非常に難しい状況だと思う」
このインタビュー当時より、
いまはさらに状況は深刻と言ってもいいだろう。
インターネットに押されて、新聞社の収入は減り続け、
アメリカでは伝統ある地方紙が次々と消えつつある。
インタビューの大半は
“ディープ・スロート”をめぐる騒動や
メディアのあり方をめぐるものだったが、
私が本当に聞きたかったのは、
ウォーターゲート事件が彼の人生にどんな影響を与え、
どんな意味を持ち続けているのか、という点だった。
バーンスタイン氏は16歳で新聞の世界に入った。
アメリカの名門のひとつ、エール大学を卒業した
ウッドワード記者とは対照的に、
バーンスタイン氏は“たたきあげ”の記者だ。
ニクソン大統領が辞任した2年後、
彼はワシントン・ポストを退社、
その後は大学で教えたり、
テレビ局のリポーターをつとめたり、
共著でヨハネ・パウロ2世についての
本を書いたりしている。
だがウォーターゲート事件を足がかりに
“ワシントン村”に深く入り込み、
ノンフィクション作家として
次々と問題作を発表し続けている
ウッドワード記者と比べると、
その仕事ぶりは“散漫”な印象を与える。
要するに、あまりぱっとしないのだ
(あくまで比較の問題だが)。
その分、ウォーターゲート事件は、
彼の中でより大きな意味を持っているかもしれなかった。
「私はボブ(ウッドワード)より、事実が持つ意味合い、
それを推理によって描き出すという記事を書く。
ボブ(ウッドワード)は、
もっと“事実”を積み重ねて
細部をつめていく手法をとるんだ。
つまり、私は事実が意味するものを見つけ出し、
ボブ(ウッドワード)は
より多くの事実を集めようとする。
それらは同じくらい重要なんだ。
ウォーターゲート事件の追及がうまくいったのは、
ふたりのコンビネーションがうまくいったからだ」
「いま、改めてウォーターゲート事件を振り返って、
何を感じますか?」
「もう遠い昔だねえ」
バーンスタイン氏は、
これ以上ないといった笑顔を浮かべた。
「明らかに私の人生の中で、最も輝かしい経験だ。
ウォ−ターゲート事件は、私の人生を変えた。
すばらしい機会を与えてくれた。
ただ記者としてだけでなく、ひとりの人間である私にも
注目が集まるとは思ってもいなかったけどね」
当時、彼らふたりはメディアの寵児となり、
芸能人並みの扱いを受けたという。
「16歳で新聞界に入ったとき、
地方記事の編集責任者になりたかった、
それが目的だったんだ。
しかしそうはならず、別のことが起きた。
素晴らしい機会が訪れた。
本当に素晴らしい出来事だった。
ジャーナリストとは何ものか、
何が出来て何が出来ないのかを知る
偉大な機会だったんだ」
バーンスタイン氏は、目を細めて続けた。
「それに、すごく楽しかった。
16歳のころ、記者になることは、
人生で最も楽しいことのように思えた。
そして実際、そうだった」
バーンスタイン氏は、インタビューの間中、
大きな体を小刻みに動かし、
水を何度も何度も口に運んだ。
だがウォーターゲート事件当時の話をしている時だけは、
穏やかで落ちついた様子に見えた。
彼は、またいつでも遠慮なく電話してくれ、
と言い残して部屋をあとにした。
このインタビュー自体に、
何か目新しい事実があったわけではない。
ただ伝説の記者だった彼が、どんな佇まいをして、
いまどんなことを考えて生きているのか、
彼の持つ何かを感じるとことはできたように思う。
人生の中のわずか2時間、向きあうだけだとしても、
その人物のそれまでの人生を垣間見ることはできるのだ。
「一瞬の中にも人生の奥行きは宿る」と、
“インタビューの神様”は教えてくれる。
バーンスタイン氏へのインタビューから3年後、
マーク・フェルト氏は95歳で死亡、
“ディープ・スロート”をめぐる長き物語は、完結した。
(終わり) |




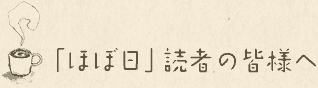
![インタビューの神様 [3] インタビューの神様 [3]](images_new/vol12_title.jpg)