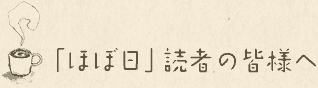裁判長が死刑判決を言い渡すときの
心情とはどのようなものなのか。
1998年、東京地方裁判所の
山室恵(やまむろめぐみ)裁判長(当時)は
オウム真理教の岡崎一明(かずあき)被告に
死刑判決を言い渡した。
岡崎被告は、
坂本弁護士一家殺害事件などで
殺人罪に問われていた。
「岡崎被告に死刑を言い渡した瞬間を
覚えていますか?」
「覚えています」
山室さんにとって
死刑判決を下すのは初めての経験だった。
「どういう心境だったですか?」
「まだ陪席
(法廷で裁判長の横に座っている裁判官)の時代に
裁判長が死刑を言い渡す瞬間を
横で立ち会っているんですよ。
視野に入るんです。裁判長の表情が。
言う瞬間も耳で聞こえてますから。
吐き捨てるように『被告人を死刑に処す』と。
それが非常に印象に残っていまして。
自分も『ああいうふうに
吐き捨てるように言い渡すのかな』
と思ってみたり。
名俳優なら全部自分をコントロールして
演じられるかもしれないけど
さすがに自分の口で
被告人に死刑を言うときは
演ずるという、
そういうところじゃないなと」
「感情というのはこめるものですか?
あるいは、こもるものですか?」と私は訊ねた。
「こめない」
と山室さんはすぐに答えた。
「できるだけ機械的にというとあれだけど‥‥」
5ヶ月前に出した林郁夫被告への判決が
“無期懲役”だったのに対して、
山室裁判長は、岡崎被告には“死刑”を選択した。
その差をジェットコースターに例えた人もいるという。
山室裁判長は、
林被告には自首を認めて
刑を軽くした一方で、
岡崎被告には自首は認めたものの
刑を軽くはしなかった。
「判決のひとつの核になる理由ですけど、
岡崎の場合は、
かなりのずる賢さというか、
つまり口先の反省というのが強く疑われる。
自首は認められるけど、
自首減刑はしない。つまり死刑のままだと」
「死刑と無期懲役といっても
全然重さが違いますよね」
「ここはクリアカットじゃないんですね」
こう言って山室さんはしばらく考え込んだ。
「どっちに転んでもおかしくない裁判も?」
「あります」
山室さんは、1999年、
ある事件で無期懲役の判決を下した。
暴行の被害を警察に届けた女性を逆恨みし、
刑務所から出たあと
この女性を殺害した男に対する判決だった。
山室さんは自分なりの判断で
あえて死刑を選択しなかった。
ところが、東京高裁は
山室さんの無期懲役の判決を破棄し、
一転して、死刑を言い渡したのだ。
山室さんは言う。
「不思議な感覚ですけど、
逆じゃなくてよかったな、と。
自分が死刑で、高裁が無期懲役じゃなくて
よかったな、と。
この方が精神的にはきついなと思いました。
理窟ではないですけどね」
すべての裁判官が
裁判官人生の中で
死刑判決を経験するとは限らない。
一度も死刑判決を下すことなく
退官していく裁判長もいるのだ。
「気持ちの上では死刑はないほうがいいですよ。
嫌ですもん。刑事裁判官やっていて
これさえなければなあ、と言った人がいたそうですし、
『死刑がなければなあ』って」
2時間ほどのインタビューの中で
山室さんが何度か立ち返る言葉があった。
それは“孤独”という言葉だった。
地方裁判所の刑事事件の多くは
裁判長と2人の裁判官の
あわせて3人で合議して判決を決める。
だが裁判長の責任が圧倒的に重いという。
3人で話していても
他の2人の裁判官はついてきていない、と
感じることがあるという。
「裁判長というのは、最終的に
たとえば“山室判決”と言われますし、
歴史上大きな裁判には
どれも裁判長の名前がつくように、
一番責任が重いのが裁判長なんですね。
事件の情報は共有できますけど、
考えて詰めて詰めるという段階になると
『あ、自分だけ独り歩きしている』という
感覚がしました。
孤独なもんだなあ‥‥と」
家族や友人に相談するわけにもいかない。
最後に頼れるのは自分自身だけだという。
「孤独ですね」と私が繰り返すと、
山室さんは「だから酒、飲むんですよ」
と笑いながら言った。
「飲まれる方、多いですか?」
「多いですね。本当に多いですね」と
山室さんは繰り返した。
裁判長時代は
重圧を背負い続ける日々だったという。
「やっぱり人様の運命を決定的に決めますからね。
人の人生変えますからね。
究極は『あんた死ね』って言いますからね。」
山室さんはそう言って
自分に言い聞かせるかのようにつぶやいた。
「ええ‥‥なかなか‥‥‥‥」
山室さんの頬を
一筋の涙がつたって落ちる。
私は息をのんで、その表情を見つめた。
インタビューとは不思議なものだ。
当然のことだが
聞き手がいて、答える相手がいる。
時に聞き手が主導して
何かを引き出すインタビューもあるだろう。
ところが山室さんへのインタビューの中で
私は初めての感覚を味わうことになった。
私は自分の意思ではなく
まるで山室さんに導かれるかのように
問いを発していた。
そして山室さんは自分自身と向き合い、
自分自身と対話を重ねていた。
裁判官は神ではない。
本当は誰もがわかっていることだが
それを語りだした裁判官が
これまでいただろうか。
なぜ山室さんはタブーとも言える領域を
踏み越えることができたのだろうか。
「実はわたし、がんになりかかったんですよ。
ある数値が、腫瘍マーカーが基準値を超えて
精密検査をしたんですよ。
結論的には嫌疑不十分で
がん細胞は見つからなかった。
でもここで相当、
ガツンときたものがありましたね。
自分の死が具体的になってきているんだという。
それがきっかけで
ブレーキをかけて、
あれはやめておこうというような思いは
捨てようと。
それが、こうして話していることと
つながっています。
間違いなく自分の気持ちとつながっています」
「裁判長時代は、
演じなければならなかったですか、
神であることを?」
と私は訊ねてみた。
「ええ、それは演じてきましたよ。
『実はな』って、なかなか言いませんもん」
山室さんは穏やかな表情で言った。
山室さんは、さだまさしの曲、
『風に立つライオン』の一節が
好きだという。
それはこんな歌詞だ。
『この偉大な自然の中で病いと向かい合えば
神様について ヒトについて 考えるものですね』
山室さんは言う。
「裁判官が、死刑か無期懲役か
という事件に向かう時には
あるいは死刑しかないという判断をする時には
神様について、人について考えざるをえないんです」
(終わり)
|