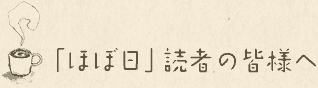この夏、多くの場所に足を運んだ。
たいていは金曜の放送を終えて、
少々の睡眠をとり、朝一番に出かける。
放送のない週末が唯一、
私にとって遠出が許される2日間なのだ。
参議院選挙の選挙区取材や、沖縄の基地問題、
原爆から65年がたつ広島など、
出張の目的は様々だった。
その中でも、自分にとって特に印象深い場所があった。
それは御巣鷹の尾根だった。
本当に久しぶりに登った
という理由だけではない。
一緒に登った相手が、
私にとって特別な意味を持つ人だったのだ。
日航ジャンボ機墜落事故から25年を前にした、
ある日曜日の午前。
群馬県上野村にある「御巣鷹の尾根」登山口で、
美谷島邦子さんと待ち合わせをした。
美谷島さんについては、去年3月に
このコラムで書いたことがある
事故の遺族がつくる『8・12連絡会』の事務局長だ。
25年前の事故当時、
駆け出しの記者だった私は遺族担当となり、
美谷島さんを取材した。
運ばれてくる多くの遺体の中で、
右往左往し立ち尽くすばかりの日々だった。
いや、私など比べものにならないくらい
美谷島さんは壮絶な時間を過ごしていた。
初めてのひとり旅に出た
9歳になる息子を亡くした悲しみ。
彼女はいてもたってもいられなくなり、
御巣鷹の尾根の道なき道を登った。
それからほとんど形も残らない部分遺体を捜す日々。
さらにひとりの主婦だった彼女が、
遺族の会の事務局長となり、
他の遺族たちの相談役まで引き受けていた。
その1年間、私は毎日のように美谷島さんと連絡をとり、
彼らの声を伝える仕事をした。
その過程ではいろいろな迷惑をかけた。
多くは私が記者として未熟だったことが原因にしても、
おそらくこの仕事が根源的に持つ無礼さが、
そこにはあったに違いない。
彼女はひとりの母親としては拒否したい取材も、
時に遺族の会の事務局長として、き然と受け入れた。
私にとっては記者としての原点とでも
いうべき仕事となった。
それから25年。
折に触れ連絡をとりあい、
節目では直接会って言葉を交わした。
その美谷島さんとふたりで
御巣鷹の尾根に登る約束をしたのだ。
一緒に登ったことがないわけではない。
だがたいていの場合、
他の遺族の方や取材陣も同行していた。
私が担当する番組のディレクターやカメラマンが
その様子を追っていたとはいえ、
ふたりで登るのは初めてだったのだ。
午前10時半すぎ、登山口に姿を見せた美谷島さんは、
ごく軽装だった。それは登山道が整備されて、
いかに御巣鷹の尾根への歩みが
楽になったかを示していた。
「いい天気ね」
と美谷島さんが空を見上げて言う。
青い空が山を覆っていた。
登山口には、たくさんの杖が置かれていた。
それは遺族が高齢化してきたことを物語る。
使ったらそこに戻す。
一本一本には空の安全への願いが書き込まれている。
美谷島さんはその中から一本を取り出して握りしめた。
並んでゆっくりと登り始める。
木々が揺れて、せせらぎの音が聞こえる。
都会のコンクリートの中にいるより、
はるかに涼しく思えた。
「美谷島さん、登るのは何度目ですか」
私は何の気もなしに訊ねた。
「147回。きょうで148回目かな」
「きょうで148回目ですか」
驚いて私は繰り返した。
この25年間、すでに147回も登っていたのだ。
「途中まで数えていて、
あとはひっくり返して見直したら
それくらいなっていたの」
美谷島さんはあたりを見渡しながらつぶやく。
「この辺りは御巣鷹らしいなあって感じるの。
あ、鳴いてる、鳴いてる」
あたりに響く鳥の鳴き声に、彼女は耳をすませた。
登山道は、急なところは登りやすいよう
段になっていて、手すりも備えつけられていた。
「はじめて登ったのは、事故から3日目ですよね」
「そう8月15日ね」
「その時はどのくらいかかったんですか?」
「4時間ちょっとかな。まだ登山道がなかったので、
機動隊とかの足跡を頼りにね」
彼女は足元を眺めながら続ける。
「1年目は下ばかり見て、登ってた気がする。
季節の変わり目、
ひとつきに1回くらいは登っていた。
カサコソ、カサコソ、落ち葉の上に
涙を落としながら登っていたわね」
途中の道端のお地蔵さんを見て、足を止める。
「この地蔵は去年、なかった、誰か作ったのかな。
ここに来るたび、新しいものがあるのよ」
事故直後は4時間ほどかかったという登山も、
今ではほぼ30分で尾根にたどり着くことができる。
その半分ほど来たころだろうか。
他の登山者とすれ違う。
その家族は美谷島さんの顔を見て、声をあげた。
「やだ、びっくりした」
遺族だった。
美谷島さんと彼らは簡単に近況を報告しあって、別れた。
登るたび、他の遺族の方々と顔を合わせるという。
「この事故、本当に遺族が全国各地にいるから、
ことあるごとにいらしてるんだと思います」
最近は新しい世代の姿が目立っているという。
「感心するのは、そうやって家族の中で
きちんとこの事故を、お父さんの死とか、
家族の死を伝えているから、
この山をいろんな人が登っているんだなって」
こうした取材では、
この辺りでこうしたことを相手に聞こう、
といった段取りを
前もって自分の中で組み立てるものだ。
もちろん実際にその通りに行くことは
ほとんどないのだが、
事前にディレクターと打ち合わせをしておく。
だがこの時ばかりは、
そうした段取りは考えなかった。
ディレクターがそう促してくれていたからでもあったが、
頭の中を真っ白にしてただ一緒に登ればいいと
自分でも自然に思えたからだった。
しばらく歩き続けると、視界が開け、
昇魂之碑が目に入った。
自分の記憶にある風景より、とても小さく思えた。
もっとだだっ広い風景のような気がしていた。
長き時間の中で、木々が以前に増して
山を覆ったこともあるのだろう。
あるいは事故の衝撃の大きさが、自分の中で
風景を変容させていたのかもしれなかった。
昇魂之碑に水をかけ、花を手向けて、手を合わせた。
降り注ぐ夏の日差しの中で、
鳥たちの鳴き声だけが耳に入ってくる。
山はしんとしていた。
細い道をのぼると、
すべての犠牲者の名前が刻まれた碑があった。
同じ苗字も並んでいる。
私が指でなぞると、
美谷島さんが後ろからつぶやいた。
「同じ家族がというのも多いから。
8人亡くなったという家族が一番多くて、
22家族が一家全員亡くなったの。
いっぺんにですからね‥‥」
そこからもうしばらく歩くと、
事故で亡くなった美谷島さんの当時9歳の息子、
健ちゃんの墓標が見えてくる。
健ちゃんの部分遺体が見つかった場所だ。
そこには、それまで見た墓標とは
まったく別の風景が広がっていた。
(8/19更新の[2]へ続く)
|