| インタビューを始める前に 自宅の奥から咳払いをする音が 何度も聞こえてきた。 もしかしたら 声が出にくくなっているのかもしれない。 無理もない。 すでに90歳を迎えているのだ。 ところがそれはまったくの杞憂だった。 京都の嵯峨野を訪ねた私を 瀬戸内寂聴さんは テレビで見慣れた笑顔で迎えてくれた。 それどころか 少々風邪気味だった私のほうが 声が出なくなり インタビューの最初の質問を 発することができないと見てとるや 「かりん酒を持ってきて」と秘書に命じ たちどころに 私の声を出るようにしてくれたほどだった。 私はその日、来年1月に放送する 筑紫哲也さんのドキュメンタリーの インタビュアーとして 庭に置かれた椅子に座って問いかけ、 紫の衣を身にまとった寂聴さんが、 感情を追いかけるように言葉を発した。 寂聴さんに話を聞けるチャンスなど めったにあるものではない。 彼女の主だった小説と 雑誌『the寂聴』の愛読者でもある私は どうしても訊いてみたかった質問を 最後にぶつけてみた。 「どうして寂聴さんは こんなに長く書き続けられたんでしょう?」 寂聴さんは少し考えたあと 怒ったような顔をこしらえて言った。 「30年も賞をもらえなくて こんちくしょうって思ってたからかな」  寂聴さんは、 代表作のひとつ『夏の終り』で 1963年に女流文学賞を受賞、 その後、芥川賞や直木賞をもらうこともなく 29年待たされ続けた。 29年と一口で言ってもピンと来ないが 女流文学賞が41歳、 次に賞をもらったのが70歳と言えば 『待たされた』と 言ってみたくなる気持ちも わかるというものだ。 「もういらないと思って 次の賞が来ても断るつもりだった。 『断りの弁』まで用意して 風呂につかりながら 声を出して読んだりしてたの。 でも谷崎潤一郎賞の電話が 滞在していた ポルトガルのホテルにかかってきて 「受けていただけますか?」と訊かれたら 『断りの弁』もすっかり忘れて よろしくお願いします、って言っちゃった。 やっぱり、もらえるものは もらっておいたほうがいいもの」 寂聴さんは 茶目っ気たっぷりの笑顔を浮かべた。 「でも書き続けられたのは、 本当は書くのが好きだったから。 2枚でも3枚でもちゃんと書けたときは 『やったあ』と喜んで、 ひとりで飲んだりするの。 この楽しさは他のものでは味わえないわ」 この言葉通り 賞などおかまいなしに 寂聴さんは作品を量産し続けた。 「賞はもらえなくても、 注文が来たから書けたのよね。 でも『源氏物語』が売れたから いまこうして一息つけてる。 それまでも貧乏してたわけじゃないけど とっても大変だった」  インタビューを終えたあと 自分も去年、 小説を出したことをこわごわ告げると (今も冷や汗が出るが) 寂聴さんの瞳がきらりと輝き 身を乗り出した。 「え、どうしてそれを早く言わなかったの。 じゃあ、小説の話をもっとしましょう」 それから彼女は 書くことへの思いを語り始めた。 (続く) |
| 2012-12-25-TUE |
| とってもご無沙汰しております。 きょうは人生の大先輩、 90歳にして人一倍、 好奇心旺盛な女性のお話です。 |


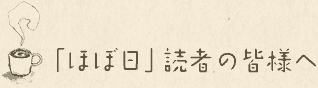
![90歳の青春[1]](images_new/20121225_title.jpg)