| インタビューを終えたあと 『寂庵』の敷地にあるお宅に場所を移して さらに寂聴さんのお話をうかがった。 というより、 まずは寂聴さんから矢継ぎ早の質問。 「どうして小説を書いたの?」 「どんな話なの?」 「書いてて楽しかった?」 「次も書いてるの?」 「どんな作品?」 たんなる想像にすぎないのだが 90歳にもなると 人は次第に、他人への好奇心を失っていき 「この人はこんな人だ」と それまでの経験をもとに カテゴライズしていくものじゃないかと思う。 でも接した限り、寂聴さんに そんな気配はいっさい感じられない。 それどころか 初めて会う人間への溢れる好奇心を 隠そうともしなかった。 寂聴さんを前にして 訊きたいのは私のほうだ。 途中から形勢を逆転させようと 私が質問を繰り出すと 思いつくまま様々な話をしてくれた。  「純文学は食べていけない。 だからみんな先生やってる。 私は人に教えるのが好きだから いい先生になると思った。 そうしたら書けなくなる。 だからやらなかった」 「小説を書く前に プロットを書いたりするんですか?」 「そんなもの書かない。 登場人物が勝手に動き出したら こっちのものよ」 何より驚いたのは いまも一日中、 書いているということだった。 数時間ではない。 可能な限り、 原稿用紙に向かっているということだった。 「インタビューとか、講演とか 書くために、できるだけ断るようにしてるの」 「若いころは、(400字詰めの原稿用紙) 1日30枚とか平気で書けた。 50枚書いたこともある。 今年の夏に、一歩も外に出ないで 清少納言を書いていたんだけど これが大変だった。 初めて体力の衰えを感じたわ」 「えっ?90歳になられて初めてですか?」 私が声をあげると 「そうよ」と言って 寂聴さんは、にんまりと笑った。 「このところ、いつも これが最後の長編という気持ちで書いてる。 でも出版社から 「瀬戸内寂聴、最後の長編」と 広告にうっていいかと聞かれると ちょっと待って、まだ書くわ、と 答えちゃうのよ」 そう言って、寂聴さんは 今度は、顔をくしゃくしゃにして笑う。 そうかと思えば、真顔で言い放つ。 「小説は熱よ、文章に出るわ。 そして小説は才能よ。 才能がない人がどれだけ努力してもダメよ」 そこまで言って、 私の顔を見据えて続けた。 「自信を持って書き続けなさい。 いい、書くことは死ぬまでできるわよ」  このあと、過去から今に至る 何人もの作家にまつわるエピソードに 耳を傾けながら、 寂聴さんの放つ なんともいえない“色気”を感じていた。 90歳の人と向き合う場面を想像してほしい。 どこか過去からの声に耳を澄ますような 構えになるのではないだろうか。 しかも仏門に入った人から 話をうかがうとなるとなおさらだ。 ところが寂聴さんは 俗世にも深く片足を残したまま 女性としての色気も枯らさず、 同時に、壮絶な人生のあと髪を剃り、 仏の教えも身につけている。 それでいて、 人を大いに油断させる笑顔で 自らをさらけ出し 老若男女かまわず 目線の高さを合わせて語りかければ 私でなくともイチコロになるだろう。 帰りの新幹線で、 寂聴さんの幅広い交友を描いた 『奇縁まんだら』を 時間を忘れて読みふけった。 島崎藤村や川端康成、三島由紀夫といった 歴史上の作家たちと向き合うかと思えば、 今の若者に向けて携帯小説まで発表する。 熟成と若さが同居する90歳は きょうも机に向かっている。 (終わり) |
| 2012-12-26-WED |
| きのうに引き続き 90歳にして人一倍、好奇心旺盛な 瀬戸内寂聴さんのお話です。 |


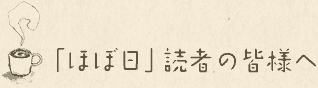
![90歳の青春[2]](images_new/20121226_title.jpg)