100万人が虐殺されるという事件が
半世紀前に起きていたとすると、
虐殺した側の人間たち、
つまり加害の側にいる人たちは
いまどうしていると思いますか。
そう尋ねられたら、あなたはどう答えるだろう。
たぶん、きちんと裁かれて
その事件は歴史のひとつになってしまっている。
そうあってほしいと願うのではないだろうか。
ところがインドネシアではそうはならなかった。
それどころか、いまも加害の側が
権力を握っているため、
虐殺に触れることすらタブーになっている。
そこに光をあてたのが、アメリカ人の
ジョシュア・オッペンハイマー監督だ。
彼はハーバード大学と、ロンドン芸術大学で
映画製作を学び、
短編のドキュメンタリーを発表する。
グローバリゼーションをテーマとした
映画を作るために滞在したインドネシアで
かつて虐殺があったことを知る。
しかも、今もそのことを
誰も語ることすらできないという現状を。
そこで彼は、加害の側に
どう人々を殺したかを語らせる。
ふつう語るのは被害者であり、
加害者は固く口を閉ざすものだ。
だがインドネシアでは
権力側にいる加害者たちにとって
虐殺は“正義”の行為にあたるため
それは武勇伝にもなるのだ。
それがオッペンハイマー監督、
初の長編となった『アクト・オブ・キリング』だ。
去年、この映画を初めて観たとき、
強い衝撃と受けるとともに
なんともいえない後味の悪さばかりが
残っていたのを覚えている。
加害の側が、どうやって
同じ国の仲間たちを殺したのかを
身振り手振りもまじえて
誇らしげに語っていたからだ。
兄を殺されたインドネシア人のアディは
そのオッペンハイマー監督と出会い
ひとつの提案をする。
自分が兄を殺した人々に会いに行くので
それを映画にしないかと。
これが最新作の『ルック・オブ・サイレンス』の
全ての始まりだった。
この提案をオッペンハイマー監督は、
どう受け止めたのだろうか。
来日した彼に聞いてみた。
「無理だと言いました。危険すぎると」
彼はすぐさまそう答えた。
「ノンフィクション映画史上、
加害者が依然、権力を握っている状態で、
被害者が加害者と向き合うという映画は
ありませんでした。
危険すぎるからです。
だからインドネシアでも
そんなこと、想像できませんでした。
でもその後、アディが
加害者と会うことが、彼にとって
どれだけ大事なのかを説明してくれました。
アディは心を開き、優しく話すことで
加害者たちが犯したことを認識し、
謝ってくれることを願っていました。
それによってアディは
加害者たちを許すことができる。
そうして初めて
彼と加害者たちは、同じ近所の住民として
和解と平安をえることができると」
インドネシアでは殺した側と、
殺された家族たちが、
近隣の住民としてともに暮らしている。
殺された側は、沈黙を続け
アディの言葉でいう
“恐怖という名の監獄”に閉じ込められている。
アディはこの見えない監獄から
子どもたちを解放してあげたいと願ったのだ。
映画では、
アディが加害者たちと会いにいく、
息詰まるようなシーンが続く。
シナリオがあるドラマではない。
何が起きるかわからない。
その場面をカメラがひたすら記録していくのだ。
静かに、表情すら変えずに
加害の側と向き合うアディに対して、
相手はときに不愉快な顔になり
ときに感情的になり、ときに脅しの言葉を吐く。
アディと向き合った地方議会の議長は言う。
「あの大虐殺は自然に起きた。
共産主義者たちは嫌われていた。
私は正しい歴史を残したいだけだ。
あれは大きな犯罪とは思っていない」
虐殺の対象となったのは、
共産主義者、あるいは
そのレッテルをはられた人々だった。
アディは問う。
「100万人以上が殺されたんですよ」
「それが政治だ。
政治とは理想を実現するプロセスであり、
その方法は様々だ」
そしてこう言い放つ。
「またあのような虐殺が起こることを
望んでいるのか?
過去のことを騒ぎたてれば
ふたたび同じことが起きる。
遅かれ早かれ、また起きる」
この脅しを目の前で聞いていた
オッペンハイマー監督はこう語った。
「残念でしたし、正直言って、怖かったです。
撮影が始まった瞬間から、
アディと家族に危険が及ばないよう、
ずっと努力してきましたが、
それでも、こういう言葉を聞くと、
本当に怖かったです」
恐しくなったのは、脅しの文句だけが
理由ではない。
インドネシアの学校では
虐殺が起きたのは
殺された側が悪かったからであり
罰を受けただけだ、と教えられている。
つまり、あれは正義の行為だったのだと。
そうした洗脳によって
虐殺がふたたび起きる土壌が
つくられていると
オッペンハイマー監督は考えている。
映画の上映は、インドネシアにとって
“事件”といってもいいほど大きな出来事になった。
若者を中心に絶賛する声があると思えば、
脅しによって上映が中止になったところもあった。
当局による検閲も入り
大規模な映画館での上映が禁止されたという。
映画を観て、改めて感じるのは
人間は人間を殺すことができる
生き物だということだ。
インドネシアでは、
共産主義者は殺すべき存在だと
信じ込まされた結果、起きた。
たとえば、今から20年前に起きた
ルワンダ虐殺では、
加害の側が、被害の側の民族を
あいつらは「コックローチ(ゴキブリ)」だと叫んで
非人間化、つまり
人間ではないのだから殺してもいい、
という考えを醸成していく。
それがひとつの引き金になって
50万人から100万人が殺されたのだ。
「なぜ人は集団で行動すると、
人間とは思えないようなことまで
出来てしまうのだと思いますか?」
そう尋ねると、
彼は自分がこの問いにきちんと答えられるとは
思わないが、と述べたうえで、こう指摘した。
「とても大事なことだと思うのは、
人間は、グループ全体が何かをやっていると、
個人的な道徳観と正反対のことでも、
それが正しいと感じてしまうことです。
権力者のお墨付きがある場合は特に。
このようなことが起きないようにするには、
小さいころから、批判的に考えること、
権力者に対し疑問を持つことを教えこむことです。
それなのにたいていの学校では、
権力者に対し疑問を持つどころか、
従うよう教えています」
さらにオッペンハイマーは続けた。
「集団としての道徳観が、
道徳的であることはきわめてまれです。
個人レベルでの道徳観が、
人間として最も美しく、深いのです。
だから、みな権力者が言うことは聞かず、
自分の心の声に耳を向けることが重要なのです」
インタビューの最後に
どうしても聞いておきたいことがあった。
彼はユダヤ人で、彼自身も親族を
ホロコーストという名の虐殺で
亡くしているのだ。
「ナチスによるホロコーストで
親族を失ったルーツは
こうした映画をつくるのに
影響を及ぼしたと思いますか」
オッペンハイマー監督は肯いた。
「おそらく大きな影響を受けていると思います。
私は、幼いころから、こう聞かされて育ちました。
全ての政治、あるいは全ての芸術は、
ホロコーストのような犯罪が
二度と起きないようにすることを
目指すべきだと」
インドネシアという異国の地に何年も住んで
ドキュメンタリーを撮り続ける。
経済的にも、精神的にも大変な作業に耐えられたのは
子どものころからのそんな思いが
彼の中に根付いていたからなのだろう。
加害と被害が向き合う。
そこに現れるのは人間の本性だ。
オッペンハイマー監督は言う。
「この映画を知らない社会への窓と
とらえて欲しくありません。
この映画はあなたを映しだす鏡なのです」
(終わり) |


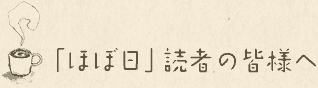
![ふたりの監督[2]](images_new/20150629_title.gif)