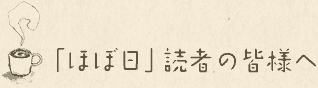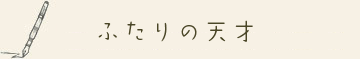ふたりはいつも対照的に見えた。
片や高校野球のスターでドラフトも1位で入団、
一方はドラフト4位でプロ野球の世界に滑り込んだ。
片やパワーヒッターで、もうひとりは技巧派、
身体もひとりががっちりした筋肉質に対して、
もう一方はしなるような細身だった。
醸し出す人物像も、対照的と言っていい。
片や温厚ではにかんだような笑顔を見せ、
もうひとりはどちらかと言うと気難しく見えた。
少なくとも気軽に声をかけるのを
一瞬、躊躇してしまう雰囲気をまとっていた。
そして、海を渡ったあとも
ひとりは大リーグ屈指の名門球団、
もうひとりは1970年代にできた
新興チームに入団するというコントラストを見せた。
2004年のことだ。
ロッカールームで目にしたふたりも実に対照的だった。
日本では考えられないことだが、
大リーグでは、選手のロッカールームにまで
記者の出入りが許されている。
最初は信じられない思いがした。
さっきまでグランドでプレーしていた選手が
シャワーを浴びて素っ裸で身体を拭いたり、
着替えたりしているのだ。
そんなプライベートな空間に
記者を入れない日本のほうが自然にも思えるが
観客がいてこそ成立するプロの球団としては
記事を書いてもらってなんぼといった割り切りが
伝統としてあるのかもしれない。
もちろんそこにはおのずと暗黙のルールが存在する。
できるだけ選手の邪魔はしないとか、
疲れている選手に配慮しながら
間合いを見て話しかける、といった具合だ。
ニューヨーク・ヤンキースの松井秀喜に
そうした配慮は必要なかった。
試合のあとに必ずカメラの前に立ったのだ。
記者たちからすれば、
ロッカールームで無理に話しかけなくとも
待っていれば必ず話を聞くことができる。
それも、ヒットを打てず、
不振に喘いでいるとき時でも
松井は記者の取材を受けたのだ。
それは時に痛々しくも見えた。
質問するほうも重苦しいし、松井も言葉を探した。
それでも表情を変えなかった。
苦行僧のような松井のそうした姿勢を
アメリカの記者が感心した面持ちで
見ていたのを覚えている。
もちろん日本から大勢来ている「松井番」記者への
サービスであると同時に、
松井の自らに課したルールでもあったのだろう。
忘れられない光景がある。
2006年5月のことだ。
レフトを守っていた松井は
浅いフライを取ろうと、仰向けの姿勢で滑り込んだ。
ところが伸ばしたグラブが芝生にひっかかって、
左手の手首を骨折してしまう。
そのまま病院に向かい、
長期離脱がはっきりした段階で、松井は声明を出す。
ファンに戦線離脱を謝罪する内容だった。
この声明に対して大きな反響が沸き起こるとは
松井も想像していなかったに違いない。
アメリカ人は驚いたのだ。
全力でプレーしてその結果、怪我をした、
どうして謝る必要があるだろう。
最初はそうした反応一色だった声明は
じきに称賛の対象へと変わっていった。
謙虚さ、ファンの立場に立った言葉に
日本人の美意識を見る論調もあった。
何より、普段の松井の佇まいと
ぴったり重なって見えたのだと思う。
そんな松井より2年ほど前に
イチローはシアトル・マリナーズに移籍、
私がアメリカに赴任したときには
すでに輝かしい成績をあげて、その実力を証明していた。
遠征でニューヨークに来たときに
やはりロッカールームをのぞいてみた。
それは松井の居た空間とはまるで異なるものだった。
一言でいうと、
ピリピリした雰囲気が漂っていた。
日本人の記者たちが、こわごわといった感じで
イチローを遠まきに見つめていた。
イチローがシャワーを浴びたあと
バスタオルを腰に巻いて椅子に座る。
それが合図だったのだろうか。
スポーツ記者たちがイチローに近づき
輪を少しずつ小さくするように、周りを囲む。
質問もこわごわといった感じだ。
どんな質問だったか覚えていないが
ひとりの記者が質問した時だ。
イチローは顔を上げて、その記者を一瞥したあと
突き放すようにこう言ったのだ。
「答える価値なし、はい次」
しばらく沈黙が流れたあと
勇気ある記者が次の質問を繰り出した。
イチローの大リーグ行きが決まる前の年だったと思う。
東京は四谷にほど近い飲み屋街を歩いているとき、
だしぬけに後ろから声が聞こえた。
「松原さんだ」
振り返ると、そこにイチローが立っていた。
驚いたのなんのって。
イチローが目の前にいることだけでも驚きなのに、
私の名前を口にしたのもイチローだったのだ。
でもそばにいる女性を見て察した。
妻となって間もない女性が、
イチローより半歩下がったところで微笑んでいる。
彼女は少し前まで
私が当時、キャスターをしていたニュース番組で
スポーツコーナーを担当していたのだ。
妻となる女性を観るため
番組にチャンネルを合わせていたため
私のことも記憶のどこかにひっかかっていたのだろう。
そのころ、私は手帳にびっしり書き込むほど
イチローの言葉に魅せられていた。
哲学的ともいえるその言葉に奥行きの深さから
イチローがどれだけ自分に課題を与え
それを乗り越えようとしてきたかを知った。
引退の会見でも、他人より頑張ったとは言えない、
自分なりの頑張りを重ねてきただけだ、
といった趣旨のことを話していたと思うけれど、
まさにその一歩、一歩を、私も同時代で
感じようとしていたのかもしれない。
だからロッカールームで見た風景も
私にはさほど違和感なく心に収めることができた。
もしそうした記憶がなければ、
ただの傲慢な選手に映っていたかもしれない。
でもそうは感じなかった。
質問をパスされたスポーツ記者に対して
同じ記者として少々酷だとは思いながらも、
常に高い目標を掲げ、
それを超えてようとしてきたイチロー選手が
記者にもプロフェッショナルな姿勢を求めているのは、
ひとつの流儀として自然なことのようにも思えた。
ロッカールームでは対照的なふたりに
共通することがひとつある。
それは野球が大好きな、
言い方を変えれば、野球にうるさいアメリカの観客が
ふたりに最大限の敬意を示していたことだ。
日本のようにラッパを吹いたり、
掛け声に合わせてそろって応援したりする習慣は
アメリカの球場にはない。
ひとりひとりが、思い思いの応援の仕方をする。
だからこそ、どれだけの敬意を抱いているのか。
選手によって一目瞭然なのだ。
子どもたちがイチローを見るとき、
どれだけキラキラした瞳をしているか。
松井が打席にたったとき
どれだけファンが息を呑んでヒットを待っているか。
そしてアメリカ人の父と子が
そろって55番のユニフォームをつけて歩いているのを見て
なんだかうれしくて、不覚にも涙したこともある。
松井が引退してから6年余り、
イチローも選手を退くことを会見で発表した。
あまりに対照的だったふたりの天才。
彼らがそろってアメリカで活躍した時代に
その土地で立ち会えたことが
奇跡のようにすら感じられるのだ。 |