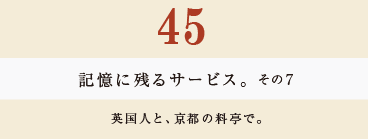お店につきます。
ため息がこぼれでるほどにうつくしい日本家屋。
ボクたちのために大きくひらかれた入り口の、
その内側からひんやりとした心地良い風が流れでてくる。
「お待ちしておりました」。
おだかやか、けれど凛と通る女性の声が
奥から響いてきます。
和服をキチッと着こなした、
おそらく70は越えてらっしゃるでしょう。
お年を召して小さくて、
けれどシャンと背筋の伸びた女性に
ボクらは出迎えられる。
「お靴をお脱ぎになりますか?」
嬉しそうに靴をぬぐ二人。
見事に磨き上げられた廊下を歩いて通された、
畳敷の座敷にあぐらをかきやすいようにと置かれた
座椅子に一堂座って、ユックリ、食事がはじまります。
うつくしく整えられた床の間、障子、
そして窓の向こうの日本庭園。
ため息をつくまもなく、
キリッと冷やした日本酒がふるまわれ、
それに続いて色とりどりの小さな器に前菜が、
一口ずつほど入れられて食卓の上にズラリと並ぶ。
「お嫌いなモノがなければよろしいのですけれど‥‥」
と、そう言いながらひとつひとつの料理が
簡単に説明されて、ボクらの食事ははじまります。
ところで、もし私たちが靴を脱ぎたくない‥‥、
と言ったら、どうしたのですか? と、彼らが聞きます。
ボクらの部屋の担当の女性がニコリと笑って答えます。
「椅子のお席がございまして、
そちらもこのお部屋と同じように
準備させていただいておりました。」
予約のときにお伺いすることもできたのでしょうけど、
ご予約を頂いたときのお客様と、
今日のお客様の気持ちが同じとは限りませぬゆえ、
可能なかぎりお客様のご要望に添えるように
準備をさせていただいております‥‥、と。
私達はお客様のたのしみのヒントを
いくつか用意するだけ。
どのたのしみが選ばれるかは、
すべてお客様の気持ち次第と心がけておりまして‥‥、
と。
申し遅れましたが、ここのお店の女将でございます‥‥、
と頭を深々下げて礼する。
まさにこここそファーストクラス。
彼らも感じ入ったのでしょう。
私はクラーク、私はヒルマンと
それぞれの名を彼女に告げて、
よろしくお願いいたします‥‥、と握手をもとめる。
ワタクシはトミ子と申しますが、
殿方から名前で呼ばれると胸がドキドキして、
器を持つ手が震えます。
ですからここでは、
「女将」と呼んでいただきますよう‥‥、と、
そういう彼女の頬がちょっと赤らむようで愛らしい。
次のお料理は夏豆のすりながしでございますが‥‥、
と次に続く料理の説明をして、異存がなければそれがくる。
ハモの季節で、けれど鰻のような‥‥、と
ハモの説明をしたら苦手という人にだけ、
ハモの代わりに鶏のササミの湯引きがきたりと、
料理までもが臨機応変。
西洋料理は「何を作るかメニューを揃える」のが
おもてなしの基本の基本。
日本料理は「季節季節の食材を揃えて、
お客様の好みにあわせメニューを誂える」
のが基本なのだ‥‥、と師匠は言います。
彼らはわかったような、わからぬような表情で、
たしかにこれほど高級な店でなければ
こうした対応もできぬであろう、とボクも思うほど、
その対応は洗練されていて素早く、的確。
|