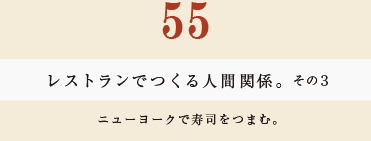歩き疲れてカフェに入って、
通りに面したテーブルにつく。
街行く人を眺めながら、お茶をたのしむ。
ニューヨークにいて、
一番たのしく贅沢な時間つぶしが
おそらくカフェでの人間観察。
あの人は、今晩、何を食べるんだろう?
肉の品揃えではマンハッタン1の食料品店の
ショッピングバッグを持った人をみると、
今日の晩ご飯はステーキなのかなぁ‥‥、とか。
もっぱらボクの観察対象は、
人そのものよりも人の胃袋みたいになっちゃう。
けれどそれもたのしく、あっという間に時間が過ぎる。
「それにしてもニューヨークって
いろんな人がいるのねぇ‥‥」
母のその一言に、ハッと我にかえってこう答えます。
「この人たち、ひとりひとりを待っている
レストランがあるっていうのが、
この街のステキなトコロなんだよネ」って。
「今晩、私たちを待っているお店って
どんなお店なのかしら‥‥、たのしみネ」
と、と母はウットリしながら答える。
時計を見ると程よい時間。
目当てのお店にむかいました。
これがかつてオイスターバーだったのか? と、
信じられないほどに見事な改装。
カウンターの中にはみるからにベテランの
腕のよい寿司職人という感じの人が、
ひとり凛々しく立っている。
もうひとり、若手のニコニコ顔の職人が
既に地元のお客様なのでしょう。
白人の老夫婦に流暢な英語で接客しながら、
寿司をにぎっている。
ボクら2人は、寿司が食べたくてしょうがないという
日本人‥‥、とホテルのコンシエルジュから
連絡があったのでしょう。
店長とおぼしきベテラン職人の前の席をもらって座る。
いらっしゃいませ。
当店のネタは築地と同じモノを仕入れておりますので、
日本の寿司を思う存分、おたのしみください。
そうニコヤカに告げるベテラン。
あら、たのしみだわ‥‥、と言いながら、
「お寿司をいただく前に手を洗わせていただきましょう」
と一旦、母が席をたつ。
母がもどるまで、カウンターを挟んだふたりは
手持ち無沙汰で会話をたのしむ。
地元のお客様も多くてらっしゃるんですか?
と、まずは質問。
日本人の観光客はワザワザ来たニューヨークで
寿司を食べようなんて思わない。
駐在しているビジネスマンも、
それほど頻繁に来てくれるわけでなく
やっぱりココで商売をしている限りは、
地元の人に来てもらわなくちゃ、仕事にならない。
最近、白人さんも寿司を珍しがって
食べに来る人が多くはなった。
けれどまだまだ、寿司の食べ方を
知らない人が多くてネ‥‥。
いきなりトロを注文したり、
おいしいからと同じネタばかり
続けざまにたのむ輩が多くて、
それじゃぁ、寿司の美味しさなんてわからないだろうって
思うんだけど、それも商売。
我慢や苦労が多いですよ‥‥、と。
お待たせしましたと母がもどって、
さぁ、何をにぎりましょうか? と。
母が言います。
「そうね、トロをいただこうかしら‥‥、
歩き疲れてコッテリとしたモノを最初に食べたいの」
あぁ、やっちゃったって思いはしたけど、
じゃぁ、ボクもとお相伴にあずかります。
いい寿司でした。
ネタも立派でなによりシャリがスキッとしてて、
確かに日本の寿司と同じと言っても
あながち誇張ではない。
とは言え口はさすがにトロの脂でペトッとしてくる。
お茶でそれを軽く流して、
「何かおすすめはありませんか?」と聞いてみる。
ボストンの沖のヒラメが
今日は脂がのってて旨いですよ‥‥、
と言われてボクはそれ。
「おかぁさんはどうするの?」
母の答えにボクとベテラン職人氏は腰を抜かすほど、
ビックラこいた。
「トロを続けていただくわ」
|