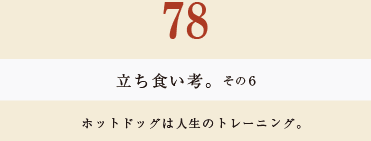考えてみれば朝からなにも食べてない。
ずっと緊張していたから、
その空腹に気づかなかったのでありましょう。
グーッのあとに、ギュルギュルグーッと
かなしげな音が続いて、
それが師匠の耳にも届いてしまったんでしょう。
クスッと彼は笑って大きな声で、
キッチンの方に向かってこう言います。
「君のパートナーは
朝ご飯を食べていないみたいだぞ‥‥、
私のホットドッグに今にもつかみかかりそうだ」と。
そして、ワハハと大きな声で笑ってボクの手を握る。
「もう忙しいコトもないだろうし、
今日の仕事はこれで終わりにしていいぞ‥‥、
ご苦労さん、ありがとう」
背中の後ろで声がして、振り返ったら店のご主人。
プレーンドッグを右手に2個。
空の左手をボクの腰の位置に突き出す。
腰に巻いてたつり銭入れのエプロンを、
ボクは外してオヤジに手渡し、
代わりにホットドッグを手にします。
熱々。
できたばかりのホットドッグの熱さが再び、
お腹を鳴らす。
1個はケチャップ。
もう1個には玉ねぎとピクルスをのせて、
食べる準備をしていきます。
隣で師匠は、ボクの手際をみながら
「あぁ、なんておいしそうなホットドッグ」
といいながら、小さく、
「You are a good pupil」と。
「よき弟子」と言われてボクはすっかり有頂天です。
彼はいつもの窓際のカウンターのところに向かう。
当然、ボクも彼のあとをついていき、
彼の隣でホットドッグをパクリといきます。
一口分ごとにケチャップやレリッシュをおき、
だから前歯が当たる場所には
邪魔するものがないソーセージ。
そしてパン。
それは驚くほどに簡単に、
唇も手も汚さずにプチュンと口にちぎれて飛び込む。
あぁ、これなんだ‥‥、と思いながら、
ボクは一口、また一口。
師匠もおなじように、一口、そしてまた一口。
そしてこんなコトをポツリポツリと、
ヒトリゴトのようにつぶやきます。
壁に向かってする食事は、一人で腹を満たす行為。
毎朝、そんなさみしい食事をするのはたまらんからネ。
壁ではなくて街に向かって食事をすると、
街を歩く人達と会話をしているような気にならないか?
あるいはレストランで食事をしているような
気持ちにもなる。
ひとりでいても寂しくならない。
そんな風には思わないか? と。
「なんか誰かに見られてるんじゃないかって、
ちょっと落ち着かなかったりしますけど‥‥」
そういうボクに、彼はいいます。
「人に注目されない人生を、
君が送っていいのだったら
壁に向かって食べるコトを
心地良いと思えばいいんだ」と。
実は彼。
ニューヨークではちょっと名前の通った
ジャズのピアニスト。
有名とは言っても知る人ぞ知る的アーティストで、
ジャズの世界に明るくはないボクが
知らぬのも当然のコト。
ステージでピアノを演奏することもある。
けれど、それよりレストランやパーティーなどで
演奏することの方が当然多く、
だから自分はステージの上で「見られる」よりも、
お客様を「見ながら」
ピアノを弾くことのほうが多いんだ。
だからいろんな人のいろんな姿を見ることが
仕事の一部になってしまった。
ときに人はあまりに無防備な姿を他人に晒す。
どんなにステキに装って、
どんなに立派に見える人でも
見なきゃ良かったと思わせられる姿を
私に見せるコトがあるんだよ‥‥、と、
彼はボクにこんな話をするのです。
|