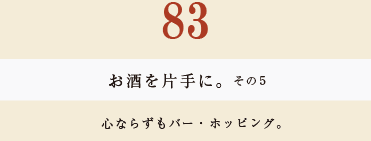|
ボクがニューヨークにやってくる数年前に
できたばかりというホテル。
当時、ニューヨークでは古いアパートを改装して
モダンなホテルに作り変えるのが流行ってて、
その代表的な一軒が、
ちょうどボクの住んでる家の近くにあった。
若いエグゼクティブをターゲットにして、
有名デザイナーが作ったというホテルで
大きなバーがある。
週末ごとにパーティや、イベントでにぎわっていて、
今日は平日。
静かに飲めるに違いない‥‥、と。
たしかにおしゃれなバーでした。
ファッションモデルのような見目麗しいバーテンダーが、
アルマーニな感じのユニフォームを着て
何をお飲みになりますか? と、
ニッコリしながら近づいてくる。
「クゥルヴォアズィエイ」はありますか?
そう聞くボクらに、ブロンドの
サラサラヘアーのバーテンダー氏が
怪訝そうな顔して聞きます。
「それは何かのカクテルですか?」と。
いえ、ブランデーなんです。
フランス産の。
だからフランス語で発音すると
「クゥルヴォアズィエイ」。
英語的に発音すると「コーヴァジェ」
ってなるのだけれど。
もしあれば、それをストレイト・アップで
飲んでみたいのですけれど‥‥、と、
ボクらは代わる代わる説明するも、答えはつれない。
ブランデーはあるにはあるけれど、
ほとんどカクテルのベースにつかってしまう。
そのまま飲めないことはないだろうけど、
はてさて、銘柄は一体なんだっけ‥‥、と。
ブランデーを飲むような人は来ないの? と聞けば、
ほとんどの人がマティーニや
マルガリータのようなモノを飲む。
一人でしんみり飲む人はほとんどいなくて、
みんな仲良く盛り上がってたのしく飲む。
そのたのしさを引き立てるような飲み物を提供するのが
ボクらの仕事だと思っているから、どうだろう。
うちで一番人気のあるダイキリを飲んでみては‥‥、
と、ウィンクしながらボクらに薦める。
しようがあるまい。
ボクはなんとかちょっとでも早くココを出たくて
それで、彼のオファーを受けることにする。
ジャンも同じ気持ちだったんでしょう。
ニコニコ、彼のサジェスチョンに頷きながら、
「あのウィンクって、ボクにじゃないよね、
エマにしたんだよね」って、
バーテンダーのクネクネ歩く後ろ姿を見ながら、
ボクの脇腹をつついて笑う。
エマがポツリとこう言います。
もしこの店に一人でワタシが座っていたら、
スゴくさみしげな女性に見えると思うのよ。
寂しい大人が出会いを待つ場所。
人を物欲しげにみせる雰囲気があって、
なんだかとても居心地悪い‥‥、と。
なるほど、ここは
酒を愛する人を相手にしたバーではなく、
ひとときハメ外すため
酒の力を借りる場所なんだと悟った次第。
陽気な鼻歌交じりにブレンダーをジャジャっと回して
彼が作ったカクテルは、イチゴの味のダイキリで、
大きなグラスにうんざりするほど
タップリ入ってやってきた。
うちのフローズンカクテルはみんなシロップを使わず、
フレッシュフルーツを使っているから飲み口がいい。
ラムもキューバ産。
しかも味わい濃厚なゴールドラムを使っているから、
フレッシュフルーツと混ぜても
本来のラムの香りを後口として感じるはずだ‥‥、
と、プロのバーテンダーらしきコトを
一生懸命ボクらに語る。
たしかにそれは飲み心地良く、
けれど知らずにアルコール分が体にたまって
気づけば酩酊におちいりそうな飲み物で、
ココにいては当初のボクらの目的は絶対叶わぬ。
さて、どうしよう。
ミッドタウンにフランス系のエアラインが経営している
ホテルがあったはず。
ほどよく高級。
バーもシッカリしていると聞く。
タクシーに乗れば10分足らずでつけるはず。
水っぽい溶けたイチゴのかき氷みたいなダイキリを
ほとんど残して、ボクらはそのホテルに向かう。
|