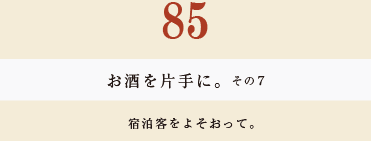驚くべきバーでした。
マホガニーの長いカウンター。
その内側の大きな壁の上から下まで
ギッシリ洋酒の瓶が並んださまは、
本の代わりに酒が並んだ図書館のような
厳粛にして壮大な景色がボクらの前にある。
カウンターの中にはバーテンダーが4人いて、
そのカウンターを囲むようにして
ソファテーブルがポツリポツリと置かれてる。
カウンターの奥の方。
3人並んで座れる場所をボクらはみつけて、腰をおろした。
鼻の下に白い髭を蓄えた、
やさしげな顔をしたバーテンダーがボクらに近づき、
ニコリとしながらこういいます。
「ようこそニューヨークへ‥‥、
何かお作りしましょうか?」と。
ボクらは首尾よく宿泊客を装うコトに成功したよう。
ジャンがニッコリ。
おもいっきりのフランス訛りの英語で言います。
「アナタ、クゥルヴォアズィエイ、オモチですか?」と。
ユックリ、ハッキリした英語で彼はこう答えます。
「ウィ、ムッシュ。
クゥルヴォアズィエイのご用意はございますが、
どんなクゥルヴォアズィエイをご用意しましょう」
再びボクらは無言になります。
またバーテンダー氏が
何を言おうとしているのかわからなくって、
目を丸くして固まっっちゃった。
彼は数回。
ユックリと、同じフレーズを繰り返し、
英語が通じないと思ったのか
ボクらの前に洋酒の瓶を次々おいて、
どのクゥルヴォアズィエイにされますか? と、
ジャンの目を見てニッコリとする。
並んだ瓶のラベルをみます。
なんたること。
どのラベルにも「Courvoisier」。
つまりクゥルヴォアズィエイとかかれていて、
どれがそれぞれどう違うのか、皆目検討つかずにお手上げ。
このバーをすすめてくれた、
さっきまでいたバーテンダー氏の
「皆さんがお飲みになりたいクゥルヴォアズィエイに
出会えますよう‥‥」
とボクらを送り出してくれた
謎の言葉の意味がやっとわかった。
そこまでしても、答えを出さぬジャンに
「Do you speak English?」
と、彼は困り果てた表情で、
コースターの裏にペンで書いてみせます。
もうしょうがない。
「英語はわかるのですけれど、
実は問題は英語の問題ではないんです」。
しょうがないから、ボクはバーテンダー氏に声をかけます。
「おぉ、いい英語を話されますね‥‥、
これは良かった、私が言っていることを
お友達に通訳してはくれませんか?」
と、ホっとした表情で言ったあと、しばし沈黙。
ボクの言葉を頭の中で反芻しながら、ユックリこういう。
「英語の問題でなければ一体、何が問題なのですか?」と。
実は宿泊客ではないということ。
そして何より、「クゥルヴォアズィエイ」という飲み物を、
実は今まで一度も飲んだことなどなくて、
今日はそれを教わりに来た。
バー使いの初心者なのだということを、
ボクらは彼に白状する。
「あなた方のようなお客様に出会えたことに、
ブランデーの神様に感謝せずにはいられませんな、
もしワタクシでよければ皆さんに
クゥルヴォアズィエイの極意を
ご教授させていただけませんか‥‥」
とウレシイ申し出。
断る理由はどこにもなくて、
たのしい授業のはじまりはじまり。
たのしい授業の内容は、さて来週といたします。
|