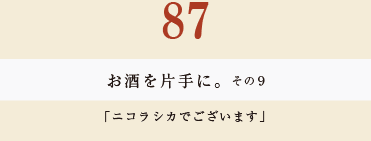ひとつめ。
そしてふたつめのグラスにトクトク、
クルボアジェが注がれる。
そして3つ目のグラスに、
瓶の口がキスをしようかというそのタイミングで、
エマが口を開きます。
殿方向きのカクテルだというコトならば、
レディーは失礼した方がよいのかしら‥‥、と。
レディーをハンサムにさせる
カクテルでもございますが‥‥、とウィリアムは言う。
「美男子」とかっていう意味でなく、
「立派で凛々しい」というときに使う、ハンサムですね。
女性を凛々しく見せるという、このキーワードに
エマが飛びつかぬはずもなく、
ならば、私もいただこうかしら‥‥、と。
結局、ウィリアムは3つのグラスにクルボアジェを注ぎ、
それから薄く切ったレモンを用意する。
デミタスカップの小さなソーサーの上に
一枚づつレモンをおいて、
カウンターの下からガラスのポットを取り出す。
中には白い結晶状の物体が、サラサラ揺れる。
それは何? と怪訝に見つめるボクたちに、
「グラニュー糖でございます」。
そして小さなスプーンで砂糖をすくう。
それをレモンの上にうず高く盛り、
ピラミッド状に形作ってレモンごと、
ブランデーを入れたショットグラスの上に
蓋するようにそっと置く。
「ニコラシカでございます」。
ロシアな名前。
そういわれれば、ロシア風の帽子をかぶった
グラスのようにも見えるコレ。
ただ、どのように飲めばいいのか、
にわかにわかりかねる謎に満ちた魅惑の飲み物。
マドラーやスプーンがあれば、
砂糖をレモンごと突き崩して
ブランデーと混ぜて飲めばいいのだろうけど、
そんなモノはなし。
それにウィリアムは
「口の中で仕上がるカクテル」
といいながら作ってくれたものでもあります。
もしや、大きな口を開け、
グラスをカプリとくわえ込むのか?
と、考えなやむ。
飲む前。
あるいは食べる前に想像力をかきたてるモノは上等。
その謎めいた挑戦を受けてたとうと、
好奇心がかりたてられる。
大きな灰皿をススッとウィリアムはすべらせ、
ボクらの前のさし出す。
そしていいます。
まずはレモンの両端を、
片手の親指と中指を使って持ち上げて、
軽く2つに折りたたみ
レモンの果肉を前歯でしごき
砂糖混じりのレモンジュースを口に含んで味わうのです。
ドライでスキッとした味がお好きであれば、
砂糖を指でつまんでどうぞ灰皿へ。
酸味をおさえたければ前歯でしごかず、
唇をつかってチュッと吸う。
レモンの皮も一緒にかじれば、
苦味が混じってビターな味わい。
甘み、酸味、そして苦味が口の中に広がったらば、
すかさずそこにクルボアジェ。
グラスの中のブランデーを
一度に飲むのもいいでしょうし、
ほんの少しだけまずはすすって、
そのあとユックリ、ブランデーの純粋な味を
たのしむコトもまた粋でしょう。
自分のイメージした味を、
口の中で作り出すことができる「あなたまかせ」、
バーテンダーとお客様とが一緒に作る
カクテルとでもいいますか‥‥。
なんてたのしい。
そしてなんて、ワクワクさせられるカクテルなんだろう。
ただナヤマシイのが
いろんな飲み方をためしたくなってしまうところ。
さて、どうしよう。
|