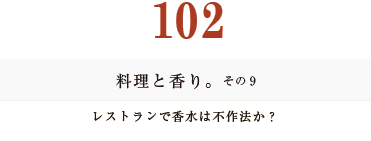どうするも何も、いつの間にか、
ボクが薦めたコトになっていて、
しかもやってくるのが父ではなくて母の友人。
こんなコトなら体をはって、
別のお店に予約をとるんだったのに。
後悔してもしょうがない。
たのしい会話で料理と料理の間をなんとかしのいで、
ワインの力を借りればなんとかなるだろう‥‥、
と思っていたら、母がいう。
ところでお二人は、お酒をお飲みにならないから、
あなたもその日は我慢するのよ‥‥、って。
絶望的な気持ちになって、それでまずはこの難局を
一緒に乗り切ってくれる仲間を探すことにする。
さいわい英語に堪能なお二人で、
それでエマに相談をする。
それは大変な課題をしょいこんじゃったわねぇ‥‥。
でも。
任せておきなさい。
あなた、私と友達だってよかった‥‥、
って感謝することになると思うわ。
そしてその日がやってくる。
ホテルまでエマと2人で出迎えにゆく。
珍しいコトに香りをまとっていないエマ。
長身のご主人と、
コロコロ転がるような声が笑顔に似合った奥様。
ほどよきお洒落を着こなして、
目的の店のウェインティングルームの
大げさな王朝趣味のソファにも負けぬ瀟洒な雰囲気。
ソファの横には暖炉であります。
パチパチはぜる燃える薪が、
むせるような森の香りを
レストランの前室一杯に漂わせている。
「なんだかこの薪の上にお肉をのせて
食べたくなるわネ‥‥、
お腹が空いてくるような素敵な匂い!」
このお店は炭で焼き上げた
Tボーンステーキで有名ですのよ。
それ以外のお料理は、あまりオススメできませんけど、
この森の香りに包まれてこんがり焼けたお肉のコトを
頭に思い浮かべていれば、
2時間なんてあっという間のコトですわ!
エマはあっさり、ネタばらし。
「あら、2時間も‥‥、そんなにタップリ、
おしゃべりを楽しむコトができますのね」。
それにしてもボクたちの周りで
テーブルに案内されるのをまっているご婦人方。
その何人かが奔放なほどに
香りのお洒落をたのしんでいる。
香水はレストランでは無作法じゃございませんこと?
という奥様に、エマはいいます。
確かにこのウェイティングルームは人口密度が高くて、
しかも暖炉があるから部屋の温度が少々高い。
香りが華やかに立ち上り気になったりするかもしれない。
けれどココのダイニングルームは、
隣合うテーブルの間隔がユッタリしていて、
香り同士が喧嘩したりすることがない。
私も実はオキニイリの香水を
もってきているのですけれど、
失礼でなければ使ってみたいのですけれど‥‥。
ハンドバッグの中から小さなガラスの瓶を取り出す。
奥様の目がニコリと輝く。
さて、来週‥‥、香りのマジック、はじまります。
|