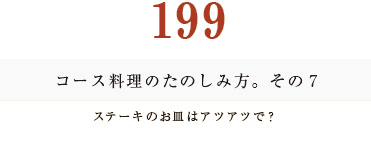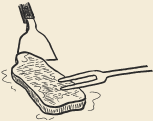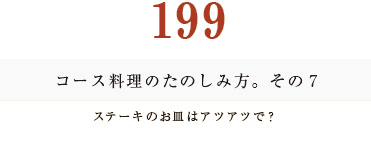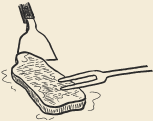ファミリー向けの郊外ステーキハウスが増え始めた
1980年代の半ばのコトだったでしょうか。
おいしいステーキを味わうコトができるのに、
「なんで鉄板でステーキを出さないの?」
っておっしゃるお客様が増えたのだと。
それが理由か、お客様の数も減り気味。
なんとかできないでしょうか?
と、そんな質問を受けたコトがあるのです。
コンサルタントとしてこういう依頼ほど困ることはない。
だって今のままで十分おいしいのに、
お客様がもっとおいしいやり方があるだろうと、
素人考えの見当違いな要望をいう。
それに答える姿勢を見せないと、
努力不足だとか、お客様思いじゃないとか言われる。
そのまま鉄板を導入したら、
確実にステーキの品質は下がる。
おいしいままで。
鉄板でやってくるステーキ以上に
熱々感と臨場感をお客様に味わっていただくことが
できればいいんだけれど‥‥、と、
もうそれは大変な仕事になった。
まず鉄板探しから。
肉を焼くことが目的でなく、ステーキを食べ終わるまで、
つまり20分ほどは温かさを持続させるのが
求める鉄板の目的。
だからタップリ蓄熱し、
その蓄えた熱をユックリ放出するような素材や厚さ。
簡単なのは分厚い鉄板の裏側だけを温めれば、
肉を乗せる部分は適温。
じんわり肉を温め続けてくれるのだけど、
そういう鉄板は恐ろしく重たくて
スマートサービスの妨げとなる。
当時、鉄板で提供するスタイルのステーキ店で、
腕や手首を痛めるサービススタッフが
続出したりもしていたのです。
だから軽くて、しかも保温性の高いものをと、
探しに探した。
結局、思うようなモノがなくて、
鋳物で新たにこさえることになったのだけど、
今度はそれの温め方。
早く食べるところは熱々でもいいけれど、
ユックリ食べる部分はほどよき熱さでなくては
熱が入り過ぎちゃう。
ほとんどの人は右利きで、
ナイフとフォークで食べるとき、右側から食べ進む。
だから皿の右側を集中的に温めて、
左側へと熱伝導を促すことで、
長時間、お皿の上に置かれた肉も
熱が入り過ぎないようにと工夫する。
それでも直接、お皿に触れた肉が焦げてしまうから、
玉ねぎを敷く。
その玉ねぎも生だと肉の匂いを邪魔してしまい、
ソテしすぎると食べてるうちに焦げて炭になってしまう。
だからほどよく熱の入った状態を
何度も何度もためして決める。
これで20分ほど、
ずっと同じ温かい状態を保つことができたのだけど、
肝心のジュウジュウ、油がはぜるような
シズル感がまだ弱い。
ソースをかければ湯気は出る。
けれどそれが焦げると不快な味や匂いを発する。
ならばと牛肉と骨で作ったブイヨンを提供する前、
鋳物のお皿の上に吹きかけ
湯気と香りをまき散らしつつ
お客様の手元にお届けするのはどうか‥‥、と。
そこまで辿り着くのに3ヶ月ほどの期間を要し、
結果、そのステーキハウスの名声は
揺るぎないものになったのでした。
|