持ってきた地図を広げると、
キーンさんは沖縄の海岸線を目で追い、
読谷(よみたん)という地名を口にした。
このあたりですね、と私が指さすと
キーンさんは大きく肯いてみせた。
1945年4月1日、
アメリカ軍が沖縄に上陸する。
地形が変わるほどの艦砲射撃を
沖縄にふらせたあとの上陸だった。
沖縄の土を踏んだキーンさんは
予期しない出来事に遭遇する。
目に飛び込んできたのは
日本兵ではなく、女性だったのだ。
30歳くらいの女性が子どもを連れて
浜辺をうろついている。
キーンさんは走っていき
「こんなところにいたら危ない。
安全なところに連れていってあげるから
逃げなさい」と言った。
ところがその女性は
訳のわからないことを口にするばかり。
それもそのはず、沖縄の言葉は
日本語を学んだキーンさんといえども
理解不能だったのだ。
そのためキーンさんは沖縄の少年を通訳にし、
ガマという呼ばれる天然の洞窟を見つけては
隠れている沖縄の人々に出てくるよう呼びかけた。
上陸した初日、2人の日本人が捕虜となる。
そのうちのひとり、海軍士官は
捕虜となったことを恥じ、
罪悪感にさいなまれている。
見かねたキーンさんは数日して
彼に会いに行き、会話を交わす。
海軍士官はこうキーンさんにこう言ったという。
「敵軍の兵士ではなく、
どうかひとりの同じ学徒兵として
自分と話をしてくれないか」と。
学徒兵とは学生でありながら
戦争に駆り出された兵士のこと。
キーンさんはもちろん同意する。
すると彼は言った。
「自分は生きるべきだろうか、死ぬべきだろうか」
この海軍士官は自殺してしまうのではないか。
アッツ島で見た日本兵の“玉砕”が
キーンさんの脳裏に焼きついてた。
何があっても生き続けるよう、
キーンさんは説得を続けたという。
その話を聞いて、私は複雑な思いを抱くことになった。
日本軍は“玉砕”を奨励し、
神風特攻隊で、自らの命を捨てることを
若い兵士に強要したといってもいい。
早い段階で負けるとわかっていた戦争なのだ。
戦後の日本の復興を考えて
若い人材を確保しておこうといった重層的な
考えをしていた人はいなかったのだろうか。
一億総“玉砕”の一歩手前まで
行きかけた状況を考えると
少なくとも意思決定をできる立場にいる人の中には
いなかったのだろう。
キーンさんも自分の乗った船めがけて
特攻の戦闘機が飛んできたという体験をしている。
結局、船のマストにぶつかったことで、
そのまま海に落ちていったが
キーンさんにとって死に最も近い瞬間となった。
そんなキーンさんが
海軍士官に死なないように説得したのだ。
日本軍は自国民に死ねと命じ、
ひとりのアメリカ人が生きろと説く。
私はキーンさんの穏やかな瞳を見つめた。
沖縄戦のあと、キーンさんはハワイに戻り、
そのあと派遣されたグアムで
日本が降伏したことを知る。
「戦争が終わるということは
まったく信じられなかった。
でも夜、隣の船の灯りを見て、
戦争中は灯りをつけていないから見えない、
でも光が見えたことで
やっぱり戦争は終わったんだと初めて感じました。
とてもほっとしました。
もう殺し合いはないのだと」
戦争が終わって、ようやく抱いた安堵の思い。
それでもキーンさんのなかで
日本人の謎は残ったままだった。
“玉砕”とは何だったのか。
そしてそんな思いも薄れかけたころ
キーンさんはふたたび“玉砕”と
向きあうことになる
戦争が終わってすでに50年がたっていた。
(続く) |



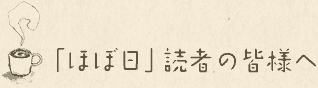
![キーンさんの見た玉砕[4]](images_new/20150512_title.gif)